万力地区は、山梨市役所の南西約1kmの笛吹川右岸(市役所の対岸)です
山梨市役所西側の中央通りを南へ、約900mの「山梨市駅前」信号を右(西)へ県道216号線です
約300mで笛吹川を根津橋で渡って直ぐを右(北)へ入ると、万力公園の駐車場です

万力公園管理事務所前の広場に大きな根津嘉一郎翁銅像を見ました
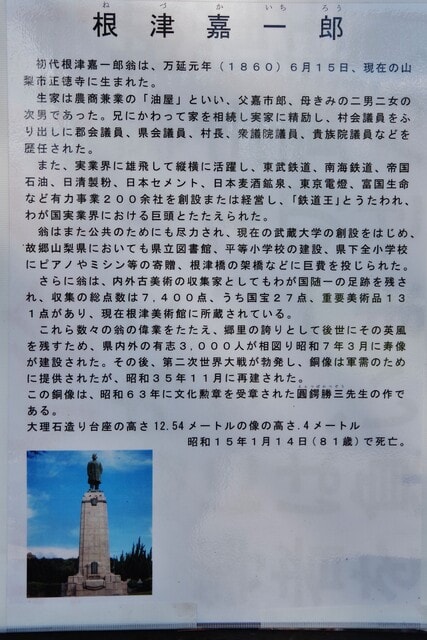
説明版です
根津嘉一郎
初代根津嘉一郎翁は、万延元年(1860)6月15日、現在の山梨市正徳寺に生まれた。
生家は農商兼業の「油屋」といい、父嘉市郎、母きみの二男二女の次男であった。兄にかわって家を相続し実家に精励し、村会議員をふり出しに郡会議員、県会議員、村長、衆議院議員、貴族院議員などを歴任された。
また、実業界に雄飛して縦横に活躍し、東武鉄道、南海鉄道、帝国石油、日清製粉、日本セメント、日本麦酒鉱泉、東京電燈、富国生命、など有力事業200余社を創設または経営し、「鉄道王」とうたわれ、わが国実業界における巨頭とたたえられた。
翁はまた公共のためにも尽力され、現在の武蔵大学の創設をはじめ、故郷山梨県においても県立図書館、平等小学校の建設、県下全小学校にピアノやミシン等の寄贈、根津橋の架橋などに巨費を投じられた。
さらに翁は、内外古美術の収集家としてもわが国随一の足跡を残され、収集の総点数は7400点、うち国宝27点、重要美術品1131点があり、現在根津美術館(東京都港区南青山)に所蔵されている。
これら数々の翁の偉業をたたえ、郷里の誇りとして後世にその英風を残すため、県内外の有志3000人が相図り昭和7年3月に寿像が建設された。その後、第二次世界大戦が勃発し、銅像は軍需のために提供されたが、昭和35年11月に再建された。
この銅像は、昭和63年に文化勲章を受章された圓鍔勝三先生の作である。
大理石の土台の高さ12.54mの像の高さ、4m。
昭和15年1月14日(81歳)で死亡。
*今日に残る各会社を利用させて頂いておりますので、創業者の銅像がその故郷にあるべきことを感じますね

公園の中央の通りを北へ進みます

道路右手に目的のアカメヤナギです

南側から、目通り幹囲4.0mの大木のはずですが、幹が倒れてしまっているので、細くなっているかもしれませんね~

北西側から

水路の北側からアカメヤナギを見ました

万力公園案内図です
万力林
万力林について
差出磯の堤は、昔笛吹川が洪水でたびたび決壊し下流の村々に大きな被害を及ぼしました。
この場所は、県内の洪水を防ぐ上で竜王の鼻(信玄堤)近津の堤(笛吹川・日川・重川の合流点)とならび三大水難所の一つとして知られて来ました。
15世紀の守護領は、石和(現笛吹市)にあり、万力堤と近津堤により守られていました。
永正14年(1517年)武田信虎(信玄の父)は、度々大洪水の被害を受け、甲府へ転出しました。
その後も天正11年(1583年)の大洪水で家や田畑が流出し、慶長5年(1600年)徳川氏は、堤防を増築し、田や畑に木を植えて水防林として木を切ることをきびしく禁じました。
明治34年(1901年)「水害防備林」に編入され今日に至っています。
この万力林は、もし洪水時に笛吹川が氾濫した場合は、密生している松の大木の中を流れる事により水の勢いを弱め、流木や土砂を防除するとともに、下流部の開口部(霞堤)から笛吹川に戻す治水施設です。また万が一、笛吹川の流れが万力林からあふれた時には、台地にぶつけ水が町へ流れないような地形的特徴も利用しています。
「万力」の地名は、南北朝時代の記録にもありますが万人の力を合わせて堅固な堤防とする願いを込めて付けられたと伝えられています。
霞堤とは
霞堤とは、堤防と堤防のあいだにすきまをつくり不連続とすることによっり洪水時には開口部から河川から洪水が逆流し河川の水位を下げることや支流の排水や内水排除を行うことなどの機能がありますが、万力林の霞堤は、主に急流河川である笛吹川の洪水があふれた時、氾濫水が拡大しないように開口部から河川へ戻る役目をしています。
国土交通省 甲府河川国道事務所
公園を散策してみましょう


公園東側の笛吹川の堤防です

丸い石が積み上げられています

がん業堤の説明版です

こちらも同じですね






公園中ほどに万力公園動物広場の南側に鹿苑です



カピバラです



マーラです

公園内では、多種の鳥が観察できるようですが、暑さの為かこの日は静かでした
では、次へ行きましょう

山梨市役所西側の中央通りを南へ、約900mの「山梨市駅前」信号を右(西)へ県道216号線です
約300mで笛吹川を根津橋で渡って直ぐを右(北)へ入ると、万力公園の駐車場です

万力公園管理事務所前の広場に大きな根津嘉一郎翁銅像を見ました

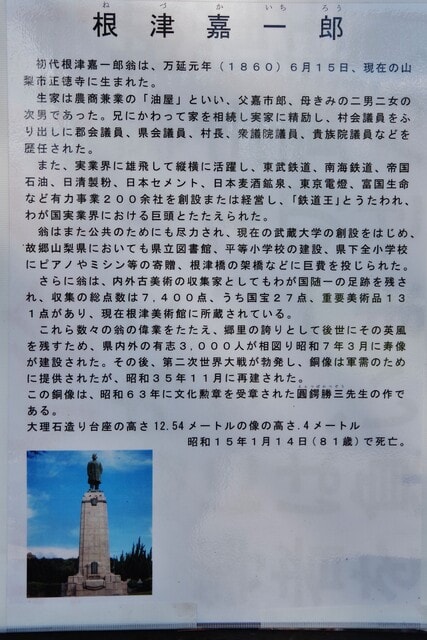
説明版です
根津嘉一郎
初代根津嘉一郎翁は、万延元年(1860)6月15日、現在の山梨市正徳寺に生まれた。
生家は農商兼業の「油屋」といい、父嘉市郎、母きみの二男二女の次男であった。兄にかわって家を相続し実家に精励し、村会議員をふり出しに郡会議員、県会議員、村長、衆議院議員、貴族院議員などを歴任された。
また、実業界に雄飛して縦横に活躍し、東武鉄道、南海鉄道、帝国石油、日清製粉、日本セメント、日本麦酒鉱泉、東京電燈、富国生命、など有力事業200余社を創設または経営し、「鉄道王」とうたわれ、わが国実業界における巨頭とたたえられた。
翁はまた公共のためにも尽力され、現在の武蔵大学の創設をはじめ、故郷山梨県においても県立図書館、平等小学校の建設、県下全小学校にピアノやミシン等の寄贈、根津橋の架橋などに巨費を投じられた。
さらに翁は、内外古美術の収集家としてもわが国随一の足跡を残され、収集の総点数は7400点、うち国宝27点、重要美術品1131点があり、現在根津美術館(東京都港区南青山)に所蔵されている。
これら数々の翁の偉業をたたえ、郷里の誇りとして後世にその英風を残すため、県内外の有志3000人が相図り昭和7年3月に寿像が建設された。その後、第二次世界大戦が勃発し、銅像は軍需のために提供されたが、昭和35年11月に再建された。
この銅像は、昭和63年に文化勲章を受章された圓鍔勝三先生の作である。
大理石の土台の高さ12.54mの像の高さ、4m。
昭和15年1月14日(81歳)で死亡。
*今日に残る各会社を利用させて頂いておりますので、創業者の銅像がその故郷にあるべきことを感じますね


公園の中央の通りを北へ進みます


道路右手に目的のアカメヤナギです


南側から、目通り幹囲4.0mの大木のはずですが、幹が倒れてしまっているので、細くなっているかもしれませんね~


北西側から


水路の北側からアカメヤナギを見ました


万力公園案内図です
万力林
万力林について
差出磯の堤は、昔笛吹川が洪水でたびたび決壊し下流の村々に大きな被害を及ぼしました。
この場所は、県内の洪水を防ぐ上で竜王の鼻(信玄堤)近津の堤(笛吹川・日川・重川の合流点)とならび三大水難所の一つとして知られて来ました。
15世紀の守護領は、石和(現笛吹市)にあり、万力堤と近津堤により守られていました。
永正14年(1517年)武田信虎(信玄の父)は、度々大洪水の被害を受け、甲府へ転出しました。
その後も天正11年(1583年)の大洪水で家や田畑が流出し、慶長5年(1600年)徳川氏は、堤防を増築し、田や畑に木を植えて水防林として木を切ることをきびしく禁じました。
明治34年(1901年)「水害防備林」に編入され今日に至っています。
この万力林は、もし洪水時に笛吹川が氾濫した場合は、密生している松の大木の中を流れる事により水の勢いを弱め、流木や土砂を防除するとともに、下流部の開口部(霞堤)から笛吹川に戻す治水施設です。また万が一、笛吹川の流れが万力林からあふれた時には、台地にぶつけ水が町へ流れないような地形的特徴も利用しています。
「万力」の地名は、南北朝時代の記録にもありますが万人の力を合わせて堅固な堤防とする願いを込めて付けられたと伝えられています。
霞堤とは
霞堤とは、堤防と堤防のあいだにすきまをつくり不連続とすることによっり洪水時には開口部から河川から洪水が逆流し河川の水位を下げることや支流の排水や内水排除を行うことなどの機能がありますが、万力林の霞堤は、主に急流河川である笛吹川の洪水があふれた時、氾濫水が拡大しないように開口部から河川へ戻る役目をしています。
国土交通省 甲府河川国道事務所
公園を散策してみましょう



公園東側の笛吹川の堤防です


丸い石が積み上げられています


がん業堤の説明版です


こちらも同じですね







公園中ほどに万力公園動物広場の南側に鹿苑です




カピバラです




マーラです


公園内では、多種の鳥が観察できるようですが、暑さの為かこの日は静かでした

では、次へ行きましょう




































