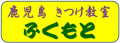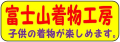日本舞踊になくてはならない「きもの」の着付け。
なくてはならない、「帯」と「帯締め」。
この「きもの」と「帯」と「帯締め」の三点セットは、「現代のきもの姿」には欠かせません。
江戸時代にはなかった「帯締め」
ところで江戸時代の組紐といえば
鎧(よろい)兜(かぶと)や、刀の下緒、鷹匠の紐などに使われていたのが組紐ですから、いわば侍の象徴。
その組紐を、「きものの帯締め」として使ったとしたら、厳しい詮議を受けること間違いなしです。
また、高価すぎて、手も出せません。
帯締めは、明治維新の廃刀令後、組紐の皆さんの生きる術(すべ)として、生み出された結果です。
「帯締め」が登場するのは
きもの姿に帯締めが登場するのは江戸末期。
黒い煙を吐きながら、黒船が浦賀沖に現れるころ、丸絎(まるぐけ)の帯締めが先に登場します。
しかも締めていたのは庶民ではありません。身分の高い方々です。
帯も全通で「つの出し」を…
ですから私たち衣裳方は、日本舞踊の古典の演目で、帯締めや六通の帯を使うことをためらいます。
現代の六通の帯は、京都西陣の商魂の中から生み出された帯。つの出しを結ぶと、残念なことに無地の部分が表に出てしまいます。
ですから、出来たら全通の帯を使いいたと願うのです。
もちろん、どんな帯でも帯締めは使わずに「つの出し風」には結びますが…。
時代劇などで登場する「つの出し」なども、全通の帯で、帯締めを使わずに粋に着せています。
やはり着付けは、時代考証を通してみると、時代物がおもしろいですね。