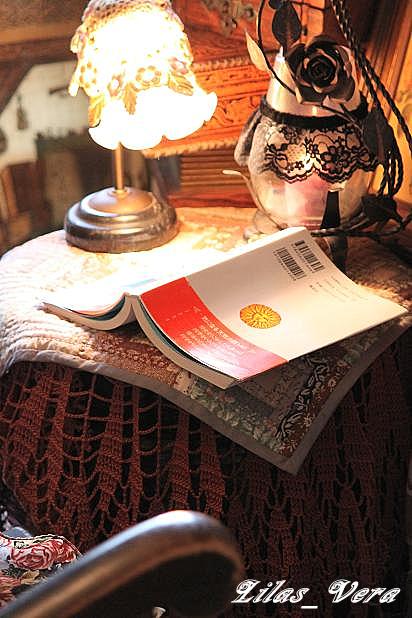
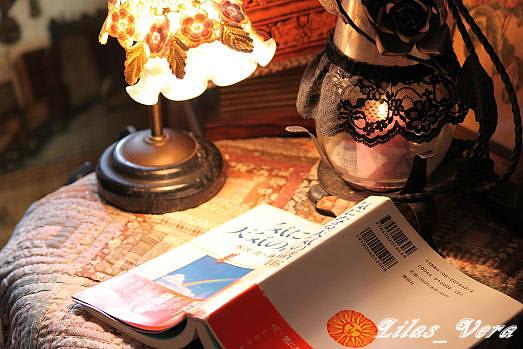

【午前7時半の空】
連日、晴れの天気が続きます。
そう言えば、今年になってからまだ雨を見ていません。
寒さもちょっと一休み。
昨日に引き続き、穏やかな冬日和です。
今日も趣きのある空と共に1日が始まりました。

| 古代人は、豊かな収穫は神の恵みであり、 不作は神の機嫌を損ねたせいだと信じたから、 厳粛な農耕儀礼を持ち、 農作物が豊かに実るような天気を その儀礼によって得ようとした。 天気に対するまじないの力が1番強い人が キミ(気見)すなわち “君” であり、 それに対して田のめんどうを見る人が タミ(田見)つまり “民” である、という 語源説さえある。 日本人の、天気に対する挨拶も、 そういったまじないが 日常語化したものとみていい。 【水沢周・藤井幸雄 「気になる天気の話146」】 |
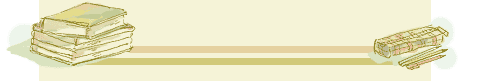
さて、今年に入ってなぜか古代人(いにしへびと)に想いを馳せている私。
そんな私が何気なく手に取ったのは、
 の本。
の本。 『気になる天気の話146』 という本です。(冒頭の写真)
お天気の本ですから、たいして期待もせず、
パラパラとめくっていたものです。しかしながら・・。
気象という言葉が日本で初めて使われたのは、
『古事記』 だというではありませんか。
その序文には、ニュートンもびっくり? の科学記述が。
そこには日本という国の成り立ち(イザナギの神)から、
様々な神が登場して来ます。まさに神の国。
ついつい引き込まれて一気に読んでしまいました。
因みに 「天照(アマテラス)」 は太陽と昼、
「ツキヨミ」 は昼と夜、そして 「スサノオ」 は海を支配する神様です。
どうやら日本の天気の話は、神様と無縁ではないようです。
それに日本人ほど天気の話題が好きな民族もありませんものね。
(私もその1人に入りますけれど)
手紙の時候の挨拶もそうですし、「こんにちは」、
「今晩は」 でさえ、その後に天気の事が略されている形と言いますから。
ところで日本国歌の 「君が代」。
日本国民でありながら、アレルギーの多い国歌のようですが、
↑ の記述は成程・・と思えます。
最後に。高校生の歌う素晴らしい 「君が代」 を。
そして余談ながら、この 「君が代」、
「世界の国歌ベスト6」 の4位に入っていました。
尤も何の根拠もないのでしょうが・・。(YOU TUBEで)











