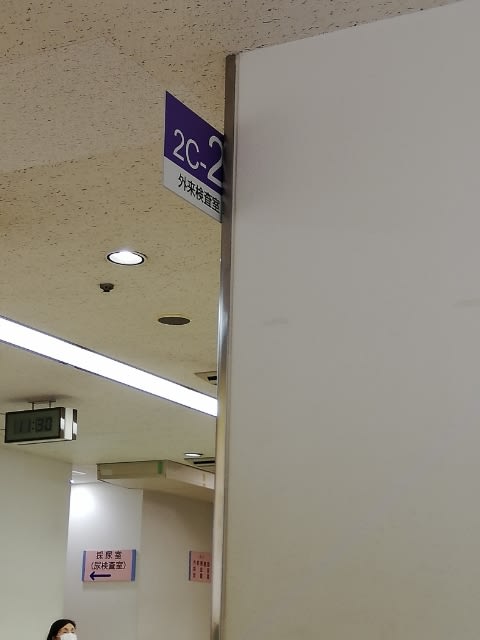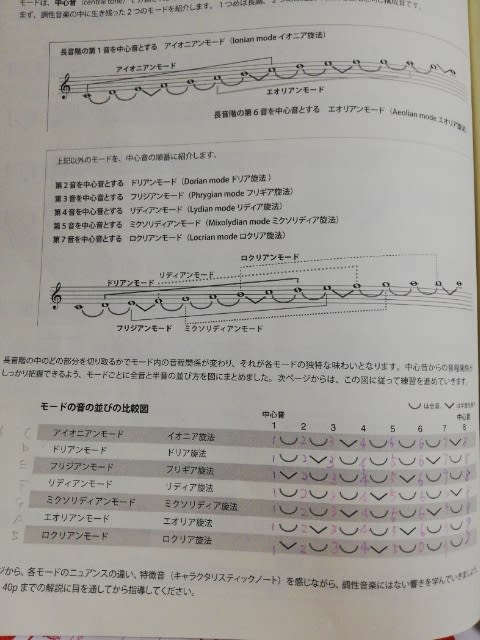「音 言葉 人間」1980年 岩波書店 作曲家武満徹と川田順造の往復書簡です。
文字の無い世界モシ族の社会の中に入って研究する川田さん。
そういう風土ではエクリチュール=書き言葉は太鼓や笛。
特に太鼓が空間や世代を越えて言葉を伝えて行く。
音楽という言葉も無いそうです。
太鼓を叩く動作を通して、身体と強く結びついた音と言葉をなんとかつかもうとアフリカの大地をさまよう川田さんと、
ニューヨークやフランスに住んで、日本の音楽のことを深く考察するようになったという武満徹さん。
一音成仏
さわり
という美的感覚は、日本の音楽の特徴だと言います。
音によって表すのではなく、「音に聴く。」
技巧を駆使していた演奏家が事故によって左手が使えなくなった後、かえって一音の深みがましたというようなこと。
三味線と謡いが違う時間軸で演奏され、合わせようとするのではなく、違うように演奏することによって絶妙にどのようにでも間が合う…。
ノーベンバー ステップスなど邦楽とオーケストラを融合させた音楽で世界を席巻した武満徹さんが何を考え、どういうことを目指して作曲していたのかを
考えるよすがになる本でした。