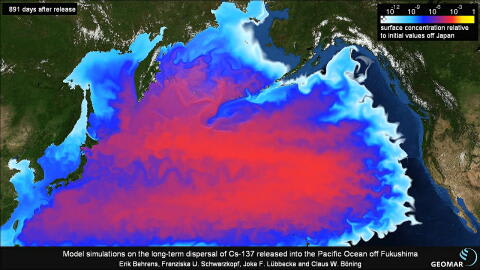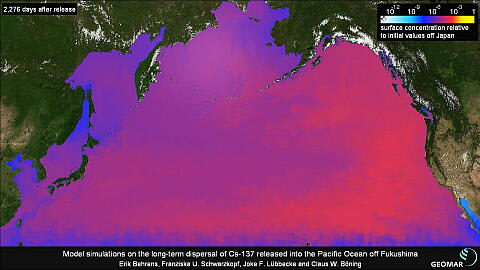もうふたつ、東京新聞の記事を書き起こししました。
このふたつの記事は、最近かなりキナ臭い、民主主義を国家主義に変えてまえと企んでる輩の言動について書かれたものです。
東京にお住まいの目良氏の意見↓とともに、紹介させていただきます。
今朝(8/27)の『東京新聞』11面「記者の眼」欄で、
「国際常識欠いたアソウ発言 ナチス否定こそ民主主義」と題し、三浦耕喜記者がアソウ副総理の「ナチス」発言を鋭く批判しています。
「徹底したナチスとの断絶こそ、国際社会でドイツが信用を得る基盤だ。」
そうです。
アソウはその、「ナチスの手口に学んで改憲を」と発言したのです。
そして、そのナチスと戦前、ムッソリーニ・イタリアをふくめて三国軍事同盟を結んだのが、戦前の皇国・軍国主義日本でした。
アソウ発言の内外の反発の広がりに慌てたアベ政権は、「ナチス政権を肯定的に捉えることは断じてない」との政府答弁を閣議決定しました。
しかし、戦後68年も経ってなお、このような恥ずべき釈明をせざるを得ないのは、
実はこの政権が、安倍首相を先頭に、ナチス政権と軍事同盟を結んだ戦前の皇国・軍国主義日本との「徹底した断絶」どころか、
皇国・軍国主義日本が行った侵略戦争を美化し、大日本帝国憲法体制への郷愁を、思想的にも人脈的にも色濃く持っているからにほかなりません。
はっきりさせましょう。
ドイツが欧米社会で、「信用を得る基盤」が「徹底したナチスとの断絶」だとするならば、
わが日本が、特に近隣アジア社会で「信用を得る基盤」は、ナチスと同盟した戦前の「皇国・軍国主義日本との徹底した断絶」なのです。
戦後日本は、アメリカの反共軍事戦略に組み入れられ、協力する見返りに、「皇国・軍国主義日本との徹底した断絶」を免れ、
社会のあらゆる面で、それとの連続性が保たれてしまいました。
そして、そのもっとも代表的な存在が、自民党という政党なのです。
アベ首相は、その自民党の中でもひときわ、人脈的にも思想的にも、「皇国・軍国主義日本」との連続性の強い存在です。
アソウ「ナチス」発言の根底にあるのは、ナチスと同盟した戦前の、「皇国・軍国主義日本」への郷愁・親近感なのです。
僕たちは今こそ、戦前の「皇国・軍国主義日本」との「徹底した断絶」を求め、内外に宣言し、
それを否定しようとするアベ暴走亡国対外犯罪的政権のたくらみと、たたかうことを決意すべきだと思います。

ナチス否定こそ民主主義
【東京新聞・記者の目】2013年8月27日
国際常識欠いた麻生発言
麻生太郎副総理兼財務相は、首相経験者の中では、英語使いで知られる。
外国要人と会談しても、肩をたたきながら冗談を交わす。
だが、いくら言葉が上手だろうと、座談が面白かろうと、民主主義をめぐる国際社会の常識に欠けては、信用は得られまい。
(三浦 耕喜)
ベルリンのドイツ連邦議会議事堂に、5枚一組の大きな絵がかかっている。
描かれているのは、闇の中に巻き上がる炎。
火の渦から人の背骨が浮かび上がっている。
チェコ生まれの芸術家カタリナ・ジーバーディングが、1992年に制作した『迫害された議員のために』という作品だ。
ナチスは、民主的に選ばれた議員を追放し、殺害し、民主主義を破壊する中で権力を握った。
闇は絶望を表し、炎はナチスの暴力を意味する。
それでも焼かれない背骨は、再生する民主主義の象徴だ。
「ドイツの民主主義は、灰からよみがえった」
議会が付した説明には、こう記されている。
今日の民主主義は、多くの犠牲によって築き上げられてきた。
奪われ、焼かれ、殺され、そのたびに人々は、再生への努力を重ねた。
ゆえに、民主主義を守るには、常に、それを破壊する思想と戦わなければならない。
それが、民主主義を確立した、諸国民の常識だ。
その思いと行動を共にすることが、外交の場で語られる「民主主義の価値観を共有する」ことの重要な要素だ。
ドイツ連邦議会が、ドイツの侵略を受けた国からも作品を求め、議員への戒めとしているのも、
二度とナチスなるものを復活させない決意の表れだ。
市民もナチスを許さない。
ベルリン特派員だった時、ネオナチの集会に対抗する市民が、デモで道をふさぎ、半ば実力で阻止するのを、何度も目にした。
普段は厳しく批判し合う保守系とリベラル系の政治家も、肩を組む。
徹底したナチスとの断絶こそ、国際社会でドイツが信用を得る基盤だ。
だとすれば、麻生氏が、日本の憲法改正をめぐり、
「あの手口を学んだらどうか」と、ナチスを引き合いに出したことは、
「民主主義の価値観を共有する」と宣言する日本の立場に、重大な疑問をもたらす。
ナチスの『闇と炎』は、今も生々しい傷だ。
それを知るなら、ワイマール憲法がナチスによって踏みにじられたことを、「誰も気づかないで変わった」と言えるばずがない。
麻生氏は発言を撤回し、政府は「ナチス政権を肯定的に捉えることは断じてない」との答弁を、閣議決定した。
当たり前のことを、あえて確認せざるを得ないのは、不信感を意識する裏返しだ。
野党に責任を問う力は乏しく、与党側には乗り切った感さえ漂う。
だが、その姿全体もまた、日本は本当に、民主主義のパートナーたり得るのかとの疑問を強めるだろう。
そのような政治を許すことで、傷つくのは日本の国益だ。

「ゲン」制限撤回 手続きのみ問題視
【東京新聞・夕刊】2013年8月27日
知る権利 踏み込まず
松江市教委
漫画『はだしのゲン』をめぐる松江市教委の閲覧制限は、学校への教育行政の指導が、どこまで許されるのかという、重い問題を突き付けた。
学校の自主性を尊重した、要請撤回の判断は妥当だが、なぜ撤回しなければならなかったかについては、議論が尽くされたとは言えない。
市教委が問題視したのは、意思決定のプロセスだった。
法に触れないとはいえ、図書館の運営権を持つ学校に対し、熟慮せず、二度も閲覧制限を要請した市教委事務局の姿勢は、撤回の論拠とはならなかった。
強制力を感じた多くの校長が、要請に従った事実もある。
「過激な描写を踏まえた教育上の配慮」と、制限の理由を説明し続けた市教委。
しかし、ある幹部は、「ここまで大きな問題になるとは……」と漏らした。
全国から批判が相次いだ後、子どもの知る権利と表現の自由を侵す可能性のある閲覧制限の重みに、初めて気付かされたという。
市教委事務局は「重要事項は教育委員に諮る」とする規則があるにもかかわらず、内部協議だけで、閲覧制限を決めていた。
この価値判断の甘さにも問題があった。
戦争体験者が高齢化する今、戦争の記憶をどう継承するのか、というテーマも問い掛ける。
戦争を知らない子どもたちが、多様な図書を読む機会を保障するべきではなかろうか。
作品全体の文脈を軽視し、一シーンの表現を過剰に規制する動きが、学校現場に広がってはならない。
(樋口浩二)
「撤回は当然」「根拠に不満」傍聴の市民ら
「撤回は当然」
「最後で踏みとどまった」
26日開かれた松江市の教育委員会議。
傍聴した市民らは、撤回の結論を評価する一方、手続き上の不備のみを根拠としたことに、不満の声も上がった。
市役所3階の部屋には、会議が始まる1時半前から、市民らが集まり始め、約40人が席を埋めた。
会議を傍聴した、東京都杉並区の永田浩三さん(58)は、
「結論は、最後の最後で踏みとどまったので、一歩前進。
ただ、手続き上の問題ということだけで終ってしまったのが残念だ」と話した。
会議終了後の記者会見でも、質問は、結論の根拠に集中。
「閉架自体については、良い悪いという立場では全くない」
内藤委員長は、あくまで、教育委員に諮ることなく、閉架を要請した手続き上の問題だったと強調した。
「撤回は当然」と受け止めた松江市の女性(43)は、
「子どもが何を読むかを、お上が制限したのはしゃくに障る。
今度もこういうことが起きるかと思うと、すっきりしない」と、語気を強めた。
「早く読めるように」作者中沢さんの妻 安堵
市教委は、閲覧制限の撤回を決めたことを受け、作者中沢啓治さんの妻ミサヨさん(70)は、
「うれしい。早く子どもたちが、読みたいときに読めるようにしてほしい」と、安堵した様子で語った。
「ゲン」について「戦争や原爆の実態を伝え、平和の尊さを知ってほしいという思いで(中沢さんは)描いた」とミサヨさん。
教育関係者に対し、
「その意図をしっかりつかんで、こういうことが繰り返されないようにしてほしい」と訴えた。
現場異論出たのか
教育評論家・尾木直樹さんの話
市教委事務局は、安易に要請したのだろうが、学校側から、「現場ではこう工夫している」などの異論が出なかったとすれば、そのことが問題だ。
感想を語り合うなどすることにより、不安や怖さを共有し合えば、深刻な心の傷を避けることができる。
ただ、手続きに問題があったとする市教委の今回の決定は、政治問題化を避ける意味でも、大人の判断だった。
閲覧制限問題の経過
2012年4~5月
漫画『はだしのゲン』を、学校図書館から撤去するよう、男性が、松江市教育委員会に、計3回要求
8月24日
作品を学校図書館から撤去するよう、同じ男性が、市議会に陳情
10月16日
市教委が、市立小中学校の全校長を対象に、作品の利用状況と感想を求めるアンケートを実施
11月26日
市議会教育民生委員会で、陳情が不採択になる
12月5日
市議会本会議で、陳情が不採択になる
12月17日
市教委事務局が、校長会で、各校に閲覧制限を要請
2013年1月9~10日
「現場で対応が分かれる」と、学校側から指摘があり、市教委事務局が再度、校長会で、閲覧制限を要請
8月16日
問題が表面化
8月19日
市教委が、全校長を対象に、作品の利用状況と対応に関する意見を求めるアンケートを実施
8月22日
教育委員が、定例会議で問題を協議し、結論を持ち越す
8月26日
教育委員が、臨時会議で再協議し、制限要請の撤回を決定
↑以上、書き起こしおわり
わたしらは今、武器こそ持ってはいないけど、戦いの真っただ中にいる。
あちこちで、卑怯な作戦を立ててる輩
このふたつの記事は、最近かなりキナ臭い、民主主義を国家主義に変えてまえと企んでる輩の言動について書かれたものです。
東京にお住まいの目良氏の意見↓とともに、紹介させていただきます。
今朝(8/27)の『東京新聞』11面「記者の眼」欄で、
「国際常識欠いたアソウ発言 ナチス否定こそ民主主義」と題し、三浦耕喜記者がアソウ副総理の「ナチス」発言を鋭く批判しています。
「徹底したナチスとの断絶こそ、国際社会でドイツが信用を得る基盤だ。」
そうです。
アソウはその、「ナチスの手口に学んで改憲を」と発言したのです。
そして、そのナチスと戦前、ムッソリーニ・イタリアをふくめて三国軍事同盟を結んだのが、戦前の皇国・軍国主義日本でした。
アソウ発言の内外の反発の広がりに慌てたアベ政権は、「ナチス政権を肯定的に捉えることは断じてない」との政府答弁を閣議決定しました。
しかし、戦後68年も経ってなお、このような恥ずべき釈明をせざるを得ないのは、
実はこの政権が、安倍首相を先頭に、ナチス政権と軍事同盟を結んだ戦前の皇国・軍国主義日本との「徹底した断絶」どころか、
皇国・軍国主義日本が行った侵略戦争を美化し、大日本帝国憲法体制への郷愁を、思想的にも人脈的にも色濃く持っているからにほかなりません。
はっきりさせましょう。
ドイツが欧米社会で、「信用を得る基盤」が「徹底したナチスとの断絶」だとするならば、
わが日本が、特に近隣アジア社会で「信用を得る基盤」は、ナチスと同盟した戦前の「皇国・軍国主義日本との徹底した断絶」なのです。
戦後日本は、アメリカの反共軍事戦略に組み入れられ、協力する見返りに、「皇国・軍国主義日本との徹底した断絶」を免れ、
社会のあらゆる面で、それとの連続性が保たれてしまいました。
そして、そのもっとも代表的な存在が、自民党という政党なのです。
アベ首相は、その自民党の中でもひときわ、人脈的にも思想的にも、「皇国・軍国主義日本」との連続性の強い存在です。
アソウ「ナチス」発言の根底にあるのは、ナチスと同盟した戦前の、「皇国・軍国主義日本」への郷愁・親近感なのです。
僕たちは今こそ、戦前の「皇国・軍国主義日本」との「徹底した断絶」を求め、内外に宣言し、
それを否定しようとするアベ暴走亡国対外犯罪的政権のたくらみと、たたかうことを決意すべきだと思います。

ナチス否定こそ民主主義
【東京新聞・記者の目】2013年8月27日
国際常識欠いた麻生発言
麻生太郎副総理兼財務相は、首相経験者の中では、英語使いで知られる。
外国要人と会談しても、肩をたたきながら冗談を交わす。
だが、いくら言葉が上手だろうと、座談が面白かろうと、民主主義をめぐる国際社会の常識に欠けては、信用は得られまい。
(三浦 耕喜)
ベルリンのドイツ連邦議会議事堂に、5枚一組の大きな絵がかかっている。
描かれているのは、闇の中に巻き上がる炎。
火の渦から人の背骨が浮かび上がっている。
チェコ生まれの芸術家カタリナ・ジーバーディングが、1992年に制作した『迫害された議員のために』という作品だ。
ナチスは、民主的に選ばれた議員を追放し、殺害し、民主主義を破壊する中で権力を握った。
闇は絶望を表し、炎はナチスの暴力を意味する。
それでも焼かれない背骨は、再生する民主主義の象徴だ。
「ドイツの民主主義は、灰からよみがえった」
議会が付した説明には、こう記されている。
今日の民主主義は、多くの犠牲によって築き上げられてきた。
奪われ、焼かれ、殺され、そのたびに人々は、再生への努力を重ねた。
ゆえに、民主主義を守るには、常に、それを破壊する思想と戦わなければならない。
それが、民主主義を確立した、諸国民の常識だ。
その思いと行動を共にすることが、外交の場で語られる「民主主義の価値観を共有する」ことの重要な要素だ。
ドイツ連邦議会が、ドイツの侵略を受けた国からも作品を求め、議員への戒めとしているのも、
二度とナチスなるものを復活させない決意の表れだ。
市民もナチスを許さない。
ベルリン特派員だった時、ネオナチの集会に対抗する市民が、デモで道をふさぎ、半ば実力で阻止するのを、何度も目にした。
普段は厳しく批判し合う保守系とリベラル系の政治家も、肩を組む。
徹底したナチスとの断絶こそ、国際社会でドイツが信用を得る基盤だ。
だとすれば、麻生氏が、日本の憲法改正をめぐり、
「あの手口を学んだらどうか」と、ナチスを引き合いに出したことは、
「民主主義の価値観を共有する」と宣言する日本の立場に、重大な疑問をもたらす。
ナチスの『闇と炎』は、今も生々しい傷だ。
それを知るなら、ワイマール憲法がナチスによって踏みにじられたことを、「誰も気づかないで変わった」と言えるばずがない。
麻生氏は発言を撤回し、政府は「ナチス政権を肯定的に捉えることは断じてない」との答弁を、閣議決定した。
当たり前のことを、あえて確認せざるを得ないのは、不信感を意識する裏返しだ。
野党に責任を問う力は乏しく、与党側には乗り切った感さえ漂う。
だが、その姿全体もまた、日本は本当に、民主主義のパートナーたり得るのかとの疑問を強めるだろう。
そのような政治を許すことで、傷つくのは日本の国益だ。

「ゲン」制限撤回 手続きのみ問題視
【東京新聞・夕刊】2013年8月27日
知る権利 踏み込まず
松江市教委
漫画『はだしのゲン』をめぐる松江市教委の閲覧制限は、学校への教育行政の指導が、どこまで許されるのかという、重い問題を突き付けた。
学校の自主性を尊重した、要請撤回の判断は妥当だが、なぜ撤回しなければならなかったかについては、議論が尽くされたとは言えない。
市教委が問題視したのは、意思決定のプロセスだった。
法に触れないとはいえ、図書館の運営権を持つ学校に対し、熟慮せず、二度も閲覧制限を要請した市教委事務局の姿勢は、撤回の論拠とはならなかった。
強制力を感じた多くの校長が、要請に従った事実もある。
「過激な描写を踏まえた教育上の配慮」と、制限の理由を説明し続けた市教委。
しかし、ある幹部は、「ここまで大きな問題になるとは……」と漏らした。
全国から批判が相次いだ後、子どもの知る権利と表現の自由を侵す可能性のある閲覧制限の重みに、初めて気付かされたという。
市教委事務局は「重要事項は教育委員に諮る」とする規則があるにもかかわらず、内部協議だけで、閲覧制限を決めていた。
この価値判断の甘さにも問題があった。
戦争体験者が高齢化する今、戦争の記憶をどう継承するのか、というテーマも問い掛ける。
戦争を知らない子どもたちが、多様な図書を読む機会を保障するべきではなかろうか。
作品全体の文脈を軽視し、一シーンの表現を過剰に規制する動きが、学校現場に広がってはならない。
(樋口浩二)
「撤回は当然」「根拠に不満」傍聴の市民ら
「撤回は当然」
「最後で踏みとどまった」
26日開かれた松江市の教育委員会議。
傍聴した市民らは、撤回の結論を評価する一方、手続き上の不備のみを根拠としたことに、不満の声も上がった。
市役所3階の部屋には、会議が始まる1時半前から、市民らが集まり始め、約40人が席を埋めた。
会議を傍聴した、東京都杉並区の永田浩三さん(58)は、
「結論は、最後の最後で踏みとどまったので、一歩前進。
ただ、手続き上の問題ということだけで終ってしまったのが残念だ」と話した。
会議終了後の記者会見でも、質問は、結論の根拠に集中。
「閉架自体については、良い悪いという立場では全くない」
内藤委員長は、あくまで、教育委員に諮ることなく、閉架を要請した手続き上の問題だったと強調した。
「撤回は当然」と受け止めた松江市の女性(43)は、
「子どもが何を読むかを、お上が制限したのはしゃくに障る。
今度もこういうことが起きるかと思うと、すっきりしない」と、語気を強めた。
「早く読めるように」作者中沢さんの妻 安堵
市教委は、閲覧制限の撤回を決めたことを受け、作者中沢啓治さんの妻ミサヨさん(70)は、
「うれしい。早く子どもたちが、読みたいときに読めるようにしてほしい」と、安堵した様子で語った。
「ゲン」について「戦争や原爆の実態を伝え、平和の尊さを知ってほしいという思いで(中沢さんは)描いた」とミサヨさん。
教育関係者に対し、
「その意図をしっかりつかんで、こういうことが繰り返されないようにしてほしい」と訴えた。
現場異論出たのか
教育評論家・尾木直樹さんの話
市教委事務局は、安易に要請したのだろうが、学校側から、「現場ではこう工夫している」などの異論が出なかったとすれば、そのことが問題だ。
感想を語り合うなどすることにより、不安や怖さを共有し合えば、深刻な心の傷を避けることができる。
ただ、手続きに問題があったとする市教委の今回の決定は、政治問題化を避ける意味でも、大人の判断だった。
閲覧制限問題の経過
2012年4~5月
漫画『はだしのゲン』を、学校図書館から撤去するよう、男性が、松江市教育委員会に、計3回要求
8月24日
作品を学校図書館から撤去するよう、同じ男性が、市議会に陳情
10月16日
市教委が、市立小中学校の全校長を対象に、作品の利用状況と感想を求めるアンケートを実施
11月26日
市議会教育民生委員会で、陳情が不採択になる
12月5日
市議会本会議で、陳情が不採択になる
12月17日
市教委事務局が、校長会で、各校に閲覧制限を要請
2013年1月9~10日
「現場で対応が分かれる」と、学校側から指摘があり、市教委事務局が再度、校長会で、閲覧制限を要請
8月16日
問題が表面化
8月19日
市教委が、全校長を対象に、作品の利用状況と対応に関する意見を求めるアンケートを実施
8月22日
教育委員が、定例会議で問題を協議し、結論を持ち越す
8月26日
教育委員が、臨時会議で再協議し、制限要請の撤回を決定
↑以上、書き起こしおわり
わたしらは今、武器こそ持ってはいないけど、戦いの真っただ中にいる。
あちこちで、卑怯な作戦を立ててる輩