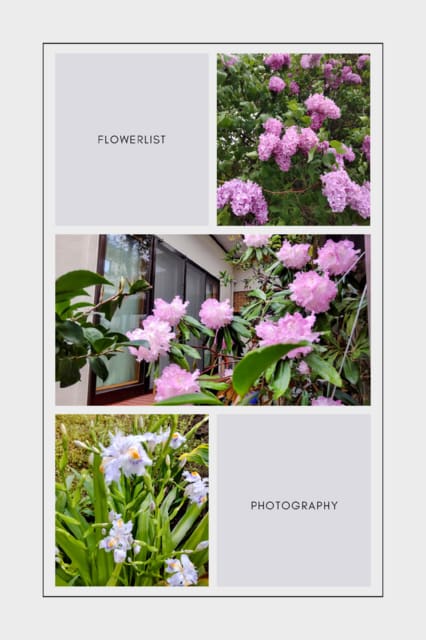この春、令和天皇のひとり娘、愛子内親王が大学を卒業し、日赤に就職された。生まれたときから、テレビの映像で紹介され、その成長の様子が折に触れ見ることができ、大学を卒業するまでになったことは感慨深い。その卒業論文は、「式子内親王とその和歌の研究」であったという。式子内親王(1149~1201)といえば、後白河天皇の第3皇女。天皇家の生まれた同じ皇女として、愛子さまはどのような気持ちで、古の式子内親王の事績に触れられたのであろうか。興味深い。
玉の緒よ絶えなば絶えね
ながらえばしのぶることのよわりもぞする 式子内親王
百人一首にとられた式子の歌である。馬場あき子の歌の意訳を、載せる。
「私の命よ、人思う苦しさに絶えだえの命の糸よ、ふっつりと切れてしまうなら、いっそそれでよい。この激しい思慕に耐えて生きながらえようとは、とても思えないのに、うちあけることはおろか、あの方を思うことさえ、私には許されていないのだから。」
式子は歌の名手といえる。その心中にある懊悩を、こんな詩句に表現することは並みの読み手にできることではない。
馬場あき子によると、式子内親王の歌に深みをもたらすできごとがある。1159年10月、式子は内親王の宣下を受け、齋院に卜定され、以後10年加茂神社に奉仕した。ここでの葵祭は、青春のよき思い出になった。
時鳥そのかみやまの旅枕
ほの語らひし空ぞ忘れぬ 式子内親王
そして1180年、この年5月に母を亡くし、兄以仁王の無残な敗死の事件が起きた。式子にとってこの年の夏は生涯忘れがたいものとなった。1994年には、出家。精神的にも深い不幸のなかにあったと思われる。
嵯峨のお寺に式子の墓がある。塚のうえに小さな五輪の塔のつつましやかな墓だ。その塚を囲む樹々の根方にある古い石仏は、式子の魂をしっかりと守っているように見える。