大きな市の市役所や、大きな警察署の部屋に「記者室」「記者クラブ」と
表札のかかる部屋がある。机が並び、新聞記者やテレビの記者が席にいたりいなかったり。
担当記者が私物化しているので、資料が山積みになっているのがほとんど。
「こんどこういう祭りがあるので取材してほしい」という人が来たり、
来月の市議会の詳細な日程が張ってあったり。
役所の担当職員がひとり、ふたりいたりして、何かを広報してほしいという
団体や市民の対応をしたり記者と話したりしている。これが、地方都市の記者クラブのひとつで、
運用は地域、機関によってだいぶ違うが、まあ大体こんな感じだ。
最近読んでいる本で、記者クラブ制度を否定する論考があり、
「なぜ記者は記者室を使えるのか」と改めて考えてみた。
記者クラブ、という組織があることはそんなに違和感はない。どこでも業界団体はあるし、
自浄作用とかなんとかで、必要だと思う。地方都市の記者クラブは、日本新聞協会の
その都市版みたいなイメージだ。
ただ、公的財産である記者室の使用については、積極的には肯定できないというのが私の考えだ。
反対に消極的肯定というのは、何の仕事でもそうかもしれないが、上司のいる職場以外の方が
仕事がはかどるとか、悲しいほど庶民的なもので、表現の自由とか報道の
自由とか、高尚な理由ではない。実質的に行政側として
必要な機関であり、場所を提供するだけのメリットもあるのは確か。
論考をもとに、少し調べたり考えたりしたことを書き留めておく。
論考は、竹内謙(2005)「ジャーナリストは「養殖場」を飛びだそう」
『ジャーナリズムの条件1』で、副題は問われる記者クラブ制度。
元朝日新聞記者で、鎌倉市長になり、市役所内にあった記者クラブへの提供部屋を
「広報メディアセンター」にして、記者クラブ加盟者以外にも開いた人物だ。
タイトルからして「記者クラブはジャーナリストにとって弊害だ」という主張が
読み取れるが、とりあえず日本新聞協会の主張する記者クラブの意義はこうだ。(HPより)
----------------------
記者クラブの機能・役割は、(1)公的情報の迅速・的確な報道(2)公権力の監視と情報公開の促進(3)誘拐報道協定など人命・人権にかかわる取材・報道上の調整(4)市民からの情報提供の共同の窓口―である。
----------------------
記者室を提供することの解釈は、
----------------------
公的機関にかかわる情報を迅速・的確に報道するためのワーキングルームとして公的機関が記者室を設置することは、行政上の責務であると言えます。常時利用可能な記者室があり公的機関に近接して継続取材ができることは、公権力の行使をチェックし、秘匿された情報を発掘していく上でも、大いに意味のあることです
-----------------------
実質的には、記者クラブの役割(記者クラブに属する記者の役割)として、
記者室がどうしても必要な理由は、(1)公的情報の迅速・的確な報道だけだ。
そして、公的情報の迅速・的確な報道なんて、仕事の優先順位からすればそんなに高くはない。
そこまで迅速じゃなくてもいいはず。市や市議会のホームページに載っていることがほとんどだからだ。
くわえて、竹内氏が書いていた、「日本新聞協会が2002年に示した見解の中で
援用している1958年の旧大蔵省管財局長通達」の内容を知り、がっかりだった。
これは、国が公的財産を記者クラブに渡すことを正当化するものだが、
そこには「国の事務、事業の遂行のため、国が当該施設を提供する」とある。
結局、「公的情報の迅速・的確な報道」は国の事務にあたるのだ。
国の事務を新聞記者がやってると捉えることができてしまう。
客観的に考えて、新聞界の人はこういう「国のお墨付き」を嫌いそうなものだ。
他ならいざしらず、なぜ新聞協会の「見解」で50年も前のなんとか局長の文章を出すのか。
おそらく、多くの新聞社、地域で記者室の使用を続けたいからだろう。
今更、警視庁や財務省に始まり、全国津々浦々の県や市町にある記者室がなくなったら、
そこにいた記者たちを置く場所はない。
それならやはり、「見解」が言及するように使用料有りの、
賃貸スペースにするべきだし、そんなに支障はないと思う。
表札のかかる部屋がある。机が並び、新聞記者やテレビの記者が席にいたりいなかったり。
担当記者が私物化しているので、資料が山積みになっているのがほとんど。
「こんどこういう祭りがあるので取材してほしい」という人が来たり、
来月の市議会の詳細な日程が張ってあったり。
役所の担当職員がひとり、ふたりいたりして、何かを広報してほしいという
団体や市民の対応をしたり記者と話したりしている。これが、地方都市の記者クラブのひとつで、
運用は地域、機関によってだいぶ違うが、まあ大体こんな感じだ。
最近読んでいる本で、記者クラブ制度を否定する論考があり、
「なぜ記者は記者室を使えるのか」と改めて考えてみた。
記者クラブ、という組織があることはそんなに違和感はない。どこでも業界団体はあるし、
自浄作用とかなんとかで、必要だと思う。地方都市の記者クラブは、日本新聞協会の
その都市版みたいなイメージだ。
ただ、公的財産である記者室の使用については、積極的には肯定できないというのが私の考えだ。
反対に消極的肯定というのは、何の仕事でもそうかもしれないが、上司のいる職場以外の方が
仕事がはかどるとか、悲しいほど庶民的なもので、表現の自由とか報道の
自由とか、高尚な理由ではない。実質的に行政側として
必要な機関であり、場所を提供するだけのメリットもあるのは確か。
論考をもとに、少し調べたり考えたりしたことを書き留めておく。
論考は、竹内謙(2005)「ジャーナリストは「養殖場」を飛びだそう」
『ジャーナリズムの条件1』で、副題は問われる記者クラブ制度。
元朝日新聞記者で、鎌倉市長になり、市役所内にあった記者クラブへの提供部屋を
「広報メディアセンター」にして、記者クラブ加盟者以外にも開いた人物だ。
タイトルからして「記者クラブはジャーナリストにとって弊害だ」という主張が
読み取れるが、とりあえず日本新聞協会の主張する記者クラブの意義はこうだ。(HPより)
----------------------
記者クラブの機能・役割は、(1)公的情報の迅速・的確な報道(2)公権力の監視と情報公開の促進(3)誘拐報道協定など人命・人権にかかわる取材・報道上の調整(4)市民からの情報提供の共同の窓口―である。
----------------------
記者室を提供することの解釈は、
----------------------
公的機関にかかわる情報を迅速・的確に報道するためのワーキングルームとして公的機関が記者室を設置することは、行政上の責務であると言えます。常時利用可能な記者室があり公的機関に近接して継続取材ができることは、公権力の行使をチェックし、秘匿された情報を発掘していく上でも、大いに意味のあることです
-----------------------
実質的には、記者クラブの役割(記者クラブに属する記者の役割)として、
記者室がどうしても必要な理由は、(1)公的情報の迅速・的確な報道だけだ。
そして、公的情報の迅速・的確な報道なんて、仕事の優先順位からすればそんなに高くはない。
そこまで迅速じゃなくてもいいはず。市や市議会のホームページに載っていることがほとんどだからだ。
くわえて、竹内氏が書いていた、「日本新聞協会が2002年に示した見解の中で
援用している1958年の旧大蔵省管財局長通達」の内容を知り、がっかりだった。
これは、国が公的財産を記者クラブに渡すことを正当化するものだが、
そこには「国の事務、事業の遂行のため、国が当該施設を提供する」とある。
結局、「公的情報の迅速・的確な報道」は国の事務にあたるのだ。
国の事務を新聞記者がやってると捉えることができてしまう。
客観的に考えて、新聞界の人はこういう「国のお墨付き」を嫌いそうなものだ。
他ならいざしらず、なぜ新聞協会の「見解」で50年も前のなんとか局長の文章を出すのか。
おそらく、多くの新聞社、地域で記者室の使用を続けたいからだろう。
今更、警視庁や財務省に始まり、全国津々浦々の県や市町にある記者室がなくなったら、
そこにいた記者たちを置く場所はない。
それならやはり、「見解」が言及するように使用料有りの、
賃貸スペースにするべきだし、そんなに支障はないと思う。
















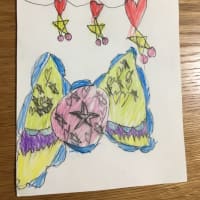


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます