反捕鯨の映画「THE COVE」を見たことや、舞台の和歌山県太地町に行ったことから、
あまり考えたことの無かった捕鯨問題を少し考えてみた。
情報を集めただけで、結論には至っていないが。
映画については、興味のきっかけにはなったし、表現の自由という点で
上映阻止はおかしいと思う。ただ、これがアカデミー賞ドキュメンタリー部門で
受賞したのには、この映画を「優れたドキュメンタリー」とすることに強い違和感がある。
変だ。下に書くように、アメリカは国として捕鯨に反対しているから、
そこらへんも影響したのだろうか、と疑りたくもなる。
以下、つれづれに。
・映画「THE COVE」について
世界でも最大規模の「イルカ追い込み漁」をしている和歌山県太地(たいじ)町を
舞台に、いるか追い込み漁を批判する映画だ。太地は人口は3200人ほどの町。
「cove」というのは「入り江」という意味。何層もの船がカンカン音を鳴らし、
音に敏感なイルカたちは逃げるように入り江に入り込む。数十頭(たぶん)の
群れのイルカを網などで入り江から出ないようにし、銛で数回ずつ刺して
放置、血を流しながらイルカが息絶えるのを待つ。入り江はイルカの血で染まる。
ユーチューブでも英語版が見られる。
・太地町のいるか漁の規模
毎年「2万3000頭」のイルカが太地で捕獲されるというのは映画の数字。
その数字が誇張だ、という話は耳にしないので、そうなんだろう。
公式の数字はちょっと見あたらなかった。
(いるか(小型鯨)の許可頭数を各都道府県に
割り振っている水産総合研究センターのHPを見て、表の数字を足し合わせたら
全道県=北海道、宮城、千葉、静岡、和歌山、沖縄=9225頭だった(2008年))
・いるか追い込み漁
国内では、太地と、静岡県の伊東で許可されているらしい。
世界では、南米、アルゼンチンのフォークランド諸島とか、オーストラリアのソロモン諸島
とかでやられているようだが、太地の規模が一番大きい(Wikipediaだけど)。
・シー・シェパードの主張と、日本の水産庁の主張、アメリカの反捕鯨の背景(?)
なぜ、反捕鯨団体のシー・シェパードは、なぜいるか漁を批判するのか。
映画の中では、隊長らしき人物はいるかの調教師の草分け的存在で、
いるかを愛し、水族館などでショーをさせるために利用する流れを作ってしまったことを後悔、
それを是正しようと努めている感じ。
その経験が理由のような気がするが、基本的には
いるかの知能の高さ、そして追い込み漁の残酷さを批難している(と思われる)。
(捕るなと言っているのか、残酷なやりかたを改めろと言っているのか、
英語だったしよくわからなかった)
それをアメリカが支えていそう、という疑いは、アメリカにとっての利害関係にある。
1800年代ごろは大捕鯨国だったアメリカが、反捕鯨なのは、
昔から「鯨油」目的の捕鯨で、それが石油に代替された今は捕る必要がないこと、
鯨の肉が、アメリカの輸出産品である牛肉の代替物であり、牛肉マーケットと競合すること、
がある(と思われる、とどこかにあった)。
なるほど、その可能性は否定できない。
日本側の(捕鯨に関する)主張は、水産庁のHPには
----------------------
我が国は、以下の基本認識の下、商業捕鯨の再開を目指しています。
( 1 )鯨類資源は重要な食料資源であり、他の生物資源と同様、
最良の科学事実に基づいて、持続的に利用されるべきである。
( 2 )食習慣・食文化はそれぞれの地域におかれた環境により歴史的に
形成されてきたものであり、相互の理解精神が必要である。
-----------------------
とあります。霞ヶ関文学。
日本がなぜ、強固に捕鯨推進で主張するのか、と考えてみよう。
なぜなら、そっちの方がちょっと不自然に思えたから。
直接捕鯨に関わる従事者は相当少なそうだし、大体くじらを食べることはあまりない。
なくても、たぶん私は気づかない。
鯨マーケットに関する人たち、というだけでは政治力も強くはなさそう。
これに対する仮説は、鯨の購入先、アイスランドなどとの外交関係をまもるため、
右翼団体の文化を守れという主張、アメリカなどの理不尽な反捕鯨圧力に屈するものかという意地、
ここで負けたらクロマグロなどの回遊魚の捕獲量規制にも悪影響、
などが思いついた。
以上をふまえて、私の今の捕鯨問題への印象を書くと、
自分で書いてきてなんだが、日本の捕鯨問題≒世界的な生態系の保全と、
太地町のいるか追い込み漁の問題がごっちゃになっている。
それが、シー・シェパードの戦略のような気もする。
いるか追い込み漁の残虐さを見せつけ、「やっぱり捕鯨はだめでしょうあなた」と同意を求める。
日本の捕鯨問題については、鯨の生態数が減っていないというデータが正しいとすれば、
捕鯨自体は問題ないし、食文化として残したいという主張は他国に認められるべきだ。
「知能レベルが高い」ということを、食用には出来ないという線引きにするのは難しい。
強制的にやめる理由にはならない。
追い込み漁については、確かに荒っぽい、残酷な行為という印象。
海は誰もが共有できる自然だし、それを血で染めることには配慮すべきだ。
牛やブタの血抜き、をした後の血がどう処理されているのか知らないが、
何かしらの方法があるはず。そういう流通コストは払うべきだ。
そして、「文化」と言うなら、映画にあるような、すべてを隠すようなやり方はいけない。
漁の実行に支障がある場合は仕方ないが。
堂々と見せて、日本国民にも非難される場合には、やはり加工や流通の方法の再考が必要だろう。
IWCは、おそらく生態系への影響だけが論点だと思う。
それならデータさえあればそんなに難しい話ではないのに、政治的に利用されている印象。
これからもうちょっと注意深く見ていきたいと思います。
参考:水産総合研究センター http://kokushi.job.affrc.go.jp/H21/H21_45.html
水産庁 http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_thinking/index.html
あまり考えたことの無かった捕鯨問題を少し考えてみた。
情報を集めただけで、結論には至っていないが。
映画については、興味のきっかけにはなったし、表現の自由という点で
上映阻止はおかしいと思う。ただ、これがアカデミー賞ドキュメンタリー部門で
受賞したのには、この映画を「優れたドキュメンタリー」とすることに強い違和感がある。
変だ。下に書くように、アメリカは国として捕鯨に反対しているから、
そこらへんも影響したのだろうか、と疑りたくもなる。
以下、つれづれに。
・映画「THE COVE」について
世界でも最大規模の「イルカ追い込み漁」をしている和歌山県太地(たいじ)町を
舞台に、いるか追い込み漁を批判する映画だ。太地は人口は3200人ほどの町。
「cove」というのは「入り江」という意味。何層もの船がカンカン音を鳴らし、
音に敏感なイルカたちは逃げるように入り江に入り込む。数十頭(たぶん)の
群れのイルカを網などで入り江から出ないようにし、銛で数回ずつ刺して
放置、血を流しながらイルカが息絶えるのを待つ。入り江はイルカの血で染まる。
ユーチューブでも英語版が見られる。
・太地町のいるか漁の規模
毎年「2万3000頭」のイルカが太地で捕獲されるというのは映画の数字。
その数字が誇張だ、という話は耳にしないので、そうなんだろう。
公式の数字はちょっと見あたらなかった。
(いるか(小型鯨)の許可頭数を各都道府県に
割り振っている水産総合研究センターのHPを見て、表の数字を足し合わせたら
全道県=北海道、宮城、千葉、静岡、和歌山、沖縄=9225頭だった(2008年))
・いるか追い込み漁
国内では、太地と、静岡県の伊東で許可されているらしい。
世界では、南米、アルゼンチンのフォークランド諸島とか、オーストラリアのソロモン諸島
とかでやられているようだが、太地の規模が一番大きい(Wikipediaだけど)。
・シー・シェパードの主張と、日本の水産庁の主張、アメリカの反捕鯨の背景(?)
なぜ、反捕鯨団体のシー・シェパードは、なぜいるか漁を批判するのか。
映画の中では、隊長らしき人物はいるかの調教師の草分け的存在で、
いるかを愛し、水族館などでショーをさせるために利用する流れを作ってしまったことを後悔、
それを是正しようと努めている感じ。
その経験が理由のような気がするが、基本的には
いるかの知能の高さ、そして追い込み漁の残酷さを批難している(と思われる)。
(捕るなと言っているのか、残酷なやりかたを改めろと言っているのか、
英語だったしよくわからなかった)
それをアメリカが支えていそう、という疑いは、アメリカにとっての利害関係にある。
1800年代ごろは大捕鯨国だったアメリカが、反捕鯨なのは、
昔から「鯨油」目的の捕鯨で、それが石油に代替された今は捕る必要がないこと、
鯨の肉が、アメリカの輸出産品である牛肉の代替物であり、牛肉マーケットと競合すること、
がある(と思われる、とどこかにあった)。
なるほど、その可能性は否定できない。
日本側の(捕鯨に関する)主張は、水産庁のHPには
----------------------
我が国は、以下の基本認識の下、商業捕鯨の再開を目指しています。
( 1 )鯨類資源は重要な食料資源であり、他の生物資源と同様、
最良の科学事実に基づいて、持続的に利用されるべきである。
( 2 )食習慣・食文化はそれぞれの地域におかれた環境により歴史的に
形成されてきたものであり、相互の理解精神が必要である。
-----------------------
とあります。霞ヶ関文学。
日本がなぜ、強固に捕鯨推進で主張するのか、と考えてみよう。
なぜなら、そっちの方がちょっと不自然に思えたから。
直接捕鯨に関わる従事者は相当少なそうだし、大体くじらを食べることはあまりない。
なくても、たぶん私は気づかない。
鯨マーケットに関する人たち、というだけでは政治力も強くはなさそう。
これに対する仮説は、鯨の購入先、アイスランドなどとの外交関係をまもるため、
右翼団体の文化を守れという主張、アメリカなどの理不尽な反捕鯨圧力に屈するものかという意地、
ここで負けたらクロマグロなどの回遊魚の捕獲量規制にも悪影響、
などが思いついた。
以上をふまえて、私の今の捕鯨問題への印象を書くと、
自分で書いてきてなんだが、日本の捕鯨問題≒世界的な生態系の保全と、
太地町のいるか追い込み漁の問題がごっちゃになっている。
それが、シー・シェパードの戦略のような気もする。
いるか追い込み漁の残虐さを見せつけ、「やっぱり捕鯨はだめでしょうあなた」と同意を求める。
日本の捕鯨問題については、鯨の生態数が減っていないというデータが正しいとすれば、
捕鯨自体は問題ないし、食文化として残したいという主張は他国に認められるべきだ。
「知能レベルが高い」ということを、食用には出来ないという線引きにするのは難しい。
強制的にやめる理由にはならない。
追い込み漁については、確かに荒っぽい、残酷な行為という印象。
海は誰もが共有できる自然だし、それを血で染めることには配慮すべきだ。
牛やブタの血抜き、をした後の血がどう処理されているのか知らないが、
何かしらの方法があるはず。そういう流通コストは払うべきだ。
そして、「文化」と言うなら、映画にあるような、すべてを隠すようなやり方はいけない。
漁の実行に支障がある場合は仕方ないが。
堂々と見せて、日本国民にも非難される場合には、やはり加工や流通の方法の再考が必要だろう。
IWCは、おそらく生態系への影響だけが論点だと思う。
それならデータさえあればそんなに難しい話ではないのに、政治的に利用されている印象。
これからもうちょっと注意深く見ていきたいと思います。
参考:水産総合研究センター http://kokushi.job.affrc.go.jp/H21/H21_45.html
水産庁 http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/w_thinking/index.html
















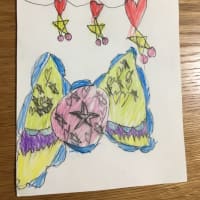


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます