「イリアス」という舞台を観た。
イリアスとは、トロイアの詩、という意味だそうだ。
内容は、3000年ほど前、エーゲ海を挟んでトロイア(今のトルコの一部)と
ギリシャとが戦ったトロイア戦争のその後を描いたもの。
ギリシャ神話の延長のような位置づけなのかは知らないが、
ギリシャの神々がトロイアに味方したり、ギリシャに味方したり、
神と人間の子が英雄として出てきたりする。
世界最古の物語と言われ、平家物語のように、文字が出来る前から口で伝承されてきたという。
主演は内野聖陽(まさあき)=アキレウス。
休憩20分を挟んで3時間半ほどもある作品だ。
感想はいろいろあるが、ポジティブな面で言えば、
「人間はいつか死ぬ」という事実が、人間の行動原理をけっこう左右してるのでは、
という仮説めいたことを考えたこと。
なぜかといえば、「神」という永遠の命を持つ存在が、人間のそばに出てきて、
ストーリーをなしていて、そういえば初めて対比してみたから。
物語の中でも、「永遠の命を持つ神々にもてあそばれ、10年も戦争をしてしまった」
といった台詞があった気がした。
「人はいつか死ぬのだから」が、「どのように死ぬかが大事。どうせなら華々しく死んで、
英雄になりたい」といった動機につながることはありうる。
実際、特攻隊に参加した人に話を聴いたことがあるが、
「死ぬのは、自分の順番が来るのは全然怖くなかった。『靖国神社で会おう』と言って」
と、死ぬ意味が、死ぬという事実を上回っていたというか、
似たような感想を持った。
「神にとっては人間の命など些細なこと」
といったような台詞もあって、神が身近に存在し、助けたり助けなかったりと
運命をもてあそばせる設定では、神は敬うだけのものではないのだなと
新鮮にも思った。
神が登場する物語なんて仰々しいというか、現実離れしすぎでしょうと興味を持ったことが
なかったが、人間との対比は面白そうだと思った。
・・・だから、そういう人間と神との行動原理の違いみたいな所に焦点があれば、
面白かったのだと思う。結果としては、ボリュームのわりに響くモノは少なく、
言ってみれば「舞台化してみました」という自己満足のような感じがした。
やはり、「これを伝えたい」というのがないとだめですね。
それは何でも同じ。何を伝えたいのか。それを自己認識してないと伝わりません。
今回は舞台のための筋書きではなく、筋書きありきの舞台だったので、
「舞台」というツールを最大限生かそうとした作品を次回は探してみたいと思います。
イリアスとは、トロイアの詩、という意味だそうだ。
内容は、3000年ほど前、エーゲ海を挟んでトロイア(今のトルコの一部)と
ギリシャとが戦ったトロイア戦争のその後を描いたもの。
ギリシャ神話の延長のような位置づけなのかは知らないが、
ギリシャの神々がトロイアに味方したり、ギリシャに味方したり、
神と人間の子が英雄として出てきたりする。
世界最古の物語と言われ、平家物語のように、文字が出来る前から口で伝承されてきたという。
主演は内野聖陽(まさあき)=アキレウス。
休憩20分を挟んで3時間半ほどもある作品だ。
感想はいろいろあるが、ポジティブな面で言えば、
「人間はいつか死ぬ」という事実が、人間の行動原理をけっこう左右してるのでは、
という仮説めいたことを考えたこと。
なぜかといえば、「神」という永遠の命を持つ存在が、人間のそばに出てきて、
ストーリーをなしていて、そういえば初めて対比してみたから。
物語の中でも、「永遠の命を持つ神々にもてあそばれ、10年も戦争をしてしまった」
といった台詞があった気がした。
「人はいつか死ぬのだから」が、「どのように死ぬかが大事。どうせなら華々しく死んで、
英雄になりたい」といった動機につながることはありうる。
実際、特攻隊に参加した人に話を聴いたことがあるが、
「死ぬのは、自分の順番が来るのは全然怖くなかった。『靖国神社で会おう』と言って」
と、死ぬ意味が、死ぬという事実を上回っていたというか、
似たような感想を持った。
「神にとっては人間の命など些細なこと」
といったような台詞もあって、神が身近に存在し、助けたり助けなかったりと
運命をもてあそばせる設定では、神は敬うだけのものではないのだなと
新鮮にも思った。
神が登場する物語なんて仰々しいというか、現実離れしすぎでしょうと興味を持ったことが
なかったが、人間との対比は面白そうだと思った。
・・・だから、そういう人間と神との行動原理の違いみたいな所に焦点があれば、
面白かったのだと思う。結果としては、ボリュームのわりに響くモノは少なく、
言ってみれば「舞台化してみました」という自己満足のような感じがした。
やはり、「これを伝えたい」というのがないとだめですね。
それは何でも同じ。何を伝えたいのか。それを自己認識してないと伝わりません。
今回は舞台のための筋書きではなく、筋書きありきの舞台だったので、
「舞台」というツールを最大限生かそうとした作品を次回は探してみたいと思います。
















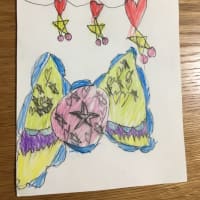


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます