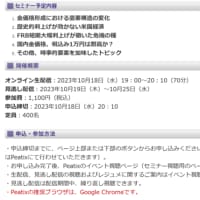3月最初の取引となった1日のNY金は3営業日続伸となった。8.70ドル高の1845.40ドルで終了。この日発表されたISM製造業景況指数にてインフレが高止まりする可能性が示唆されたことに加え、FRB高官によるタカ派的発言も伝わり、米国債利回りが上昇。金の売りが意識されたものの、一方でドルが幅広い通貨に対して下落した上に、1日に発表された中国の堅調な製造業関連指標が金市場ではサポート要因として意識されたとみられた。
注目の2月のISM(米供給管理協会)製造業景況指数は47.7と、1月の47.4からやや上向いたものの予想(48.0)は下回った。拡大と縮小の分岐点となる50を下回るのは4カ月連続となる。新規受注指数が47.0と、2020年5月以来の低水準だった前月の42.5から回復した。50を下回っているものの、安定化に向かい始めた兆候と受け止められた。
こうした指標は方向、傾向を重視する。
注目されたのは、仕入れ価格指数が51.3と、2カ月連続で上昇し昨年9月以降初めて50を上回ったこと。コスト上昇からインフレが当面は高止まりする可能性があるとの受け止め方が広がった。
そしてこれが債券市場ではFRBの利上げ継続を連想させ売りを促した。
10年債利回りは一時4.011%と昨年11月10日以来となる4%台を付け、3.994%で終了。4%台に乗せる水準まで価格が下がると、利回り確保の買いが見られるようで、持続的に4%を超えるのか注目される。 一方、金融政策の方向性を敏感に映すことで知られる2年債利回りも上昇。一時4.904%と2007年7月以来約16年ぶりの高水準を付け、そのまま水準を維持し4.895%で終了した。金利が予想よりも長く上昇し続けるとの見方を映している。
4%近くまで米長期金利(利回り)が上昇すると、金市場では売りが優勢になるが、この日はドル指数(DXY)の下落が買い要因として上回った。
相場力学と表現できるが、売り要因と買い要因という反対方向のベクトルが存在しているのが、ゴールドに限らずどの相場も同じ。要因が勝る方向に相場は動く。
この日ドル指数(DXY)を押し下げたのはユーロ高で、ドイツの2月の消費者物価指数(CPI)速報値が前年比9.3%上昇と1月の9.2%上昇から加速し、市場予想(9.0%上昇)を上回ったことがある。欧州中銀(ECB)がタカ派姿勢を強めるとの観測がユーロ買いにつながった。
なお1日の金市場で欧米のアナリストが中国の指標を話題に上げていたのだが、それが昨日アジア時間に伝えられた中国の2月の製造業購買担当者景気指数(PMI)が52.6と1月の50.1から予想以上に上昇したというものだった。足元の金市場での中国の動向を意識しているのがわかる。
FRB高官のタカ派発言としては、アトランタ連銀のボスティック総裁の発言が目に留まった。政策金利を5%以上に引き上げていく必要があるとの見方は以前からのものだが、「2024年もしばらくその水準で維持する必要がある」という部分が以前にはなかった。「1970年代のようなパターンで再加速するのを防ぐため」としている。 本日はウォラーFRB理事の講演が予定されており要注目だが、日本時間の明朝4時の予定。
こう書いてきて現在の米10年債利回りをチェックしたら、4.046%と節目を上抜いている。こうなるとNY金は上値を抑えられるが、ドル円は円安方向に動くのでJPX金には相殺あるいは押し上げの可能性もありそうだ。