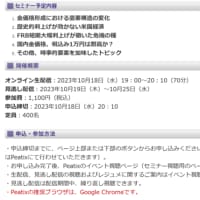先週末、ある経済誌の記者氏との話だが、ここにきてマネー誌、経済誌の売れ行きが回復を見せているとのこと。やはり株高の効果は大きい。持続的な株価上昇の効果は、それらを取り上げるメディアをも一息つかせているという状況。もちろん、これは以前からある傾向であって、もの珍しさはないが、ほんの1ヵ月半ほど前まで(今でも?)書店には「恐慌」の見出しをもつ書籍が、数多く並んでいたので、その変化の度合いが興味深い。日米がほぼ同じタイミングで特定のインフレ率を掲げ、一定の政策目標にしつつ緩和策を継続し、ECBは独自路線で集中的にマネーの大規模供給を実施、気が付けばブラジルだインドだ、そして中国だと緩和策の大合唱になってきた。多くの国が、外からの影響を心配しているのも共通している。
しかし、カネは余っているが、金市場を含めどの市場もここから更に上昇となると、いよいよ地に足が着いた材料が必要になってくる。季節性としては、とりわけ米国の場合、このところ年始からの4、5月に掛けての好調さが夏に向け失速するパターンを繰り返しているだけに、これからが正念場ということになる。金が上がりやすいのは、そうしたパターンなんだが、さてどうなるか。不胎化量的緩和などという新手の技に走ろうとするような報道も先週あったが、さて13日のFOMCでは、そうした具体的なものはないだろう。
それにしてもQEⅢというのは、以前から別にFRBがコミッ(約束)トしているわけではなく、状況によってはそこまで可能性はあるという類のものなので、各種数値の改善が見られている中での29日の下院金融サービス委員会でのバーナンキ証言にQEⅢへの言及がなくとも当然ということ。それを急落で反応するというのも疑問だった。そんなに市場参加者が単細胞でもあるまいに。それを口実にしたファンドの攪乱作戦ということか。