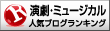道頓は物事の緩急を心得た男で、けして急いだ工事はやらせなかった。
この天正十二年(1584年)という年は、九州や四国、関東以北が、まだ秀吉になびいておらず、徳川家康も臣従していない、小牧長久手の戦いが引きわけに終わる年である。
秀吉は、まだ天下の半分ほどしか手にしていないわけで、そのためにも秀吉の威を示す大坂城の普請は急がれた。普請場は大名や近在の大商人たちに請け負わされたが、事情を承知していたので、どの作事場も灰神楽が立つような賑わいと急ぎようであった。
そんな中で、道頓の持ち場だけは、朝五つから宵五つまでの作業と時間を限っていた。また十日に一度は有給の休みを取らせ、けして無理はさせなかった。それでも、道頓の作事場は、他に比べて進捗が早く、文句を言う作事方の役人もいなかった。
そのくせ道頓自身は明け六つには作事場に来ている。
特に、監督するという風ではなく、親方衆や人足たちと、談笑しながら朝飯を食っている。
――なるほど、こうやって働く者の様子を見ながら、作業の段取りを決めて、作事場の空気を読んでいるんだ――
美奈は感心した。相談されれば親方衆も発言し、相談の上決まったことなら、やる気も出る。
そのくせ内心ではせいている。
けして言動に出るようなことはなかったが、半月も付き合っていれば分かるようになった。「自分なら、こうやる」という観念が強いし、また洞察力もあるのだが、けして表には出さない。ただ、作業の安全ともめ事には気を配りすぎるほど配っていた。先月櫓から落ちたのも、そういう気配りの最中のことであった。
「早う羽柴様に天下を平らげていただかんとなあ……わしらの商いは天下が収まらんと進まんでのう」
昼餉の休みに、道頓は親方たちと握り飯に焼き味噌を塗ったものを頬張りながら世間話をしていた。
「徳川さまさえ、なんとかお味方になれば、あとは早いやろになあ」
「まあ、羽柴さまにもお考えがあってのことやろ、せいだい気長に明るう待ってるこっちゃろなあ」
「道頓さん、さっきの気ぜわしさと反対じゃの」
「アハハ、儂も人の子や、悟ったことを言いながら、気持ちはせきますわ。なんや若いころ女子のケツ追い掛け回してた時のようや」
「したり、したり、その若い女医師殿は、医学の腕だけではおまへんやろ」
「いやいや、わしが手ぇ出したら一服盛ってええいうことになってますのじゃ」
これには美奈も笑った。
道頓には、久宝寺と高安に女が二人いることを美奈も知っていた。親方衆も薄々知っているようで、一座はどっと沸いた。
「しかし、羽柴さまがお留守なことを知ってか、京や大坂では、五右衛門とかいう盗賊が出始めとるようでんな」
「え、それは初耳、どないな盗賊だんねん?」
道頓は知っていながら、子供のように質問する。聞いた方が人の評判や受け止め方が良く分かるからである。
五右衛門は、正しくは石川五右衛門といい、伊勢長嶋の一揆の生き残りという噂であるが、定かではない。
ただ襲われる商人たちが信長の時代に、その政権に食い込み身代を大きくした者ばかりだというから根のない話ではないであろう。
その年の四月、秀次が二万の軍勢を迂回させ、家康の本拠地三河を叩こうとして、逆に待ち伏せをくらい大敗を喫するということがおこった。世に言う小牧長久手の戦いである。一説に、その秀次中入(なかいり)の報を家康にもたらしたのは五右衛門という説もあった。
五右衛門とは、近々出会いそうな予感がした美奈である……。