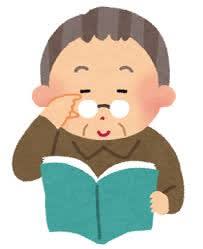当地、今日の天気予報は、「雨のち晴」だったが、
午後になっても青空が広がることなく曇天、
寒さ厳しい1日だった。
今日は、「二十四節気」のひとつ「冬至」。北半球では、1年で最も日長時間が短い日だ。「二十四節気」とは何?も分からなかった子供の頃に教えられ、「夏至」と共にしっかり覚えた日でもある。「二十四節気」とは、節分を基準に1年を24等分して約15日毎に分けた季節のこと。例えば「冬至」も、最初の1日、12月22日だけを指す場合と、その日から約15日間を指す場合が有る。今回の場合、12月22日~1月4日までが、「冬至」ということになる。あまり馴染みのないように見えるが 現在でも 季節季節の変わり目の挨拶等に、無意識に使っていることが多い気がする。
「冬至冬中冬始め(とうじふゆなかふゆはじめ」
という、冬至の頃からが、本格的な冬の厳しい寒さになるという意味合いの諺が有るが、今年はすでに、北日本、北陸地方等では、大雪となっており、真冬の様相。
例年より厳しい冬になるのかも知れない。
「冬至」の日には、地方によっては、小豆粥やかぼちゃを食べたり、冷酒を飲み、柚子湯に入り 身体を温める風習があるという。
(ネットから拝借)

寒さは、これからますます厳しくなっていくが、今日を境に、日長時間は、次第に長くなっていく。
冬来たりなば 春遠からじ
今度は、春を待ち侘びる心情が、強くなってくる。