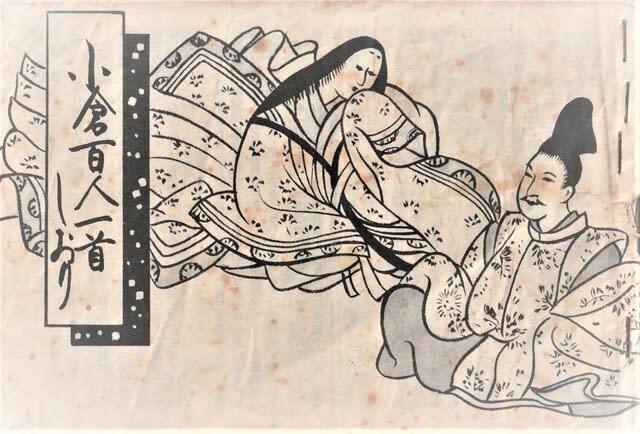相互フォロワー登録しているある方のブログを拝見していて、これまですっかり脳裏から喪失していた童謡、「冬の夜」を思い出した。子供の頃、「音楽」で習ったのかどうかは分からないが、メロディー、歌詞共、なんとなく覚えているから不思議なことだと思う。
せっかく思い出しても、そのそばから、何を思い出したかも思い出せなくなる老脳、忘れない内に、ブログ・カテゴリー「懐かしいあの曲」に、書き留め置くことにする。
今更になってネットで調べてみると
「冬の夜」は、1912年(明治45年)の尋常小学校第三学年用に掲載された「尋常小学唱歌」だった。作詞者、作曲者は不明なのだそうだ。
明治時代後期の雪国、外は一面雪に覆われ、吹雪が吹き荒れる厳しい冬、暖房もラジオも無い時代、家族が、「囲炉裏」の周りに身を寄せ合って、夜の団欒の時を過ごしている情景を表現した歌である。
戦後、昭和30年代頃からは、日本の住宅環境は急速に変わり、「囲炉裏」の有る家等ほとんど無くなってしまっており、多分、「囲炉裏(いろり)って、何?」という世代が大多数になっていると思われるが、昭和20年代~30年代、北陸の山村で幼少期を過ごした爺さんには、かすかに「囲炉裏」の有る暮らしの記憶が有り、童謡「冬の夜」には、じーんとするものがある。
現代では、雪深い地方でも、冬中、雪に閉じ込めらる暮らしは無いが、昭和20年代、30年代頃の北陸の山村ではまだ、それに近い暮らしが有ったのだった。
12年前、2010年に、岐阜県の白川郷を訪れた時、撮っていた「囲炉裏」

「冬の夜」
作詞者・作曲者 不明、
燈火(ともしび)ちかく
衣縫ふ(きぬぬう)母は
春の遊びの 楽しさ語る
居並ぶ子どもは 指を折りつつ
日数(ひかず)かぞへて 喜び勇む
囲炉裏火(いろりび)は とろとろ
外は 吹雪
囲炉裏の端に 繩なふ父は
過ぎしいくさの 手柄を語る
(過ぎし昔の 思い出語る)
居並ぶ子供は ねむさを忘れて
耳を傾け こぶしを握る
囲炉裏火は とろとろ
外は 吹雪
「冬の夜」 ダーク・ダックス (YouTubeから共有)