NHK大河ドラマ「江」も終わりに近づきました。最初の頃は3人姉妹のホームドラマ的な進め方や秀吉の大仰な言動などが漫画チックであり、歴史の芯の部分の手ごたえみたいなものが感じられなくて、時代背景を探るために戦国に関する本を探しました。
 お市の方の悲劇的生涯を中心に描いた谷崎潤一郎『盲目物語』。秀吉と利休の宿命的な闘争を描いた井上靖・短編「利休の死」。そして関ヶ原以前から持ち続けていた天下取りの野望を実現させていく家康の戦略と策略と心理を描いたのがこの『城塞』です。
お市の方の悲劇的生涯を中心に描いた谷崎潤一郎『盲目物語』。秀吉と利休の宿命的な闘争を描いた井上靖・短編「利休の死」。そして関ヶ原以前から持ち続けていた天下取りの野望を実現させていく家康の戦略と策略と心理を描いたのがこの『城塞』です。
大河ドラマの原作・脚本の田淵久美子氏は、お市と3姉妹の戦国の女性の喜び悲しみを中心に、会話も現代口語でわかり易くストーリーを進めていきます。
ドラマでは利休の死は大徳寺山門事件の目に見える部分だけが目立ちますが、井上靖の利休の死の解釈にはとても感銘を受けました。秀吉との最初の出会い以来、利休は漠然といつか死ぬことを予感します。茶室での会話の奥に秘められた相手を受け入れない心理を感じとり、お互いに不寛容になってしまう・・・。そこに利休は自分の死の必然を見て、死に直面しても精神の充実を感じるという文学的なストーリーです。こういう場面はとてもドラマでは表現できなくて、やっぱり本に頼るしかありません。
『城塞』は間諜・小幡勘兵衛が大阪方にも徳川方にも身を置く役割として登場し、冬の陣・夏の陣のストーリーをつないでいきます。
『豊臣を滅ぼすために家康がひねり出した悪知恵というのは、古今に類がない。・・・・坊主あたまの悪謀家が家康のそばにいたことが、家康の対豊臣家の陰謀をたやすくはこばせた』。坊主頭の崇伝ばかりでなく、体のどこを押しても悪知恵が出てくるとささやかれた本田正信と、子の正純を使って悪謀を「大量」に作り出して豊臣家をつぶしていった・・・というのが司馬氏の家康観です。
これだけ役者をそろえて次々と打ち出していった家康の策に、大阪方は挑発に乗らざるを得ません。夏の陣ほど東西決戦の激しかった戦いはないといわれています。
淀と秀頼の自刃は、燃え盛る炎の中で強い意志のまま哀しいまでに華麗に描かれるのをよく目にします。しかし「城塞」では、二人は燃えさかる本丸から山里廓の糒蔵(ほしいぐら)に逃げ込みながら、なお生きるつもりでいる人間らしさが書かれています。
糒蔵の場所を確認したあと作戦を練る家康と秀忠の阿吽の芝居はみごとです。家康は冬の陣の講和の誓紙の手前、秀頼の罪を許すことを周囲に聞こえるほどの大声でいい、それに対して秀忠は『この者にお情けをおかけあそばす御仁慈はありがたけれども、天下静謐のためにはお情けのみにては参り候わず。よろしくここはそれがしの裁断にお任せくださいますように』と。ここで豊臣を完全に叩いておかないと徳川の世には移行できません。家康の寛大さと秀忠の将軍の威厳を世に示しその効果を考えてのことでした。
逃げ混んだ糒蔵に銃弾と大筒が撃ち込まれ白煙があがったころ、蔵の内から自刃の終了を思わせる火が噴き始めました。淀と秀頼、家臣たちも腹を切り喉をつき、最後に残った者が焔硝を撒いて火をつけ死骸をことごとく灰にしたのです。火薬をこのように使用した大野修理の潔さと家康・秀忠の芝居の卑俗さを比較して、修理が「豊臣家の最期を詩」にしたことが世間と後世への効果を大きくしたと司馬氏は言っています。
関ヶ原のとき多くの外様大名が功名をたて、そのために家康は封を与えざるを得なくなり、そのうえ恩を着る羽目に陥りました。しかしこの大阪の陣では、できるだけ外様大名に功をたてさせないように後方に配置したり、目立たないようにしたのです。全てこれから続かせていく徳川の時代を見据えてのことでした。
最終回の「江」がどんな終わり方をするか楽しみです。



























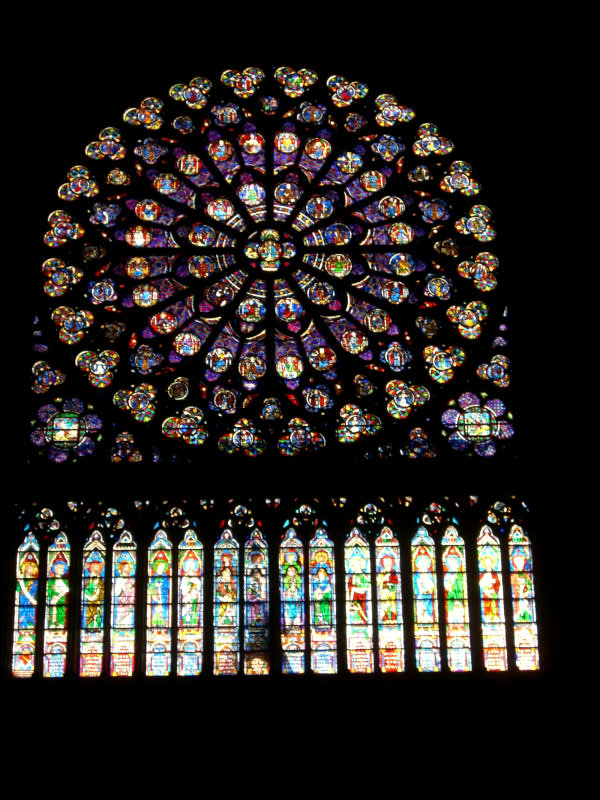































 紫の椅子がかわいい地下鉄「Opera」のホーム。帰りは、ここで地下鉄3番線「Pont de Levallois Becon 」行きに乗り、3つ目の駅「Europe」で下車するとすぐホテルです。今回のホテルはどこへ行くにもアクセスが非常にいいので大変助かりました。
紫の椅子がかわいい地下鉄「Opera」のホーム。帰りは、ここで地下鉄3番線「Pont de Levallois Becon 」行きに乗り、3つ目の駅「Europe」で下車するとすぐホテルです。今回のホテルはどこへ行くにもアクセスが非常にいいので大変助かりました。 ②乗る駅から降りる駅までを、路線の交差しているところであみだくじみたいに路線をつなぎながら複数の路線番号を確定します。
②乗る駅から降りる駅までを、路線の交差しているところであみだくじみたいに路線をつなぎながら複数の路線番号を確定します。
 サン・ラザール駅から国鉄SNCFの特急ルーアン行に乗り約45分、ヴェルノンで下車。乗車して20分もすればパリとは全く違う風景に出合います。ヴェルノン駅では特急とバスが連絡していますが、急いでバス停に行かないと積み残される恐れがあります。途中セーヌ河を渡り15分でジベルニーの村に着きます。特急は往復で13.2€。とにかく交通機関が安いのはありがたいです
サン・ラザール駅から国鉄SNCFの特急ルーアン行に乗り約45分、ヴェルノンで下車。乗車して20分もすればパリとは全く違う風景に出合います。ヴェルノン駅では特急とバスが連絡していますが、急いでバス停に行かないと積み残される恐れがあります。途中セーヌ河を渡り15分でジベルニーの村に着きます。特急は往復で13.2€。とにかく交通機関が安いのはありがたいです





















 行列ができるというパリ・アンジェリーナ(Angelina)のモンブランをヴェルサイユ宮殿のカフェでゲット!ただ場所が宮殿の一角のスタンドでスプーンはプラスチックだしティーも紙コップだし、ちょっと味気ないけどアンジェリーナだからこれでよし!ウィーンのモンブランとどちらがおいしいかわくわくしてスプーンを入れると、栗の下には濃厚なマロンクリーム、底の台はさっくりしたメレンゲで、しっとりしたスポンジ台がありません。??? 栗の味が薄くてクリーム部分が甘すぎて全部は食べきれませんでした。6.9€でちょっと高め。軍配はだんぜんウィーンに!栗の季節だしあれほど期待したのに、夫のタルト・シトロンの方がおいしそうでした。
行列ができるというパリ・アンジェリーナ(Angelina)のモンブランをヴェルサイユ宮殿のカフェでゲット!ただ場所が宮殿の一角のスタンドでスプーンはプラスチックだしティーも紙コップだし、ちょっと味気ないけどアンジェリーナだからこれでよし!ウィーンのモンブランとどちらがおいしいかわくわくしてスプーンを入れると、栗の下には濃厚なマロンクリーム、底の台はさっくりしたメレンゲで、しっとりしたスポンジ台がありません。??? 栗の味が薄くてクリーム部分が甘すぎて全部は食べきれませんでした。6.9€でちょっと高め。軍配はだんぜんウィーンに!栗の季節だしあれほど期待したのに、夫のタルト・シトロンの方がおいしそうでした。
















