

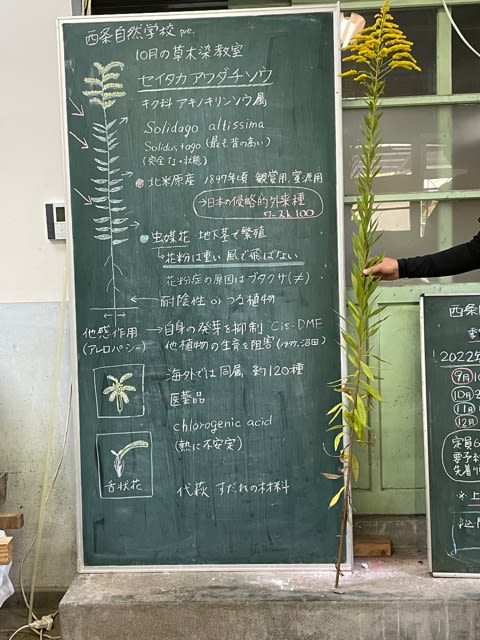
花をアップで見てみました。


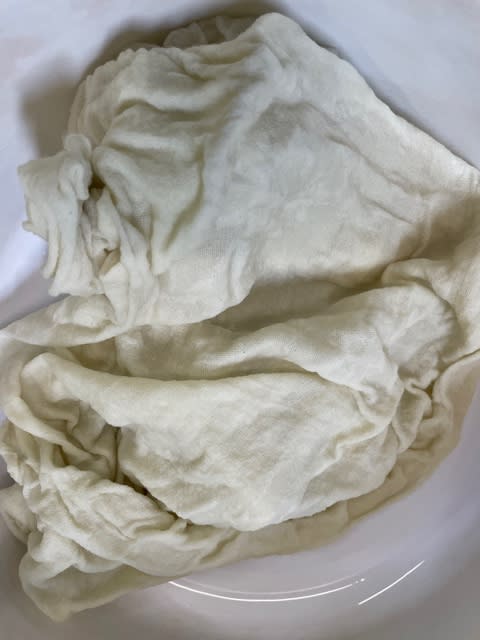
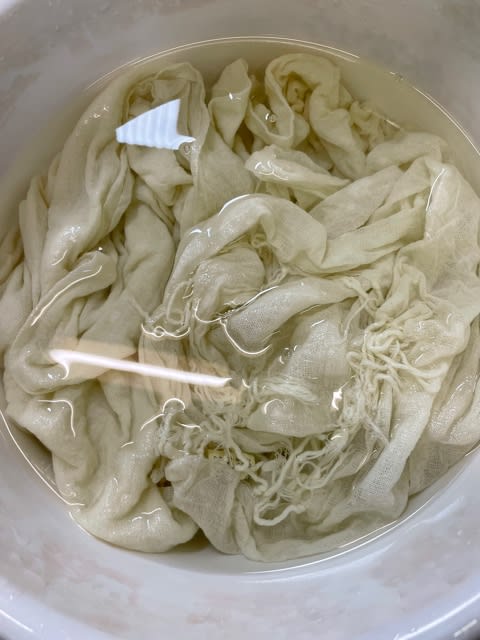


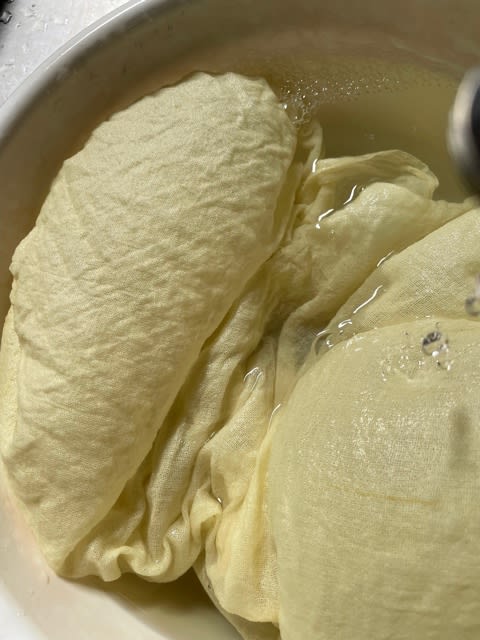







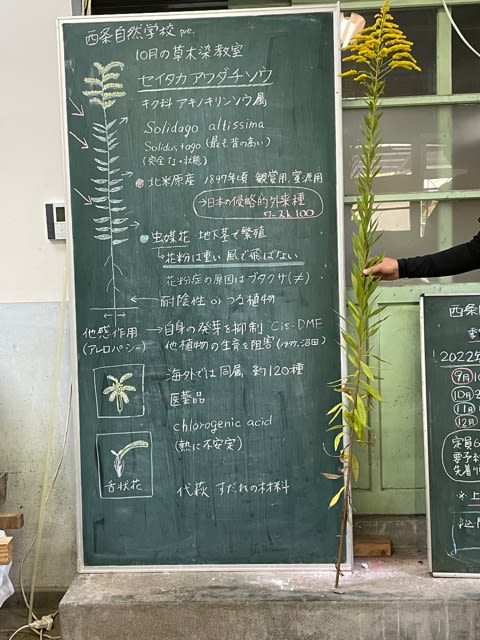


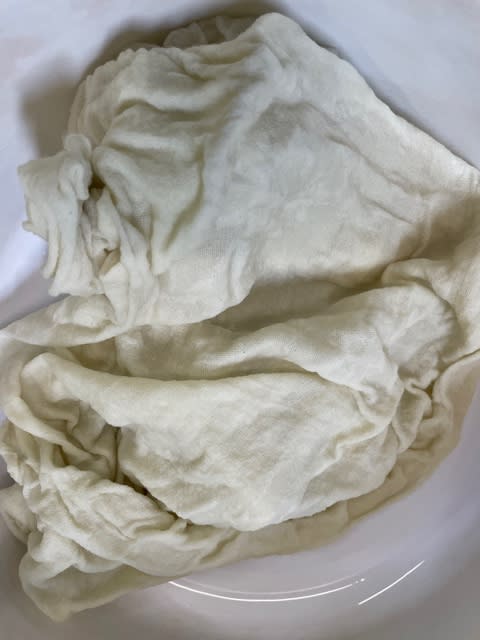
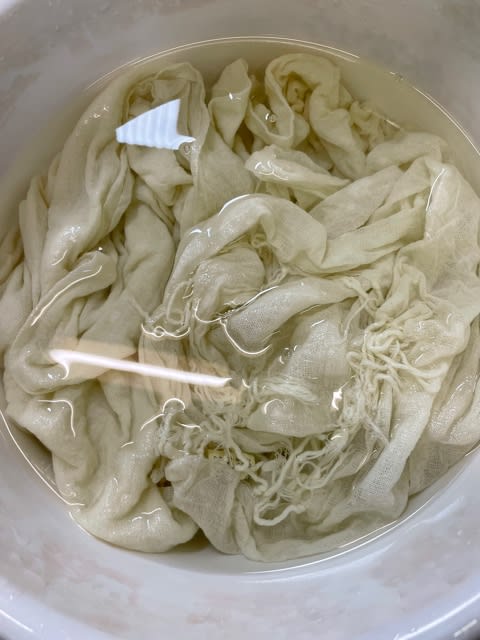


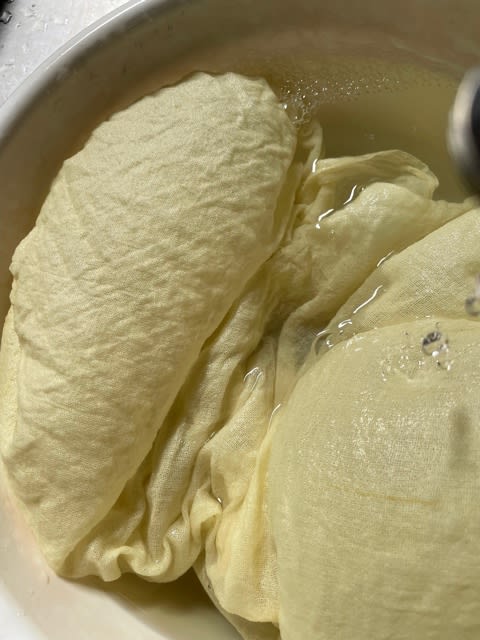








































































、
登り道が続きます。階段だらけは足に堪えます。わたしはついにズボンのひざのファスナーを開けて裾を取り外しました。すると半ズボンになるのです。これで膝のあたりに布の抵抗がなくなり、少し登りやすくなりました。座り込んでそれをしていたらすれ違う人が「大丈夫ですか?」と声をかけてくれました。
語録6 石鎚を好きになってほしいから困っている人を見かけたら進んで助けることにしている(休みのたびに登山する愛好家)
立ち止まっていても「お気をつけて」と言ってくれる人も何人もいました。ベテランの人は挨拶をするときに声や表情で相手の体調を思いやるそうです。
登り続けて夜明かし峠近くまで来ました。娘が小学生の時はここまで来たそうです。(それ以前は山頂まで行っていました。事故があったりして次第に短縮され、今は登山しなくなっています)
ここまで来ると目の前に石鎚山頂が。
右から出た枝の先あたりに山頂社が見えます。 とおい~

これは私のもっともいやなパターンだわ。
人それぞれではありますが、わたしは目の前に目標が見えているのに、歩いても歩いても到達できない道は嫌なのです。堂が森もこのタイプで、森を抜けた先に頂上が見えますが、とても遠くていやでした。逆に土小屋ルートだと先が見えないので、ひたすら歩いていくうちにいつの間にか着いていて、私にはこの方がずっといいです。
で、休憩所は?

山頂社の真下、かなり上のほうにありました。そそり立つ険しい傾斜。あそこまでは行くと決めていました。
語録7 トイレは2の鎖下までありません。登山の前にトイレを済ませましょう(ロープウエイ駅での注意書き)
これ、大事。成就から2.6㎞ すでに3時間近くかかっています。めちゃくちゃ遅い。ここで引き返したら絶対トイレで困るに決まっています。だから休憩所でトイレを済ましてから下りるつもりでした。

夜明かし峠にはルート図がたっています。これでいうと、2の鎖の下に休憩所があります。

成就ルートは土小屋ルートより1㎞短いですがその分傾斜が急で、時間的にはどちらも同じ。土小屋ルートにはところどころに休憩用のベンチが設置されていますが、成就ルートにはベンチはありませんでした。2か所だけ丸太と角材の置かれた場所があって腰を下ろすことはできましたが、それだけです。観光登山者には不親切なルートです。本当に修行の道だなあと思いました。
けど、この道を1歳くらいの幼児を抱っこ紐に抱いて登ってきたお母さんがいたのですよ。母は強し! しかも、そのぼうや、自分で歩きたいと駄々をこねている。ここは危ないからダメとお母さんがなだめていました。
語録8 登山にも英才教育が必要だ。(ずっとソロで登山してきた結果、子供が一緒に登ってくれないと寂しがるお父さん)
そうねえ、親子で登った楽しい経験があるからこそ山登りが好きになるのかもしれません。一緒に登る中でいろいろな知恵もマナーも学んでいくのでしょう。学校で一斉登山をしなくなったからこそ、だれかが教える必要があります。
階段ばかりのしんどい道ですが、眺めがいいので救われました。


振り返ると、登ってきた成就の建物

一週間前に行った瓶が森。


一の鎖に着きました。 私はもちろんう回路を行きます。挑戦した人もいましたがあえなくリタイア。すぐに下りてきました。無理はしないほうがいいです。

たまたま人の姿が途絶えて、たった一人でとぼとぼと歩いていたら目の前に小鳥が。トリミングしたらボケてしまいましたが、あなたはだあれ。

逃げるふうでもなく私の前を案内でもしてくれるように歩いていきました。しばし疲れを忘れました。
語録9 ぼくらは地球の上で遊ばせてもらっている。できるだけ自然の邪魔をしないように、壊さないように気を付けたい(県外から来た大学生ふたり)
ここへ来るまでに、ガンガン音楽をかけて登ってくる若者グループに道を譲りました。わたし、ちょっと迷ったのですけど気のよさそうな青年たちだったのですれ違いざまに声を掛けました。
「お願いがあるんですけど」 息も絶え絶えのばあさんに呼び止められた若者は何事かとびっくりしたことでしょう。 「ボリュームをもうちょっと落としてもらえませんか。小鳥の声が聞こえないから。」本当はイヤホンで聞いてくれと言いたかったけどそれは言いませんでした。その時は本当に小鳥がどこかへ行ってしまってたのです。
大分山が近づいてきました。

そしてついに休憩所がすぐ上に。
鳥居の上に避難所を兼ねた休憩所と、トイレ、その上に2の鎖、3の鎖があります。

ここまでかかった時間 3時間半。標準タイムより1時間も遅かったです。がんばった。
じつはこの鳥居からトイレのある休憩所までの石段が最難関でして、最後の力を振り絞らなければたどり着けません。
小屋に入ってお弁当を食べ、娘に電話しました。
「今休憩所」
「ええ~~ そんなとこまで登ってきたん。がんばったねえ。」
山を登り慣れているお仲間でさえ、喘ぎあえぎだったそうで、わたしなんかとっくにリタイアして下山したと思っていたらしいです。
帰りの下り道は登りよりもきつかったです。
語録10 体が寒くないのに足が震える(ウマオ)生まれて初めて膝が笑うという経験をしたらしい(笑)
語録11 抜きつ抜かれつですなあ、何度も会いましたねえ。(休むたびに道を譲っていた人から)
きつい道だからこそ連帯感が生まれてきます。 きっと同じ時間に下りるんでしょうね。なんて話していたのですが、最後は私が負けました。
抜きつ抜かれつといえば、登るとき前社が森の小屋で先を越された団体ツアーの皆さんを、この下りで追い抜きました。
ツアーに付き添っていたガイドさん、「皆さんゆっくり行きますよ。このお母さんのペースで後をついていきましょう。いいですね。」わたしがペースメーカーになるなんて! みなさん相当お疲れなのかな? あとから追いかけられるのは好きではないので先に行ってもらいました。がすぐにまた追いつきました。
追いついたのは前社が森の小屋です。このツアーの一行が休んでいるのが見えました。私が追い抜いた人たちを待っていたようです。私が休憩所まで行く間に山頂まで行って私より先に帰ってきたのだと思います。皆さんかなりの健脚とお見受けしましたが、さすがに足並みがみだれたようです。

人数の多いツアーなんですよ。足並みが揃わないのも無理ないですね。こんなに大勢が休めるところは他になかったように思います。
ツアー客の一人が男性が添乗員さんに向かって、やれ、歩くスピードが遅いだの、ちんたら下りていたらかえって疲れるだの、文句たらたら言っていました。それを聞いて私も疲れていたものだからちょっとイラっとしたんですわ。ついつい言ってしまいました。
語録12 ツアーなんだから無理ですよ。自分のペースで登りたいなら一人で来なくては(顔だけはにこやかに笑いながらね)
その男性、いかに普段自分が山登りに長けているか、ツアーで来たのは交通手段がないからだとかいろいろ周りの方に言っていましたが・・・ 私も何人かの登山好きの方のブログを読ませていただいていますが、皆さん人を当てにせずぐちぐち言わず、すがすがしい方ばかり。自分で交通の手配もガイドを雇うこともできずツアーでお世話になってるなら仲間の悪口は言わないことです。おまけに地元の人の悪口まで言うなんて
その悪口とはー
登ってくるとき、買わない人にはトイレは貸さないと言った小屋のおじさんのことを、商売人として心が狭いというのです。 しかし、その人の言うように気前よく貸してあげたとしても1日に数百人の、ほとんどが再訪することのない登山者の何人が亭主の人柄に感銘して飴湯を買ってくれるでしょうか。都会の商売とは違うと、わたしは心の中で反論しました。
語録13 石鎚山は団体ツアーには向かない山だ(私他複数の人)
剣山などは、山頂に行かなくても楽しめる場所が何か所かあるし、余力のある人は隣の次郎笈までも行けます。体力に応じて楽しめる山だと思いますが、石鎚山はひたすら登るだけ。無理になったら同じ道を引き返すだけ。考えようによってはつまらない山です。少人数でガイドを雇って登っているグループに何組も会いましたが、初めて登るときはそれがベストのように思います。それに・・・さっきのツアーは人数のわりにガイドさんが少ないような気がしたなあ。去年会ったツアーはガイドさんと添乗員さん、3人以上付いていたような・・・
大勢で登るのではなく自分一人だったら、しんどいながらも楽しみはいろいろあります。
サルノコシカケの仲間でしょうか。まるで貝がへばりついているみたい。




八丁坂を下りきったときホッとしました。上り道がこんなにもうれしいとは。
成就で出迎えてくれた猫ちゃん。 どこかのお店の看板猫で玉ちゃんというんだそうです。めったに出てこないので会えるのはラッキーなんだとか。

しばらく娘たちを待ちましたが下りてこないので先にロープウエイに乗って下りました。こんなこともあろうかと、私の車で来ていたので先に帰るつもりでしたが、駐車場で電話が通じたのでさらに10分ほど待って一緒に帰りました。ウマオは天狗岳にも行ってご満悦でした。
車の中で、娘が山頂で出会った人のことを話してくれました。
なんと! 汚物の袋を持って天狗のように駆け下りて行った人が、先週私たちが廃村をうろついていた時会った青年だというのです。彼はボランティアで石鎚山の環境維持のために汚物の始末やごみ拾い、道の整備などをしているのだそうです。台風で倒れた木や枝も片付けて歩きやすくしてくれたんだそうです。私とすれ違った後、彼は夜勤の仕事に出かけたんですって。
私たちがこうして険しい山に登り自然を満喫できるのも、道を切り開いた役小角から続く先人の苦労に支えられているのだと心からありがたく思いました。そして、気持ちよく登山できるのは、たくさんの信者さんや石鎚を愛してやまない人たちの奉仕の精神があってこそ。本来は信仰の道ですから厳しくはありますが、その分人を思いやりながら真摯に登る人たちにたくさん出会うことができて、登ってよかったなあと思いました。 けど、このしんどさは、もうしばらくは味わわなくていいかな。
追記 下山した時、歩数は17000歩を超えていました。登った階数 36階。すべてが階段だったわけではありませんがそれだけ小刻みの階段が多かったということです。 ポチの散歩を終えた時には20000歩を超えていました。つかれました~ そしてさすがに筋肉痛になりました。翌日ね。まだまだ若い?