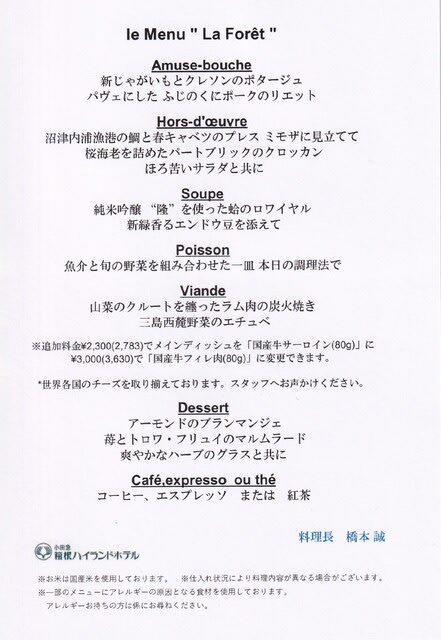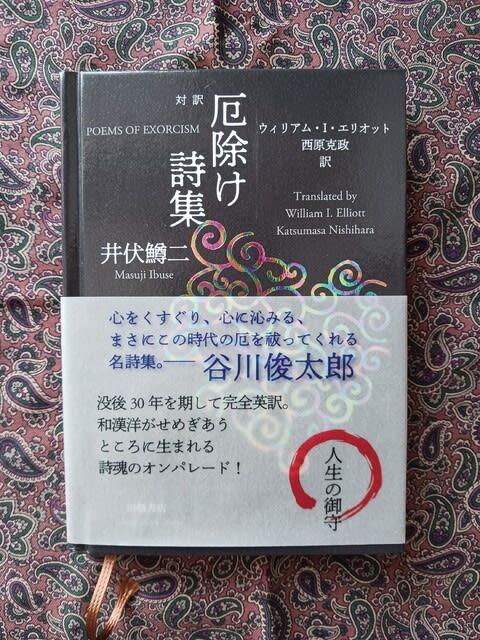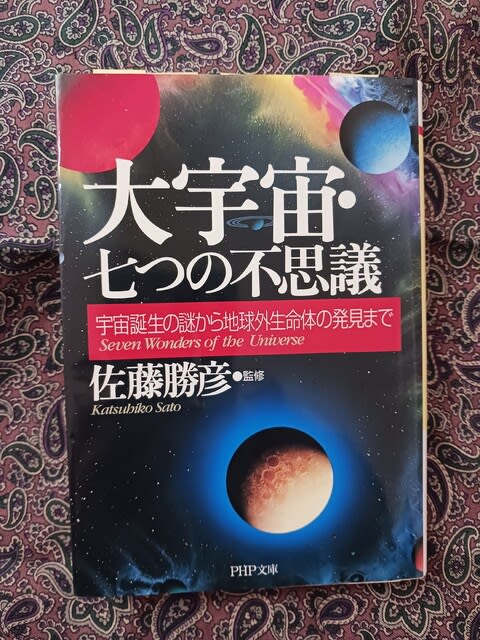一年半ぶりのライブである。前回は河口湖畔での辻井伸行/加古隆/山下洋輔のジョイント。ついでにちょっと足をの延ばしての二泊三日の行程だった。
今回は電車で20分の大和駅から徒歩6分のシリウスの文化芸術大ホール。心身共に安心・安全、楽々の往復であった。身体は正直ですね。

なかなかにエキサイティングなコンサートだった。それは構成に依るところが大きい。一・二部形式。間に20分の休憩を入れ都合2時間半。
第一部はおなじみの有名曲。観客は高齢者が殆ど。若かりし頃、或いは両親が口ずさんでいたタンゴが世界を席巻した時代のナンバーである。
タンゴを辿って世界を回る旅に出ましょうとMC(小松自身が務める)。「まず日本から」と場内に呼びかける。誰しも〔日本のタンゴ?]と。演奏が始まる。『夜のプラットホーム』。服部良一作と紹介される。ドイツ➡イギリス➡アメリカ➡ウルグアイ➡アルゼンチン。


タンゴ特有の楽器の特徴や基本となる4種のリズムの解説など、オーディエンスに分かり易く解説する姿は好感度大。
二部は小松自身の作編曲中心の作品。国府とのコラボもここで登場する。タンゴがこれほど編曲が自由だとは知らなかった。自作曲も実に堂々としたもので、聴く人にタンゴへの愛情を感じるさせるものだった。何よりタンゴの維持・発展そして野心が垣間見えた。このくらいの熱と汗が無ければ、タンゴ世界は維持できなかろう。
彼とこの仲間がいればタンゴの将来は案ずることは無い。そんな思いが去来する一夜であった。
終演後の食事は、大和駅近の大乃寿司。家族で行ったり来たりしてきた40年来の友人夫妻の奥様が働いていた寿司店。
その後館山に転居されて逝去された。もう4年前になろうか。一人館山に住むご主人に、リニューアルの模様などを語り、追善などしようと思う。