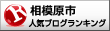トップ画像は2軒が繋がっている看板建築です。
右側が花市生花店。 明治初期に建てられた<看板建築>の花屋です。建物の全面は花屋らしくデザインされています。…遠目に写し過ぎてわかりにくいけど。店内には造花を配置。昭和30年代の花屋を再現しています。/千代田区神田淡路町一丁目 1927年(昭和2)
左側が武井三省堂。 明治初期に創業した文具店です。当初は書道用品のおろしをしていましたが、後に小売店に変りました。建物は震災後に建てられた<看板建築>で前面がタイル貼りになっていて屋根の形にも特徴があります。/千代田区神田須田町一丁目 1927年(昭和2)
内部はこんな感じ。

墨汁とか墨とか筆とか半紙とかとかとか。まるでタイムスリップしたような佇まい。トップ画像の右手の路地に入ると裏手はこんな感じ。

ついでに通りを挟んで向かいに建つ植村邸

建物の前面を銅板で覆った姿は<看板建築>の特徴をよく現しています。外観は、全体的に洋風にまとまっていますが、2階部分は和風のつくりとなっています。/中央区新富二丁目 1927年(昭和2)
ちなみに、WIKIで看板建築を検索すると「関東大震災後、商店などに用いられた建築様式。建築史家藤森照信が命名したもの」とあります。
建築年が近いのでもう一軒。

村上精華堂 台東区池之端の不忍通りに面して建っていた小間物屋(化粧用品屋)です。昭和前期には、化粧用のクリーム・椿油や香水等を作って、卸売りや小売りを行っていました。正面は人造石洗い出しで、イオニア式の柱を持ち、当時としてはとてもモダンな造りとなっています。/台東区池之端二丁目 1928年(昭和3)
建築年代が近いのでもしや…。と思って「関東大震災」をWIKIで検索。関東大震災は1923年(大正12)9月1日に発生してました。震源は相模湾の北西。地震の規模はマグニチュード7、9。発生したのが正午近かったので、火を使っていた家庭が多く、大火が発生したのです。だから看板建築は復興住宅だったんですね。耐火性を向上させるため、建物の外側をモルタルや銅板で覆われたんです。
以前、神田&お茶の水界隈を散歩した時に、神田須田町も散策したのですが、現地にはまだ現役の看板建築が現存してました。







たてもの園の建物と神田にあるお店を並べてみた。しっくり。違和感セロ。驚いた!
これらの建物の正体はこちら。神田須田町老舗めぐり(2009年10月29日)の記事です。必見やもしれん…。自画自賛。

右側が花市生花店。 明治初期に建てられた<看板建築>の花屋です。建物の全面は花屋らしくデザインされています。…遠目に写し過ぎてわかりにくいけど。店内には造花を配置。昭和30年代の花屋を再現しています。/千代田区神田淡路町一丁目 1927年(昭和2)
左側が武井三省堂。 明治初期に創業した文具店です。当初は書道用品のおろしをしていましたが、後に小売店に変りました。建物は震災後に建てられた<看板建築>で前面がタイル貼りになっていて屋根の形にも特徴があります。/千代田区神田須田町一丁目 1927年(昭和2)
内部はこんな感じ。

墨汁とか墨とか筆とか半紙とかとかとか。まるでタイムスリップしたような佇まい。トップ画像の右手の路地に入ると裏手はこんな感じ。

ついでに通りを挟んで向かいに建つ植村邸

建物の前面を銅板で覆った姿は<看板建築>の特徴をよく現しています。外観は、全体的に洋風にまとまっていますが、2階部分は和風のつくりとなっています。/中央区新富二丁目 1927年(昭和2)
ちなみに、WIKIで看板建築を検索すると「関東大震災後、商店などに用いられた建築様式。建築史家藤森照信が命名したもの」とあります。
建築年が近いのでもう一軒。

村上精華堂 台東区池之端の不忍通りに面して建っていた小間物屋(化粧用品屋)です。昭和前期には、化粧用のクリーム・椿油や香水等を作って、卸売りや小売りを行っていました。正面は人造石洗い出しで、イオニア式の柱を持ち、当時としてはとてもモダンな造りとなっています。/台東区池之端二丁目 1928年(昭和3)
建築年代が近いのでもしや…。と思って「関東大震災」をWIKIで検索。関東大震災は1923年(大正12)9月1日に発生してました。震源は相模湾の北西。地震の規模はマグニチュード7、9。発生したのが正午近かったので、火を使っていた家庭が多く、大火が発生したのです。だから看板建築は復興住宅だったんですね。耐火性を向上させるため、建物の外側をモルタルや銅板で覆われたんです。
以前、神田&お茶の水界隈を散歩した時に、神田須田町も散策したのですが、現地にはまだ現役の看板建築が現存してました。







たてもの園の建物と神田にあるお店を並べてみた。しっくり。違和感セロ。驚いた!
これらの建物の正体はこちら。神田須田町老舗めぐり(2009年10月29日)の記事です。必見やもしれん…。自画自賛。