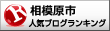次に目指すは箱根板橋の古稀庵の庭なんですが、移動途中にもあれこれあったんで紹介しますね。
つーか、その前に腹ごしらえだ。さっきの山角天神社のベンチに腰掛けて、いつものアンパンとお茶で一息。いや~、9月に入ったら散歩もしやすくなるかと思いましたが、暑いです~。もう体力がだいぶん目減りしてるんですけど…。
さて。地図を片手に次なる場所は。
 人車鉄道 小田原駅跡。
人車鉄道 小田原駅跡。
…往時を偲ぶものはこれだけ~。石碑を撮影してて気づいた!
歩道橋に道路の行き先案内板がかかってます。そういや、コレ国道1号線だったわ。
次、次々。もう30度を超えてるピーカンの炎天下、そんなに元気に歩けるか~~っ!!
ぼやきが入り始めました。早っ!!
到着したのは「早川口遺構」です。小田原城の現存する数少ない総構えの一部です。
それって、明治の邸宅巡りと関係ないんじゃないの?と思われましたか。
そんなことないんですよ。この場所はかつては因藤成光の旧邸でして一時期庭園として使われていたのです。小田原城の豪快な土塁や堀を上り下りして体感出来ます。

ちょっと規模が大きすぎて画像ではなんだかよくわからない感じになってしまいましたが、トップ画像も早川口遺構を選びました。画像右手が土塁。左手が空堀です。
説明板発見…。「小田原城は、戦国時代に後北条氏の本城として関東支配の拠点であり、政治•経済•文化の中心を担っていました。
小田原城は、永禄4年(1561)に長尾景虎(上杉謙信)、永禄12年(1569)には武田信玄に攻め込まれましたが、三代氏康は籠城戦により退けました。これ以降、小田原城では相次いで改修工事が進められ、天正15年(1587)なでには丘陵部を取り込んだ三の丸外郭を造営したと考えられます。
さらに、天正18年(1590)、全国統一を進める豊臣秀吉との戦い(小田原合戦)の際しては、城下をも取り込んだ土塁と堀からなる周囲訳キロメートルに及ぶ「総構え」を造営し、小田原城の強化を図りました。
この早川口遺構は、小田原城総構の南西に位置する虎口(城の出入り口)で、その遺構は、二重戸張と呼ばれる土塁と堀を二重に配した構造となっています。この場所は明治時代以降に屋敷の庭園として少なからぬ改変を受けており、本来の遺構の姿を留めておりませんが、外側の高さ2、8メートル程の土塁や堀状の窪地などは当時の遺構の姿が残されたものといえます」だそうで。
………。かつて土塁だったと思われる場所のてっぺんに登り、かつて堀だったと思われる場所に降りてみた。
…なにげに楽しい。でも土塁と堀を堪能したければやはり冬にこないと!草に埋もれて状態がわからん。
続いてサクサク移動です。
陸橋の下をくぐってると、変わった貼板を発見!

この上は東海道本線が通っているのです。

陸橋を抜けると南側に大久寺があります。こちらは大久保一族のお墓があるそうなので、見学に。
あれ?東海道本線になぜに小田急のロマンスカーが走ってるんじゃ??
地図で確認。すると、JRに隣接して箱根登山鉄道が通ってました。画像のロマンスカーは小田急の相互乗り入れで箱根湯本まで行くやつですね。


説明板発見「大久寺…大久寺は宝聚山随心院と号法華宗8現在は日蓮宗)の寺で、小田原大久保の初代七郎を開基とする寺である。
天正18年(1590)の小田原合戦に、徳川家康に従って参戦した遠州二俣城主大久保忠世は、合戦後論行賞によって小田原城4万5千石が与えられた。この時忠世は日頃から帰依していた僧自得院日英を二俣から招請し、しばらくは石垣山三の丸(古称聖人屋敷)に仮住いでいた。そして忠世が開基となって寺の建設をすすめ、翌天正19年堂字が完成すると、日英を開山とする大久保家の菩提寺とした。
慶長19年(1614)二代相模守忠隣の時、大久保家が改易になると寺も衰退したので、寛永10年(1633)石川主殿頭忠総(忠隣二男、石川日向守家成養子)が大久寺を江戸下谷に移した。その後、大久保新八郎康任が石塔、位牌を戻して大久寺がこの地に再建された。
墓石は、正面右から小田原大久保氏三代加賀守忠常、二代相模守忠隣、藩祖七郎右衛門忠世、勘三郎忠良(忠勝五男)、五郎左衛門忠勝(忠俊の子)、常源忠俊(忠世の伯父)、忠良の娘の墓で、これらは前期大久保氏一族の墓所として小田原市の史跡に指定されている。
大久保氏の墓所は、法華宗陣門流の大本山京都の本禅寺、愛知県岡崎市の長福寺、東京青山の敬学院にもある。」ですって!
このお墓って、小田原城の城主の一族のものなんですね。
以前、JR小田原駅近くにある北条氏政、氏照の墓所北条早雲像(2010年4月30日)の記事こちらに北条氏政、氏照の墓所の画像があります。
や入生田駅近くの稲葉一族の墓所にも訪れたことがあります。これらの墓所も小田原城主のお墓でした。なんだか不思議~~。
ちなみに、稲葉一族は、今年のNHKの大河「江」でも出てくる徳川三代将軍、徳川家光の乳母を務めた春日局の一族でうす。入生田の長興山紹太寺には春日局のお墓もあります。
さて次だっ!!
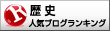
つーか、その前に腹ごしらえだ。さっきの山角天神社のベンチに腰掛けて、いつものアンパンとお茶で一息。いや~、9月に入ったら散歩もしやすくなるかと思いましたが、暑いです~。もう体力がだいぶん目減りしてるんですけど…。
さて。地図を片手に次なる場所は。
 人車鉄道 小田原駅跡。
人車鉄道 小田原駅跡。…往時を偲ぶものはこれだけ~。石碑を撮影してて気づいた!
歩道橋に道路の行き先案内板がかかってます。そういや、コレ国道1号線だったわ。
次、次々。もう30度を超えてるピーカンの炎天下、そんなに元気に歩けるか~~っ!!
ぼやきが入り始めました。早っ!!
到着したのは「早川口遺構」です。小田原城の現存する数少ない総構えの一部です。
それって、明治の邸宅巡りと関係ないんじゃないの?と思われましたか。
そんなことないんですよ。この場所はかつては因藤成光の旧邸でして一時期庭園として使われていたのです。小田原城の豪快な土塁や堀を上り下りして体感出来ます。

ちょっと規模が大きすぎて画像ではなんだかよくわからない感じになってしまいましたが、トップ画像も早川口遺構を選びました。画像右手が土塁。左手が空堀です。
説明板発見…。「小田原城は、戦国時代に後北条氏の本城として関東支配の拠点であり、政治•経済•文化の中心を担っていました。
小田原城は、永禄4年(1561)に長尾景虎(上杉謙信)、永禄12年(1569)には武田信玄に攻め込まれましたが、三代氏康は籠城戦により退けました。これ以降、小田原城では相次いで改修工事が進められ、天正15年(1587)なでには丘陵部を取り込んだ三の丸外郭を造営したと考えられます。
さらに、天正18年(1590)、全国統一を進める豊臣秀吉との戦い(小田原合戦)の際しては、城下をも取り込んだ土塁と堀からなる周囲訳キロメートルに及ぶ「総構え」を造営し、小田原城の強化を図りました。
この早川口遺構は、小田原城総構の南西に位置する虎口(城の出入り口)で、その遺構は、二重戸張と呼ばれる土塁と堀を二重に配した構造となっています。この場所は明治時代以降に屋敷の庭園として少なからぬ改変を受けており、本来の遺構の姿を留めておりませんが、外側の高さ2、8メートル程の土塁や堀状の窪地などは当時の遺構の姿が残されたものといえます」だそうで。
………。かつて土塁だったと思われる場所のてっぺんに登り、かつて堀だったと思われる場所に降りてみた。
…なにげに楽しい。でも土塁と堀を堪能したければやはり冬にこないと!草に埋もれて状態がわからん。
続いてサクサク移動です。
陸橋の下をくぐってると、変わった貼板を発見!

この上は東海道本線が通っているのです。

陸橋を抜けると南側に大久寺があります。こちらは大久保一族のお墓があるそうなので、見学に。
あれ?東海道本線になぜに小田急のロマンスカーが走ってるんじゃ??
地図で確認。すると、JRに隣接して箱根登山鉄道が通ってました。画像のロマンスカーは小田急の相互乗り入れで箱根湯本まで行くやつですね。


説明板発見「大久寺…大久寺は宝聚山随心院と号法華宗8現在は日蓮宗)の寺で、小田原大久保の初代七郎を開基とする寺である。
天正18年(1590)の小田原合戦に、徳川家康に従って参戦した遠州二俣城主大久保忠世は、合戦後論行賞によって小田原城4万5千石が与えられた。この時忠世は日頃から帰依していた僧自得院日英を二俣から招請し、しばらくは石垣山三の丸(古称聖人屋敷)に仮住いでいた。そして忠世が開基となって寺の建設をすすめ、翌天正19年堂字が完成すると、日英を開山とする大久保家の菩提寺とした。
慶長19年(1614)二代相模守忠隣の時、大久保家が改易になると寺も衰退したので、寛永10年(1633)石川主殿頭忠総(忠隣二男、石川日向守家成養子)が大久寺を江戸下谷に移した。その後、大久保新八郎康任が石塔、位牌を戻して大久寺がこの地に再建された。
墓石は、正面右から小田原大久保氏三代加賀守忠常、二代相模守忠隣、藩祖七郎右衛門忠世、勘三郎忠良(忠勝五男)、五郎左衛門忠勝(忠俊の子)、常源忠俊(忠世の伯父)、忠良の娘の墓で、これらは前期大久保氏一族の墓所として小田原市の史跡に指定されている。
大久保氏の墓所は、法華宗陣門流の大本山京都の本禅寺、愛知県岡崎市の長福寺、東京青山の敬学院にもある。」ですって!
このお墓って、小田原城の城主の一族のものなんですね。
以前、JR小田原駅近くにある北条氏政、氏照の墓所北条早雲像(2010年4月30日)の記事こちらに北条氏政、氏照の墓所の画像があります。
や入生田駅近くの稲葉一族の墓所にも訪れたことがあります。これらの墓所も小田原城主のお墓でした。なんだか不思議~~。
ちなみに、稲葉一族は、今年のNHKの大河「江」でも出てくる徳川三代将軍、徳川家光の乳母を務めた春日局の一族でうす。入生田の長興山紹太寺には春日局のお墓もあります。
さて次だっ!!