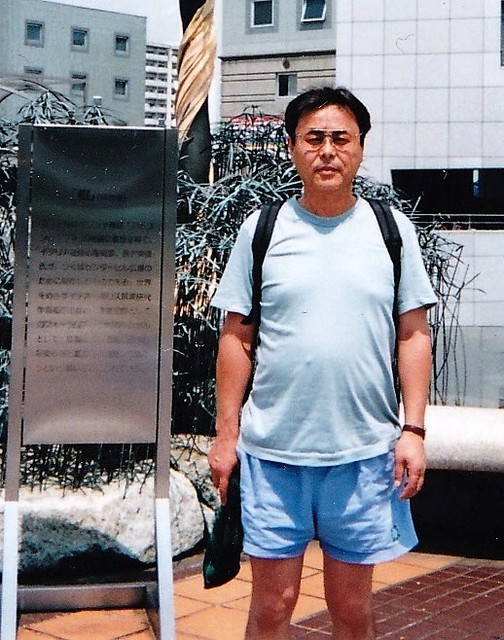金曜日の続きです。
それで、“一人旅の女性”が滝の姿をカメラに収めるのを、それとなく、それなりに、辺りを眺めつつ待っていたのです。
何となく、それとなく、それなりの「緊張感」を、勝手に楽しみながら待つ。まぁ、何と云うか、ふつうの中年女性何ですけどねぇ、そこは「旅先」ですので、それなりの「遊び心」と云ったところです。
それで、女性が立ち去り、次は私の番になりました。寺の境内の、そのまた本堂の裏にある小さな滝なのですが、紅葉と苔生す岩を背景に、深山幽谷の趣なのです。

小さいけれどれど、大自然の広がりを感じさせる風景です。妙雲寺“常楽滝”はなかなかの風景です。
灯籠越しに滝を狙ってみたのですが、滝が隠れてしまいちょっと失敗です。

滝の傍に、苔生したこんな案内板がありました。夏目漱石も今から82年前に、この滝を見物していたのです。

常楽滝を詠んだ漢詩です。漢詩を読むと「直立不動」になります。

※石に刻まれた「詩碑」を撮るのを忘れてしまいました。
『蕭条たる古刹 崔嵬に依る』
“ショウジョウたるコサツ サイカイにヨル”
明治の匂いがしてきます。堅いです、凛々しいです、疲れます。
『直ちに銀蟒と為なりて 仏前に来たる』
“タダチにギンポウとナリテ ブツゼンにキタル”
漱石さんもこんな漢詩を詠んだのです、知りませんでした。
漱石も、やはり滝を観るとふつうに「大蛇」を連想するようです。山奥の渓谷、古い寺、ゴツゴツとした岩山・・・・・・、漱石さんも、私と「同じ?」感想を抱いたようです。
苔生した藁葺きの門、風景が漢詩に見えてきます。

山の中腹へ連なる杉の大木、これも漢詩です。

このお堂も漢詩。詩吟が流れて来るようです。

そこに、これです! 石灯籠を支える「鬼」です。

これは笑えました。この不自然な姿勢はかなり疲れます。これは「狂歌」の風景です。ホントにご苦労様です。
そろそろ暗くなり、予報どおり雨も落ちてきました、宿に戻る事にします。裏から入って表門から出ます。

宿までは1分ほどの距離でした。宿の裏がお寺だったのです。
順序が逆になってしまったのですが、宿に帰ってフロントで貰ったパンフレットです。

塩原は「門前温泉」だったのです。「鐘の音しみる文学の里」だったのです。まったく知りませんでした。
妙雲寺には、明治、大正、昭和、文人達の碑が沢山あるようです。
塩原温泉は“文学温泉”でした。
これから、温泉にゆっくりつかって、そして食事です。
それでは、また明日。
それで、“一人旅の女性”が滝の姿をカメラに収めるのを、それとなく、それなりに、辺りを眺めつつ待っていたのです。
何となく、それとなく、それなりの「緊張感」を、勝手に楽しみながら待つ。まぁ、何と云うか、ふつうの中年女性何ですけどねぇ、そこは「旅先」ですので、それなりの「遊び心」と云ったところです。
それで、女性が立ち去り、次は私の番になりました。寺の境内の、そのまた本堂の裏にある小さな滝なのですが、紅葉と苔生す岩を背景に、深山幽谷の趣なのです。

小さいけれどれど、大自然の広がりを感じさせる風景です。妙雲寺“常楽滝”はなかなかの風景です。
灯籠越しに滝を狙ってみたのですが、滝が隠れてしまいちょっと失敗です。

滝の傍に、苔生したこんな案内板がありました。夏目漱石も今から82年前に、この滝を見物していたのです。

常楽滝を詠んだ漢詩です。漢詩を読むと「直立不動」になります。

※石に刻まれた「詩碑」を撮るのを忘れてしまいました。
『蕭条たる古刹 崔嵬に依る』
“ショウジョウたるコサツ サイカイにヨル”
明治の匂いがしてきます。堅いです、凛々しいです、疲れます。
『直ちに銀蟒と為なりて 仏前に来たる』
“タダチにギンポウとナリテ ブツゼンにキタル”
漱石さんもこんな漢詩を詠んだのです、知りませんでした。
漱石も、やはり滝を観るとふつうに「大蛇」を連想するようです。山奥の渓谷、古い寺、ゴツゴツとした岩山・・・・・・、漱石さんも、私と「同じ?」感想を抱いたようです。
苔生した藁葺きの門、風景が漢詩に見えてきます。

山の中腹へ連なる杉の大木、これも漢詩です。

このお堂も漢詩。詩吟が流れて来るようです。

そこに、これです! 石灯籠を支える「鬼」です。

これは笑えました。この不自然な姿勢はかなり疲れます。これは「狂歌」の風景です。ホントにご苦労様です。
そろそろ暗くなり、予報どおり雨も落ちてきました、宿に戻る事にします。裏から入って表門から出ます。

宿までは1分ほどの距離でした。宿の裏がお寺だったのです。
順序が逆になってしまったのですが、宿に帰ってフロントで貰ったパンフレットです。

塩原は「門前温泉」だったのです。「鐘の音しみる文学の里」だったのです。まったく知りませんでした。
妙雲寺には、明治、大正、昭和、文人達の碑が沢山あるようです。
塩原温泉は“文学温泉”でした。
これから、温泉にゆっくりつかって、そして食事です。
それでは、また明日。