The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―24. ISO,品質規格,品質改善活動の3本柱によって、品質を向上させる”
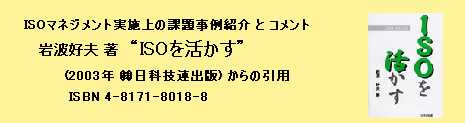
このシリーズも とうとう “第3章 品質を向上させる方法” に入って来ました。
さて、今回は、ISO9001マネジメント・システムの運営の問題です。
【組織の問題点】
ゲーム機器メーカーのA社は、同業他社がISO9001認証を取得し始めたので、製造不良の低減も目的として、3年前にISO9001認証を取得しました。しかし、その後も製造不良は一向に減少せず、困っている、とのことです。
【ISO活用による解決策】
またまた 周辺の情報が 乏しい事例です。
著者・岩波氏は ISO9001は “仕事のしくみを決めたもの” であり、“製品に対する要求事項、すなわち「製品規格」” を “補完するものである” と ISO9001 0.1項を引用して 述べています。つまり、“製品規格とISO9001の両方が、品質保証のために重要な規格、すなわち「しくみ」であるということです。”
“しかし「しくみ」だけでは、品質はよくなりません。実際に品質を向上させるためには、・・・(中略)・・・「品質改善活動」を推進することが重要です。「品質改善活動」にはたとえば、TQM活動、TPM活動、QCサークル活動、改善提案活動などがあります。”
“すなわちISO認証を取得すれば、自動的に品質がよくなるというわけではありません。”
【ポイント】
この事例での 著者の総括は 以下の通りです。

【磯野及泉のコメント】
著者・岩波氏の指摘は 極めて 常識的 当然の内容であると思います。
それにしても、この著者の言葉 “ISO認証を取得すれば、自動的に品質がよくなるというわけではありません。” は、依存心の強い経営者には 衝撃的ではないでしょうか。この事例で “A社は、同業者でISO9001認証を取得するところが増えてきたため、製造不良の低減を目的に、3年前にISO9001認証を取得しました。” と あります。いかにも 現在の日本の経営者メンタリティが 十分に伝わって来ます。あたかも ISO9001の認証が 経営改革の呪文を獲得することであるかのような 経営者の受動的メンタリティです。
こういう 経営者のメンタリティを改めない限り、前回指摘した通り、ISOマネジメントシステムは いつまで経っても 自家薬籠中のモノには出来ません。
なお、“改善活動”に関連して、“継続的改善”の仕組の一つとして 改善提案制度 を 生かすというのも ISO9001マネジメント活動の テクニックとしてあり得ます。そして、これをマニュアルに “継続的改善”の具体的活動として記載することが できます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 中越沖地震へ... | いつの間にか... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




