1958年に三代目駅舎として建てられた新潟駅万代口駅舎。地下には名店街が入り、昨年3月までは本屋などもありました。今年の3月23日にCocolo万代が完全に閉鎖されてからは、駅弁屋など一部の店舗だけになっていました。そして、今年10月3日の内覧会を経て、昨日運用を停止しました。明日のメディアステーションbananaの1日限定復活などのイベントをもって、新潟駅万代口駅舎は完全に大団円となります。
早速ですが、在りし日の新潟駅万代口駅舎を見てみましょう。
自動改札の左手には、自動券売機(指定席券売機を含む)とみどりの窓口がありました。
その隣には、Cocolo万代の跡がありました。旧名店街につながる通路は完全に塞がれてました。
で、その右手にはWEEKENDがありましたが、9月30日をもって閉店しました。
その向かいにはNewDaysとたび御膳があり、その前ではしばしば特産品などが販売されてました。
WEEKENDの隣には無料で入れる待合室がありました。
その待合室には115系の廃車発生品を利用した椅子もありました。
メディアステーションBananaの跡には鉄道模型が置かれてました。
その向かいにはコインロッカーがありましたが、10月2日をもって使用停止となりました。
待合室から鉄道警察隊を経るとATMコーナーが。10月8日を最後に閉鎖されました。
その90°相対して向かいにはびゅうプラザがありました。
外には右からVIE DE FRANCE(9月30日閉店)、やなぎ庵(9月27日閉店)、駅の八百屋(9月30日閉店)がありました。
それでは、2020年8月からの新潟駅高架化工事のあらましを見てみましょう。
2020年8月8日。8、9番線からの通路の狭くなっている部分の一部はオープンになってました。
西改札から西側自由通路の短絡路はもう運用再開してました。右手には意味ありげな構造物が

2020年8月14日。2番線の旧階段は骨組だけになってました。
2020年9月5日。新潟駅新万代口の一部があらわに 茶系です。
茶系です。
2番線は、白山方が延伸されて新たな構造物がつくられようとしてました。業務用エレベーターに違いありません。
2020年9月27日。8、9番線の狭くなっている部分では、ヨド物置のようなものが置かれてました。
9月30日をもってCocolo中央のオレンジガーデンが閉店しました。ビッグスワン内に移ることになっています。
2020年10月3日。ぽんしゅ館クラフトマンの隣には、意味ありげな構造物が

2020年10月6日。お忘れ物センターとレールゴーサービスになってました。
2、3番線の間には鉄道警察隊が移設されました。相談室が新設されました。
2020年10月8日。西改札前にはびゅうプラザが移転してきました。営業時間は10:00~17:00です。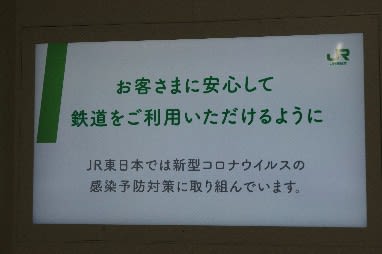
びゅうプラザの前には2台のサイネージが設けられました。
2~5番線コンコースから東改札、万代口への通路。分岐点に空間が開いてました 翌日から変わる予感。
翌日から変わる予感。
8、9番線への通路の狭くなっている部分はもうオープンになり、みどりの窓口のようなものがも これはもう間違いない。
これはもう間違いない。
ついにその日を迎えました。
まずは、その仮万代口の入口を。西側自由通路の入口をちょっといじった形状です。
仮万代口に早速入ると、右手にはKIOSKが。
少し広くなったと思ったら、自動改札の左手にはみどりの窓口。トイレはゴミ箱の脇に。自動券売機(指定席券売機を含む)は奥に。尚、窓口営業時間は5:30~20:20です。
自動改札は5台。すぐ左には8、9番線。
折角なので、2~5番線に進んでみます。しばらく直進して右に曲がります。
少し歩くと左折して上りになります。右手にはエレベーター。Cocolo本館などに行くには、再び右折することになります。
仮万代口開設レポートは以上です。仮万代口は、8、9番線に直結するようになっています。2~5番線、新幹線ホームに行くには以前より歩かされます。8、9番線に発着する列車から高架ホームに発着する列車への乗り継ぎは以前より時間を要するといえます。
仮万代口の設備ですが、KIOSKとトイレ以外には何もありません。駅弁屋はなくなっています。イベントなどは一切で出来ないので。
新潟駅万代口は、来週から取り壊しが始まるものと思われます。JR東日本新潟支社の新社屋も来月移転します。新潟駅高架化工事は、今まさに佳境を迎えているといえよう。次の段階は、万代広場の改造ですかね。
いよいよ大詰めを迎えている日高本線の存廃問題。JR北海道と沿線7町が、来年4月1日付で鵡川〜様似間を廃止して完全にバス転換することに正式に合意したことが昨日判明しました。来る10月23日に合意締結書を交わすということです。残る問題は、2016年の連続台風で大破した護岸の工事のコストを誰が負担するか等ですかね。
さて、本題に。「いなほ6号」の撮影を終え、再び踏切を渡って。間島駅への戻りは集落を通って。
間もなくすると、間島集落開発センターを通過。
何とか駅に戻り、10時37分発の825D(GV-E400-8+GV-E400-6+GV-E401-4+GV-E402-4)で酒田方面へ。
10時42分に越後早川駅に到着。ここから単線から複線に変わるポイントで、2面2線+保線用側線1本の構内です。副本線は撤去されています。
では駅舎の中へ。左右にベンチが並んでいるだけで、あとは何もありません。
それでは駅舎撮影。昭和63年3月築の木造駅舎です。トイレは村上方に。これを撮影するのは命がけでした。
というのも、隣に瀬賀医院があり、その向かいに駐車場があって激しく車が出入りしてたからです。
47分の滞在時間で周辺散策。駅前は集落が続きます。
とある民家の一角ではサツキが満開でした
 。
。
15分ほどで駐車場のある建物を通過。吉浦集落センターです。
更に歩を進めるも、集落だけなのでここで駅に戻ります。
駅に戻り、11時29分発の824D(GV-E402-3+GV-E401-3)で村上に戻ります。
936M(E129系B9編成)で新発田に出た後、128D(キハ110-203+キハ110-215)に乗り継いで新妻に帰還ました。
羽越線プチ乗り継ぎ旅は以上です。今回は、桑川駅など4駅にとどまりいずれも既訪問でしたが、20年ぶりに訪問してみると、思わぬ発見があったりするものです。
今回最も目についたのは、駅機能の合理化でした。今回訪問した4駅は、いずれも自動券売機が撤去されて何も無くなっています。今年の3月に撤去されたものと思われます。今年に入って、JR東日本新潟支社は駅機能の合理化を急速に進めています。最近撮影に使った京ケ瀬駅が乗車駅証明書発行機に置き換えられ、今月に入って石打駅が無人化され、越後堀之内駅のみどりの窓口が廃止されるほどです。
さて、822D/825Dですが、国鉄形気動車からGVに変わっても4連は健在でした。特に822Dの場合、酒田方面から鶴岡方面の高校への通学で唯一利用出来る普通列車ですからね。
話が変わりますが、阿武隈急行は今日、6月に仮復旧して回送列車のみの運転にとどまっていた富野〜丸森間について本復旧の目処がついたため、来る10月31日に営業運転を再開すると発表しました。これで、阿武隈急行は元通りになります。
ところで、新潟駅を見てみますと、びゅうプラザが今日移設開業しました。明日は、仮万代口が運用開始となります。次は、新潟駅高架化工事の「いま」をお伝えします。
最後までお読みいただきありがとうございます 。
。
京都丹後鉄道は昨日、一昨日の夜、宮舞線丹後由良〜栗田間にて乗務員が異音を感非常ブレーキをかけたものの効かずに1.4kmほど走行し、栗田駅構内を240m通り過ぎてやっと停車した事象があったと発表しました。これを受けて国交省は昨日重大インシデントに指定し、調査官2人を派遣しています。詳しい原因は調査中ですが、当該車両に金属製のブレーキを効かせるための部品の付け根部分に空気漏れがあったということです。
さて、本題に。越後寒川駅に降り立って周辺散策を終え、脇川街道踏切を渡って駅に戻ります。寒川ふれあいセンターを経て脇川郵便局を通過。
雨はもう上がってました。9時1分発の822D(GV-E402-4+GV-E401-4+GV-E400-6+GV-E400-8)で村上方面へ。
9時27分に間島駅に到着。ここから単線から複線に変わり、2面3線+保線用側線1本の構内です。
跨線橋を渡って駅舎の中へ。左右にタイプの異なるベンチが並んでいますが、無人化されて何もありません。
それでは駅舎撮影。昭和63年3月18日築の木造駅舎です。トイレは酒田方に。
滞在時間は70分。駅前には新潟漁協岩船港支所上海府連絡所が。
ここでバス停を。村上、寒川方面がそれぞれ2本ずつで、いずれも土休日運休です。
駅前の民家では、終いを迎えたツツジが咲き誇ってました 。
。
越後早川方面に歩を進めていくと、集落が尽きて「能化山登山口」なるものを発見 20年くらい前に降り立ったことがある駅でも、改めて訪問すると思いがけない発見があるものです。
20年くらい前に降り立ったことがある駅でも、改めて訪問すると思いがけない発見があるものです。
国道345号に出て再び海沿いに出ました。水平線の向こうには粟島
 。
。
この海域は漁師以外魚などを採れません 漁協がしっかり管理しているのです。
漁協がしっかり管理しているのです。
更に歩を進めていくと、封鎖された旧道のトンネルを発見 旧国道345号のものだろうか。
旧国道345号のものだろうか。
このまま駅に戻るのも何なので、水を張っただけの田んぼで「いなほ6号」を狙うことに。E653系U102編成で通過していきました。車両はちゃんと映りこんでいましたが、背景がちょっと悪かったかな。例によって空気を運んでいたようですが、走ってただけよしとしないと。で、時計を見ると10時17分だ~ 。
。
話が変わりますが、JR東日本は今日、新幹線の速度向上について発表しました。盛岡~新青森間の最高速度については、現行の260km/hから320km/hを目指すとし、7年程度かけて防音壁の嵩上げやトンネル遮蔽板の延長を行うとしています。時短効果は5分程度といいます。また、大宮~上野間の最高速度については、来春のダイヤ改正で現行の110km/hから130km/hに引き上げるとし、時短効果は1分を見込んでいます。
そして、もう1つ。JR東日本は今日、トヨタ自動車及び日立製作所と連携して水素燃料車両を開発すると発表しました。形式名はFV-E991系で、愛称は「ひばり」です。2022年春ごろから南武線(武蔵中原~尻手~浜川崎)及び鶴見線で走行試験を実施するとしています。
つづく
前回の記事で反映出来なかったですが、大井川鐵道は一昨日、「SLかわね路」を来る10月8日に運転再開すると発表しました。当該SLの不具合の修繕が完了したからということです。尚、運転区間は新金谷〜千頭となっています。東海道線からアプローチする場合、新金谷駅で乗り継ぐ必要があります。
さて、本題に。2020年5月16日(土)の朝となりました。雨が降る中、自転車で新津駅に行き、6時16分発の823D(GV-E401-2+GV-E402-2)で出発。
8時4分に越後寒川駅3番線に到着。2面3線+保線用側線1本の構内です。
跨線橋を渡る前に1番線の上屋を。設置から10年半だというのに、もう色褪せてます

跨線橋を渡って駅舎の中へ。村上方にベンチが。窓口がなくなって無人化されて久しく、自動券売機もなくなっています。
それでは駅舎撮影。平成10年12月25日築の簡易駅舎です。トイレは酒田方に。
時刻表を。上下それぞれ8本ずつです。滞在時間は57分。
まずは、北の方に進みます。そぞろ歩きしていると、声を掛けられました。尚、標高は10.5m。
浜道踏切を渡って国道345号に出ました。遠くには粟島
 。
。
駅裏に出ました。駅舎と海岸線の標高差が分かるでしょう。「春の交通安全」ですって

更に南に進みます。粟島を借景に漁船が1艘 。コロナ禍でそうそう旅に出れないので何だか癒されます。
。コロナ禍でそうそう旅に出れないので何だか癒されます。
テトラポットの向こうに磯が見えてきました。このあたりが笹川流れの北端。
更に南に進むと、磯が連続するようになります。このあたりで国道345号の歩道がなくなるので、これ以上の進軍はやめにします。
脇川街道踏切を渡って駅に戻ろうとすると、梅田ターミナル行きの4060レが通過していきました EF510-14が牽引しています。
EF510-14が牽引しています。
つづく
前回の記事で反映出来なかったですが、東京メトロは一昨日、来年上半期に半蔵門線に18000系を投入し、8000系を順次置き換えていくと発表しました。千代田線では精悍な顔つきの車両が主力になってますが、半蔵門線はもっと精悍な顔つきの車両に染め上げられていきます。
それはさておき。これからお伝えするのは、2020年5月15、16日の羽越本線プチ駅巡りです。実は、コロナ前にH100形の乗り始めに函館本線の駅巡りを計画してました。しかし、3月に入ると日本国内で感染爆発の様相を呈し、この北海道旅行を全てキャンセルしました。4月7日には緊急事態宣言が出てしまい、新潟発着のJAL便が全て欠航してしまいました。そこで、「えちごツーデーパス」を使った、県を跨がない羽越本線駅巡りを計画しました。ただ、GW中は道の駅の中が全てクローズしていたので、この時期の実行に至りました。
前置きはこれくらいにして、そろそろ出発しましょう。
2020年5月15日(金)。出発は「いなほ5号」(E653系U102編成)で。自由席はガラガラ。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で車内販売はなし。
村上駅で〆張鶴と大洋盛を購入した後、829D(GV-E401-9+GV-E402-9)に乗り継いで目的の駅へ。この時期は高校の授業が始まっておらず、登校日の高校生がパラパラと乗ってきただけ。
14時9分に桑川駅に到着。ここから複線から単線に変わるので、2面3線の構内です。
駅舎に入ると、「うみの待合室」になってました

それでは駅舎撮影。平成5年11月築の、「笹川流れ 夕日会館」との合築駅舎です。トイレは左右に。
酒田方には大野風柳の歌碑が。「蟹の目の 二つの冬の 海がある」。
一旦駅舎の中へ。道の駅は営業再開しており、土産物屋もカフェも再開してました。館内にはNGT48(?!)の音楽が延々と流れてました。
螺旋階段へ。「山北の四季」の写真がそこらじゅうに
 。上がって右手にはレストラン。
。上がって右手にはレストラン。
左手に進むと粟島の眺望が
 。
。
では、時刻表を。上り、下りとも8本ずつです。滞在時間は31分。
駅前は国道345号。はす向かいには「民宿ちどり」があり、海鮮料理を食べさせてくれるそうです。
横断歩道を渡ると粟島の眺望が
 。いい所に道の駅をつくったね。
。いい所に道の駅をつくったね。
南の方角に。弁天岩は630mの所に。ここから北は「笹川流れ」。
出発の時間が刻々と迫る中ホームへ。下りホーム上にある待合室は「ゆうひ」の待合室。2019年10月7日に竣工しました。
「ゆうひ」の待合室の中へ。海岸の方にテーブルがありますが、如何せん窓ガラスはまだら模様。
跨線橋を渡って2、3番線へ。「ゆき」の待合室です。「ゆうひ」の待合室と同時期の竣工です。
「ゆき」の待合室の中へ。雪模様のガラスに背を向けて座る構造です。
で、村上方には「海里」仕様の駅名標が。この駅で「海里」は長時間停車します(一部期間を除く)。
14時40分発の826D(GV-E402-4+GV-E401-4)で村上に戻ります。
その後、940M(E129系B15編成)で新発田に出た後、130D(キハ110-213+キハ110-202)に乗り継いで一旦帰宅しました。
話が変わりますが、相模鉄道は昨日、11月7、8日のかしわ台の車両基地でのイベントをもって新7000系の大団円とすることを発表しました。1986年にデビューした新7000系ですが、現在は2編成が残されてるに過ぎません。これをもって、直角カルダン駆動車の歴史が1つ終わることになります。尚、その鉄道イベントは事前予約制です。
つづく
参考サイト さいきの駅舎訪問


















