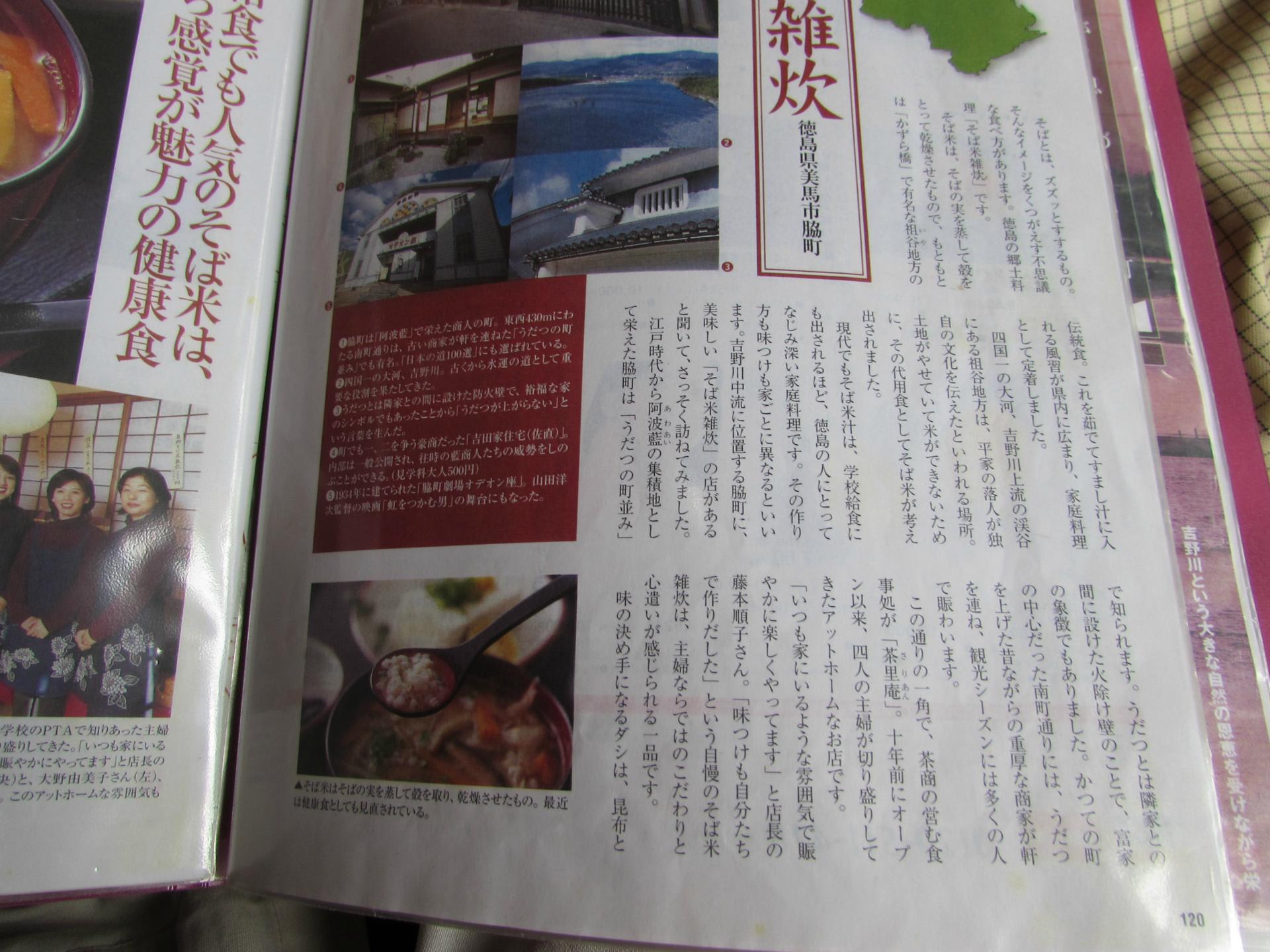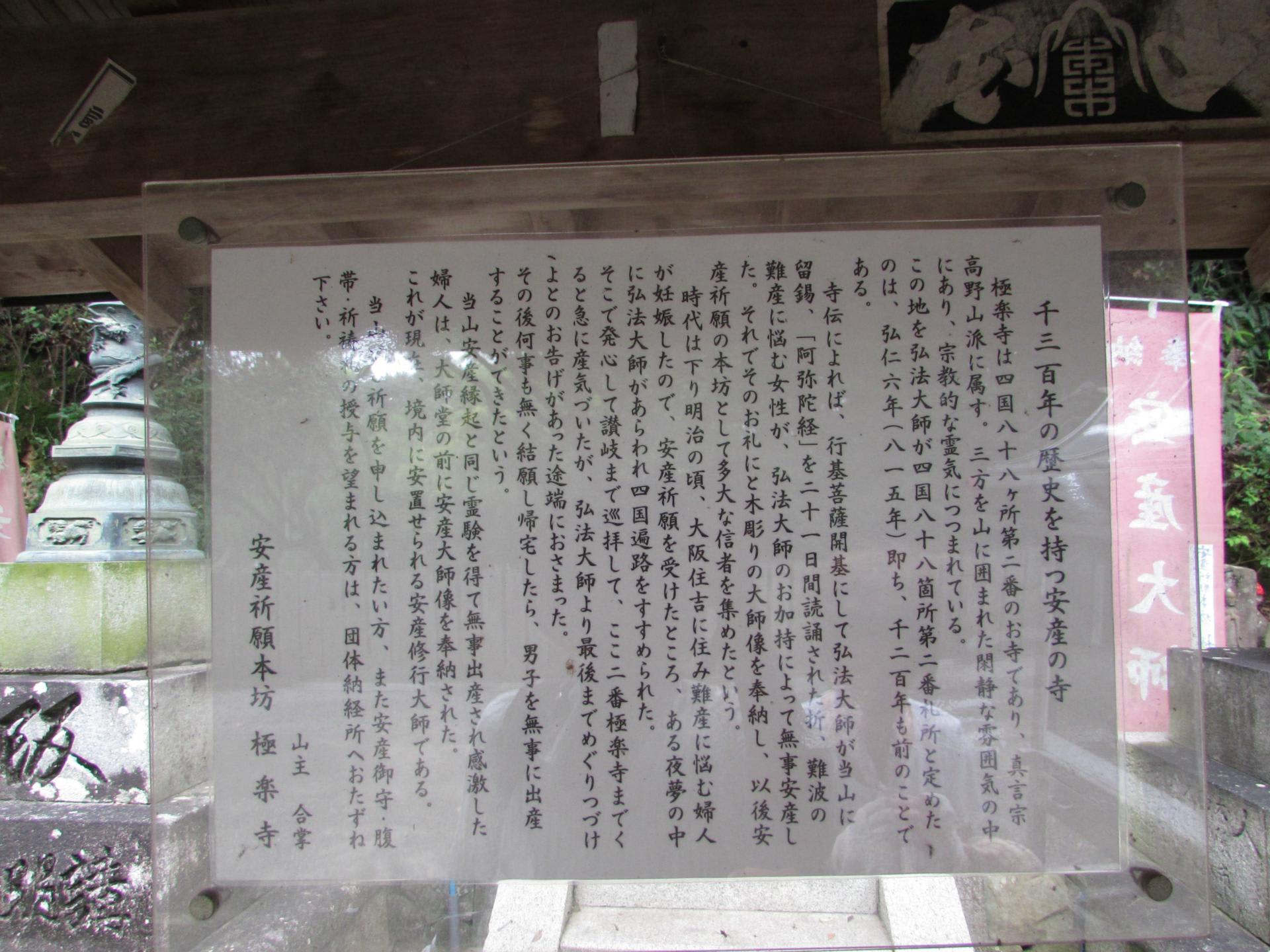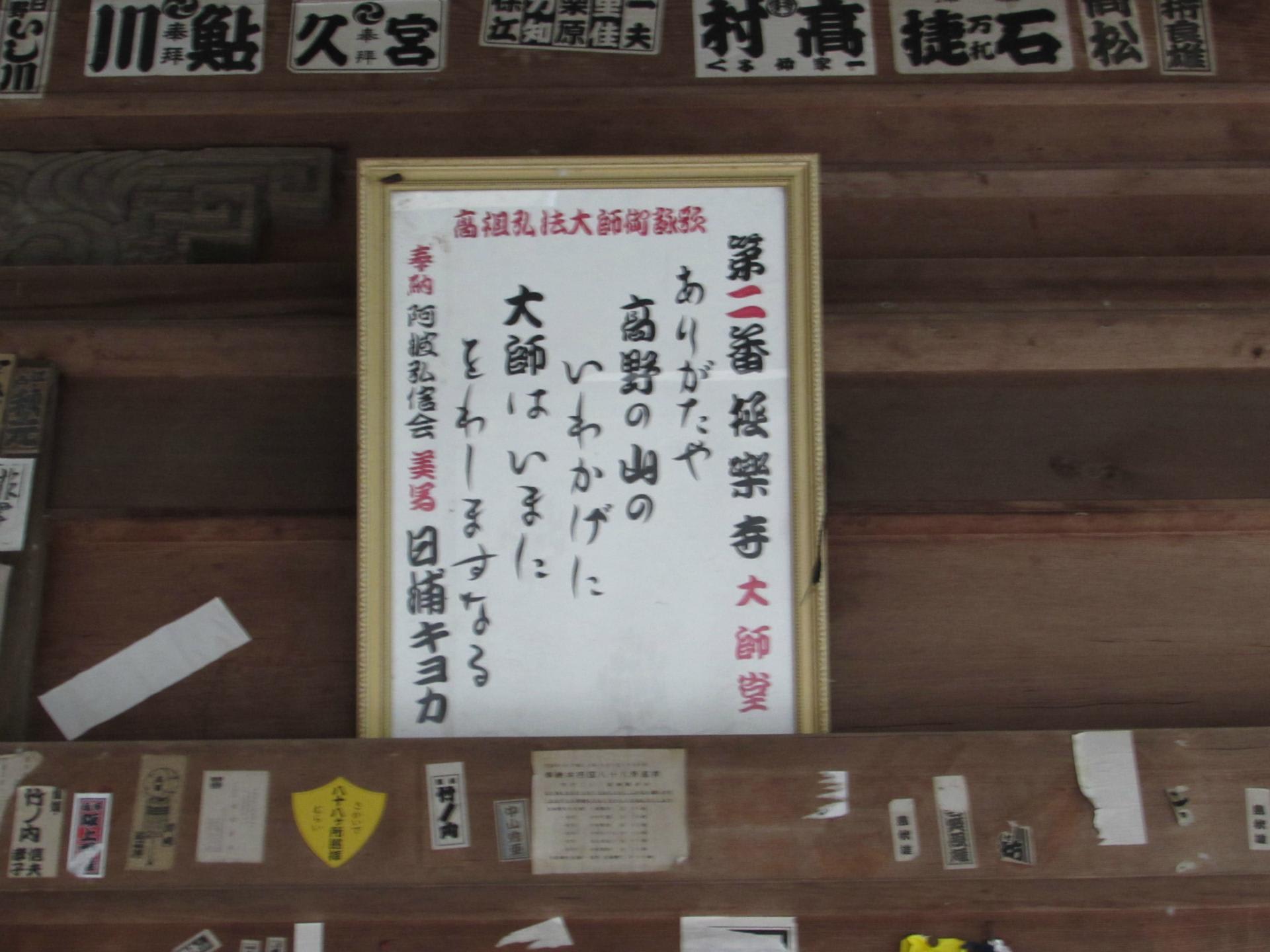2015年9月6日、お参りしました。美馬市脇町を後にして徳島道で徳島に戻りました。
曹洞宗の寺院で、山号は瑞麟山です。
寺伝によれば、寺の歴史は白雉元年(650年)に関東地方よりたどり着いた尼僧が、この地に庵を構えたことに始まると伝えられています。
徳島県徳島市丈六町丈領32
map
境内図

中老生駒家墓碑

鐘楼


中門



戒壇石

三門(重要文化財)
「この門は室町時代末期の16世紀に建立された。徳島県下最古且つ優美で県を代表する建築文化財である。この門の形は、和様・唐様折衷の重層、間口が三間で三か所とも出入りするので三間三戸の門と呼ぶ。柱は丸く上部が細い粽柱で下に礎盤を置く。二階の窓は火燈窓である。それらを唐様と呼ぶ。垂木が多いことなどは和様である。」





僧堂

本堂(重要文化財)
説明書
「寛永6年(1629)蜂須賀蓬庵が娘辰(美濃国加納城主松平忠光夫人)の供養のため、方丈を再建寄進したものである。」






徳雲院(徳島県指定文化財)
説明書
「細川持隆が寄進した瑠璃殿を子の真之が、永禄6年に改築して持隆の法名の徳雲院と改称した。現在の堂宇は、寛永19年(1642)に再建されたものです。」




鐘楼



経蔵(重要文化財)
説明書
「室町末期の永禄11年(1568)細川真之が修行僧が座禅の修行をする僧堂を寄進建立した。江戸中期の享保12年(1727)奥行を1間縮小して二間後ろに移築し、経蔵に改めた。納められた一切経は明国で1616年に出版された径山版大蔵経で、徳島市指定文化財となっている。」


遍照庵観音

観音堂(重要文化財)
説明書
「室町末期の永禄10年(1567年)、細川真之により建立された。現存する建物は江戸時代初期の慶安元年(1648年)と昭和32年(1957年)に解体修理された。」



曹洞宗の寺院で、山号は瑞麟山です。
寺伝によれば、寺の歴史は白雉元年(650年)に関東地方よりたどり着いた尼僧が、この地に庵を構えたことに始まると伝えられています。
徳島県徳島市丈六町丈領32
map
境内図

中老生駒家墓碑

鐘楼


中門



戒壇石

三門(重要文化財)
「この門は室町時代末期の16世紀に建立された。徳島県下最古且つ優美で県を代表する建築文化財である。この門の形は、和様・唐様折衷の重層、間口が三間で三か所とも出入りするので三間三戸の門と呼ぶ。柱は丸く上部が細い粽柱で下に礎盤を置く。二階の窓は火燈窓である。それらを唐様と呼ぶ。垂木が多いことなどは和様である。」





僧堂

本堂(重要文化財)
説明書
「寛永6年(1629)蜂須賀蓬庵が娘辰(美濃国加納城主松平忠光夫人)の供養のため、方丈を再建寄進したものである。」






徳雲院(徳島県指定文化財)
説明書
「細川持隆が寄進した瑠璃殿を子の真之が、永禄6年に改築して持隆の法名の徳雲院と改称した。現在の堂宇は、寛永19年(1642)に再建されたものです。」




鐘楼



経蔵(重要文化財)
説明書
「室町末期の永禄11年(1568)細川真之が修行僧が座禅の修行をする僧堂を寄進建立した。江戸中期の享保12年(1727)奥行を1間縮小して二間後ろに移築し、経蔵に改めた。納められた一切経は明国で1616年に出版された径山版大蔵経で、徳島市指定文化財となっている。」


遍照庵観音

観音堂(重要文化財)
説明書
「室町末期の永禄10年(1567年)、細川真之により建立された。現存する建物は江戸時代初期の慶安元年(1648年)と昭和32年(1957年)に解体修理された。」