2016.7.11(月)曇り
「地震なまず」武者金吉著 1995年12月第1刷発行 明石書店 府立図書館借本
なんとも奇妙なタイトルなのだが、他の本で「地震はなまずが地中で動くとされていたが、その昔はなまずではなく地震の虫とされていた」という文を読んで、これは読んでみたいと思ったのである。鎌倉時代の暦に地震虫が載っているという。見ると地図の周囲をウロコのある虫が取り囲んでいて、その顔はどうも龍のような感じである。地震なまずが登場するのが17世紀、この500年の間にどうして地震虫が地震なまずになったかまったく見当が付かないと著者は書いている。
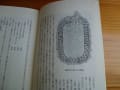
鎌倉時代には地震はなまずではなく地震虫だった。
なまずに限らず地震と動物たちの異常行動、地震や津波の際の怪光、発光など、地震を予知する人の話、古語に地震を表す言葉がないなどおもしろい話が満載である。ところが本書は1957年に発行されたものを再版したものであり、当時は地震についての研究は今日とは雲泥の差があり、機器にしても理論にしても初歩的なものばかりで相当のご苦労があったことがうかがえる。しかし著者が偏見や迷信のなかで、実に科学的に物事を見ようとしていることがわかる一冊である。また著者は日本の歴史的な地震のオーソリティで「増訂大日本地震史料」全4巻を著しておられ機会があれば読んでみたいと思う。
「東京と大地震」というタイトルの一文があるが、東京に大地震の起こる可能性について、警鐘を鳴らしている。特に東京に住む住民に対してのものだが、今日のように政権の中枢が集中していることを考えるとこれは国民全体の問題であると思う。省庁の地方分散が言われた際に官僚の反発に驚いている。東京を離れることに都落ち、左遷の感があるようだ。国民のことを考えれば、そんな思考には陥らないと思うのだが、、、。電車が止まった、雪が降った、水不足だなどと大騒ぎするくせに、もっと致命的な災害に対してあまりにも無頓着ではないだろうか。限界を超えて集中し、競って高層化している景色を見ているとバベルの塔の愚かしさを垣間見てしまう。
【作業日誌】芝生広場、ドッグランど草刈り、チエンソースターター修理

古い刈り払い機のスターターの紐を再利用する。
【今日のじょん】何をしてるのでしょうか?

暑さのかげんでボーっとしておるのデス、はよ来んかい
















