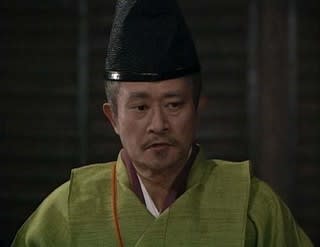その2はこちら。
さて、太平記のドラマ化が困難だとされたのは、皇統がからむからだけではない。登場する人物がとにかく錯綜していて、裏切りが至極当然のこととして行われたりするので、視聴者がはたしてついてこれるのか、ということもあった。
たとえば尊氏の弟の直義にしても、いかにも好漢でありながら、高師直(柄本明)の存在などもあって尊氏と骨肉の争いを演ずることとなる。こんな展開だからこそ、足利尊氏を真田広之は無色な人物として演じなければならず、それは成功していた。
むしろ南朝側の登場人物のほうがストレートな存在としてあった。大楠公(この言葉で学生服を連想したあなたはわたしと同じ世代だ)とまで呼ばれた楠木正成(七回生まれ変わっても朝敵を討つ人ね)や、後醍醐天皇はあくまで理想に殉ずるタイプ。
しかし問題はこの後醍醐天皇。片岡孝夫が演じたこの大看板は、本来の太平記ではさほど評価されていないのに、いわゆる戦前の皇国史観が彼をヒーローに押し上げた。だから彼のために湊川の戦いで殉じた楠木正成が大楠公となったわけだ。
しかしこの大河では、後醍醐は確かに理想に燃えてはいるけれども、実務者としてはいかがなものか、という描き方にもなっていた。楠木正成も、領民に慕われる土豪のような扱い。優秀な戦術家ではあったが。武田鉄矢が意外に渋く演じてよかった。
皇国史観のおかげで大逆賊あつかいだった足利尊氏を、今思えば真田広之以外の誰がやれただろう。実直でありながら、しかしそのルックスからどうしても屈託が感じられる真田にしか背負えない役柄ではなかったでしょうか。
キャストはとんでもなく豪華。新田義貞に萩原健一、でも病気で降板して根津甚八。ほとんど表情を動かさないのに憎々しげな高師直に柄本明、のちに尊氏に刃向かう息子役に筒井道隆、婆娑羅として高名な佐々木道誉に徹底してはまり役だった陣内孝則、美少年として知られた北畠顕家にはなんと後藤久美子!
尊氏の悲恋の相手に宮沢りえ、樋口可南子、本妻に沢口靖子……ああああ豪華である以上にアンサンブルとしても完璧だった。すばらしいドラマ。これぞ大河です。NHKの気合いが感じられる一年でした。
「信長 KING OF ZIPANGU」につづく。