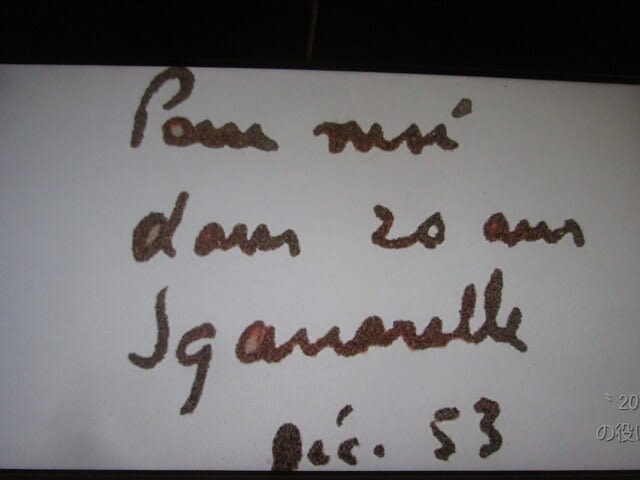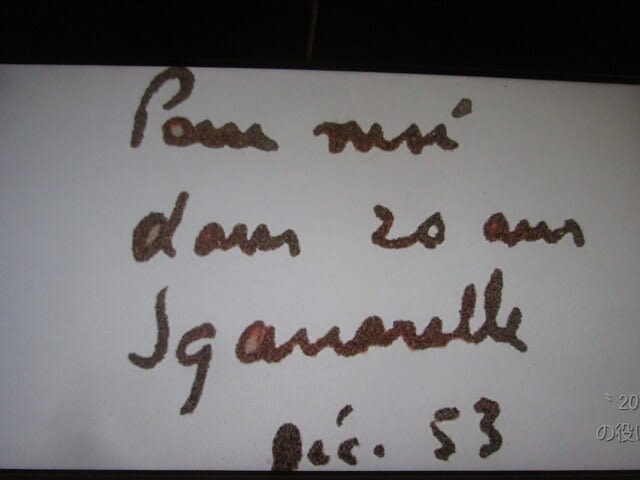
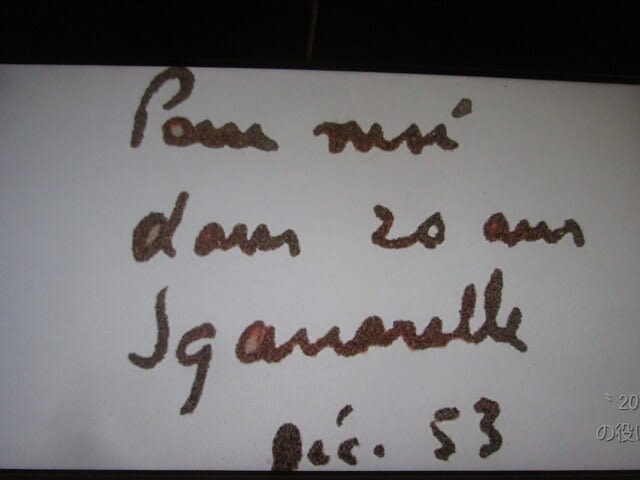 これでも詩かよ第314回&蝶人物見遊山記第382回
これでも詩かよ第314回&蝶人物見遊山記第382回
志郎康さんの誕生日を前にして鈴木一家の映像作品が一堂に会するというので、久し振りに京橋へ行った。
私が今よりずっと若くて元気だった頃、京橋にはワーナーとセゾンの試写会場があったので、よく足を運んだものだ。セゾンの向かいには中央公論社の小ぶりなビルジングが建っていて、「マリ・クレール」という雑誌に、売り出し中の吉本ばななが「TUGUMI」を書いていた。
会場のASK?(アートスペースキムラ)は、私が生涯にたった一度だけ、うどんすきを食べた「美々卯」の隣にある南天子画廊の上階だった。
すでに会場には、野々歩さんと由梨さんと、「浜風文庫」の主宰者、さとう三千魚さんがいた。
朝早く、静岡からやってきたさとうさんは、新幹線で立ちん坊だったといった。
4部に分かれたプログラムの最初は、3名の「はじめての映像作品」だった。
野々歩さんが全裸になって、なにやら懸命に喋っている姿を見ているうちに、私は不思議な感情に襲われ、これは何だ!と、怖れ慄きながら、画面を見つめていた。
映画会が終わった後で、今夜のゲストの萩原朔美さんが語っていたように、黒澤も、小津も、溝口も、名だたる映画監督の誰一人として、裸になって、己の裸を公衆に晒さなかった。
しかし、ここにそれを成した唯一の人間がいるではないか。
まさしくこの瞬間に、鈴木野々歩は偉大なる詩人にして映像作家の父鈴木志郎康を、乗り越えたのではないか、と思うと、なぜか私の目玉から、数滴の涙が零れて落ちたのだった。
プログラムCの村岡由梨の「眼球の人」は、同名の詩作品に導かれるようにして完璧に構成され、ヴィジュアライズされた見事な映像作品である。
大人たちは、少女の私を見る度に、
「無邪気で愛らしい」と言ってくれた。
皆の愛のこもった視線の先にいるのは、いつも私だった。
で、開始され、
先日、眠が16歳の誕生日に種を蒔いたひまわりが花を咲かせた。
芽吹いたひまわりは、私の身長を超え、
あっという間に野々歩さんの身長も超えたのだった。
を、経て、
ひまわりの花を見上げて
自分を恥じないで生きていいのだと、
私は私に言い聞かせる。
ひまわりがこんなにも美しくて切実な花だと、眠が教えてくれた。
と、結ばれる12分間は圧倒的に美しく、村岡由梨という一人の女性、一人の母親、そして一人の芸術家の過ぎ来しゆくかたを、鮮やかに物語っているのだった。
「いまは役者をやっている時が最高のよろこびなんですと」と心情を吐露し、病と闘いながらガハハハと人世を豪快に笑う飛ばす萩原朔美さんとお二人の愉快なトーク「表現者の血を超えて」が終わると、京橋は、妄りにさんざめく土曜の夜の賑わいだった。
「はて東京駅はどっちでしたっけ?」と、きょろきょろしている私を、タクシーで新橋まで送って下さったさとうさんと別れを告げ、鎌倉の滑川沿いの夜道を歩いていた私を待ち構えていたのは、懐かしい合図を符牒のように点滅させるヘイケボタルと、河底を流星のように走る大中小の天然ウナギの群れだった。
ウナジロウ、ウナサブロウ、ウナシロウの死後、絶滅したかに思えた希少な天然ウナギたちが、往時のように自由奔放に踊り狂う姿を目にした私は、これはひょっとすると、かの極私的遊人、鈴木志郎康さんの精霊ではないかと思ったことだった。
京橋の画廊も試写室も無くなりて同じ顔したビルのみ聳ゆ 蝶人















 西暦2024年皐月蝶人映画劇場 その4
西暦2024年皐月蝶人映画劇場 その4
 歳月はまたたく間に飛びゆけどウクライナ、ガザの戦果てなし 蝶人
歳月はまたたく間に飛びゆけどウクライナ、ガザの戦果てなし 蝶人


 照る日曇る日 第2048回
照る日曇る日 第2048回