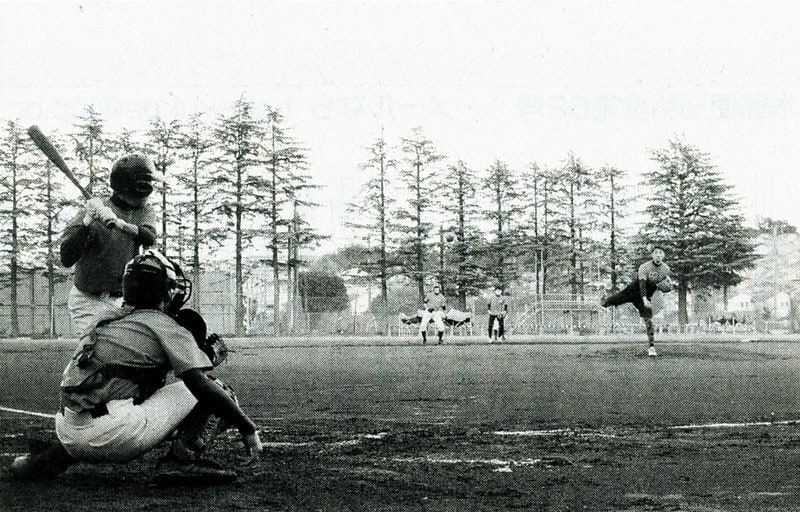変わる高校野球③ 鳥取・米子東高校 研究・発表通じて強豪に
野球に関わる研究を行う同学会で発表するのは、ほとんどが研究者や大学院生です。
しかし、米子東高は2018年から発表しています。先進的な理数教育を実施するために行われる「スーパーサイエンスハイスクール事業」指定校の同校には「課題探究応用」という授業があり、野球部の2年生は野球に関するテーマを扱っています。
けがから着想
今回発表したのは「腰椎分離症の治療期間中に適切なトレーニングをすることでパフォーマンスの向上は可能か」と「前の回の守備内容が次の回の攻撃に影響するのか」をテーマにした2班。
「腰椎―」の班では、投手である山崎壮選手自身が経験した故障から着想。治療期間中に医師や理学療法士からの助言をもとに、柔軟性の向上や体幹強化のメニューを実践し、可動範囲や筋力などの変化を記録していきました。約4カ月の治療から復帰したあと、球速は落ちることなく、1・6キロ向上していました。
「けがの復帰に向けた取り組みの事例が少なかった。ここで実践例を発表することで、同じけがをした選手の役に立てるかもしれないとも思った」(山崎選手)
発表で参加者からの質問に答えた藪本鉄平選手は「楽しかった。この機会に経験できたことは自信になる」と話しました。
「前の回の守備内容―」では、「ピンチのあとにチャンスあり」という言葉が本当なのかという疑問から、全国大会の試合結果151試合分を分析しました。その結果、前の回の守備内容と攻撃の結果には、有意差(偶然に起こったとは判定できない差)はないが、有意傾向が見られました。
瀬川凛太郎選手は「野球でよく言われる“流れ”には選手のメンタルが関わっていると分かった。流れをつくるのは自分たちの気持ちなんだと分かれば、どう行動すべきか考えることができる」と語ります。
徳丸航祐選手は「チャンスをつぶして落ち込むチームは負けていくという感覚があったが、データでもそうだった。これを知ることで試合での心構えが変わると思う」と話しました。
これまでの卒業生の研究テーマは「ゴロを打て、は正しいか」「表情や姿勢、言動はパフォーマンスに影響するか」「動画を使った練習は動作習得に有効か」など。高校野球で当たり前だと思われていた作戦を見直したり、新しい練習方法の効果を検証したり、自由な発想のものばかりです。

野球科学研究会で発表した米子東高の(左から)瀬川、山崎、徳丸、薮本の各選手=11月27日、石川県金沢市・金沢星稜大学
自信になった
県内有数の進学校として知られる同校では部活動のあとに学習塾に通う部員もおり、平日の練習は2時間半もとれません。それでも19年には23年ぶりに春の選抜に出場。同年夏にも甲子園の土を踏むと、21年夏にも県大会で優勝し甲子園へ。県内外の私立高校とも互角以上にたたかえるチームに成長しました。
紙本庸由(かみもと・のぶゆき)監督(40)=同校保健体育教諭=は、野球や指導に関する情報を積極的に集めることで練習の効率を上げてきました。「選手には、目標を設定して達成するための習慣を形成しようと話しています」といい、そのために研究と発表の経験が役立ったといいます。
山崎選手は「目標と課題を明確にして、それに一向けて有効な方法でアブ一ローチすることを学べた」といい、練習メニュー一つにも根拠を考えるようになったと話します。
取り組みが結果につながったことで、選手たちが自信を持つようになりました。
「研究を通じて科学的な考え方を身に付け、野球も強くなった。それによって選手に自信が生まれました。地方でも公立校でも進学校でも、強くなれるんだと。レベルの高い大学で野球を続ける選手や、プロを目指す選手の数が増えています」(紙本監督)
従来の野球指導を見直し、根拠のある練習で野球と向き合う米子東高の姿勢は、全国から注目されています。(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年12月11日付掲載
けがの治療期間中に医師や理学療法士からの助言をもとに、柔軟性の向上や体幹強化のメニューを実践し、可動範囲や筋力などの変化を記録。復帰したあと、球速は落ちることなく、1・6キロ向上。
「ピンチのあとにチャンスあり」という言葉が本当なのかという疑問から、全国大会の試合結果151試合分を分析。「野球でよく言われる“流れ”には選手のメンタルが関わっていると分かった。流れをつくるのは自分たちの気持ちなんだと分かれば、どう行動すべきか考えることができる」
ただただしゃにむに頑張れば良いってもんじゃない。スポーツにも科学がある。
野球に関わる研究を行う同学会で発表するのは、ほとんどが研究者や大学院生です。
しかし、米子東高は2018年から発表しています。先進的な理数教育を実施するために行われる「スーパーサイエンスハイスクール事業」指定校の同校には「課題探究応用」という授業があり、野球部の2年生は野球に関するテーマを扱っています。
けがから着想
今回発表したのは「腰椎分離症の治療期間中に適切なトレーニングをすることでパフォーマンスの向上は可能か」と「前の回の守備内容が次の回の攻撃に影響するのか」をテーマにした2班。
「腰椎―」の班では、投手である山崎壮選手自身が経験した故障から着想。治療期間中に医師や理学療法士からの助言をもとに、柔軟性の向上や体幹強化のメニューを実践し、可動範囲や筋力などの変化を記録していきました。約4カ月の治療から復帰したあと、球速は落ちることなく、1・6キロ向上していました。
「けがの復帰に向けた取り組みの事例が少なかった。ここで実践例を発表することで、同じけがをした選手の役に立てるかもしれないとも思った」(山崎選手)
発表で参加者からの質問に答えた藪本鉄平選手は「楽しかった。この機会に経験できたことは自信になる」と話しました。
「前の回の守備内容―」では、「ピンチのあとにチャンスあり」という言葉が本当なのかという疑問から、全国大会の試合結果151試合分を分析しました。その結果、前の回の守備内容と攻撃の結果には、有意差(偶然に起こったとは判定できない差)はないが、有意傾向が見られました。
瀬川凛太郎選手は「野球でよく言われる“流れ”には選手のメンタルが関わっていると分かった。流れをつくるのは自分たちの気持ちなんだと分かれば、どう行動すべきか考えることができる」と語ります。
徳丸航祐選手は「チャンスをつぶして落ち込むチームは負けていくという感覚があったが、データでもそうだった。これを知ることで試合での心構えが変わると思う」と話しました。
これまでの卒業生の研究テーマは「ゴロを打て、は正しいか」「表情や姿勢、言動はパフォーマンスに影響するか」「動画を使った練習は動作習得に有効か」など。高校野球で当たり前だと思われていた作戦を見直したり、新しい練習方法の効果を検証したり、自由な発想のものばかりです。

野球科学研究会で発表した米子東高の(左から)瀬川、山崎、徳丸、薮本の各選手=11月27日、石川県金沢市・金沢星稜大学
自信になった
県内有数の進学校として知られる同校では部活動のあとに学習塾に通う部員もおり、平日の練習は2時間半もとれません。それでも19年には23年ぶりに春の選抜に出場。同年夏にも甲子園の土を踏むと、21年夏にも県大会で優勝し甲子園へ。県内外の私立高校とも互角以上にたたかえるチームに成長しました。
紙本庸由(かみもと・のぶゆき)監督(40)=同校保健体育教諭=は、野球や指導に関する情報を積極的に集めることで練習の効率を上げてきました。「選手には、目標を設定して達成するための習慣を形成しようと話しています」といい、そのために研究と発表の経験が役立ったといいます。
山崎選手は「目標と課題を明確にして、それに一向けて有効な方法でアブ一ローチすることを学べた」といい、練習メニュー一つにも根拠を考えるようになったと話します。
取り組みが結果につながったことで、選手たちが自信を持つようになりました。
「研究を通じて科学的な考え方を身に付け、野球も強くなった。それによって選手に自信が生まれました。地方でも公立校でも進学校でも、強くなれるんだと。レベルの高い大学で野球を続ける選手や、プロを目指す選手の数が増えています」(紙本監督)
従来の野球指導を見直し、根拠のある練習で野球と向き合う米子東高の姿勢は、全国から注目されています。(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年12月11日付掲載
けがの治療期間中に医師や理学療法士からの助言をもとに、柔軟性の向上や体幹強化のメニューを実践し、可動範囲や筋力などの変化を記録。復帰したあと、球速は落ちることなく、1・6キロ向上。
「ピンチのあとにチャンスあり」という言葉が本当なのかという疑問から、全国大会の試合結果151試合分を分析。「野球でよく言われる“流れ”には選手のメンタルが関わっていると分かった。流れをつくるのは自分たちの気持ちなんだと分かれば、どう行動すべきか考えることができる」
ただただしゃにむに頑張れば良いってもんじゃない。スポーツにも科学がある。