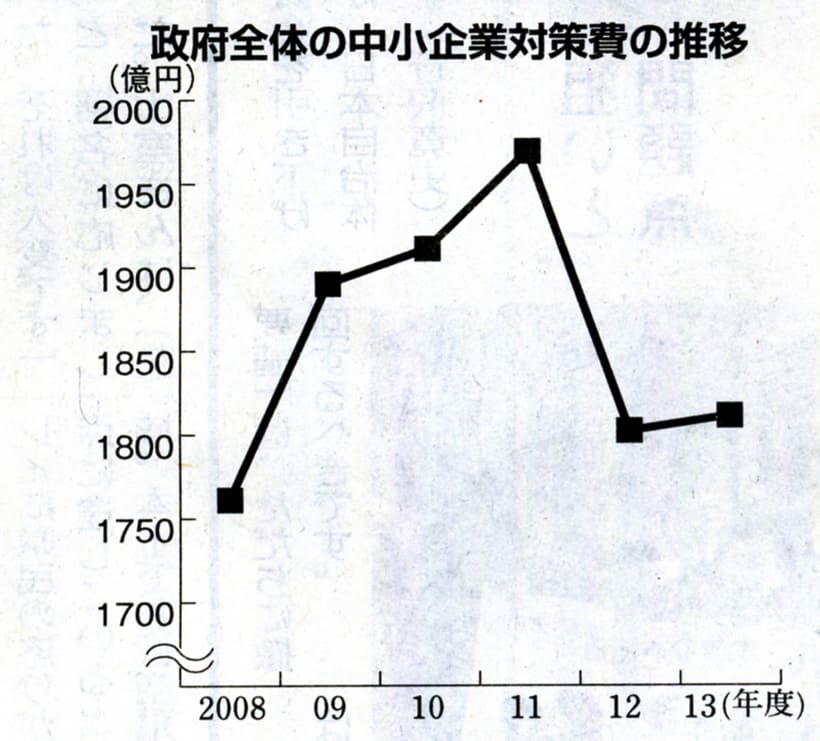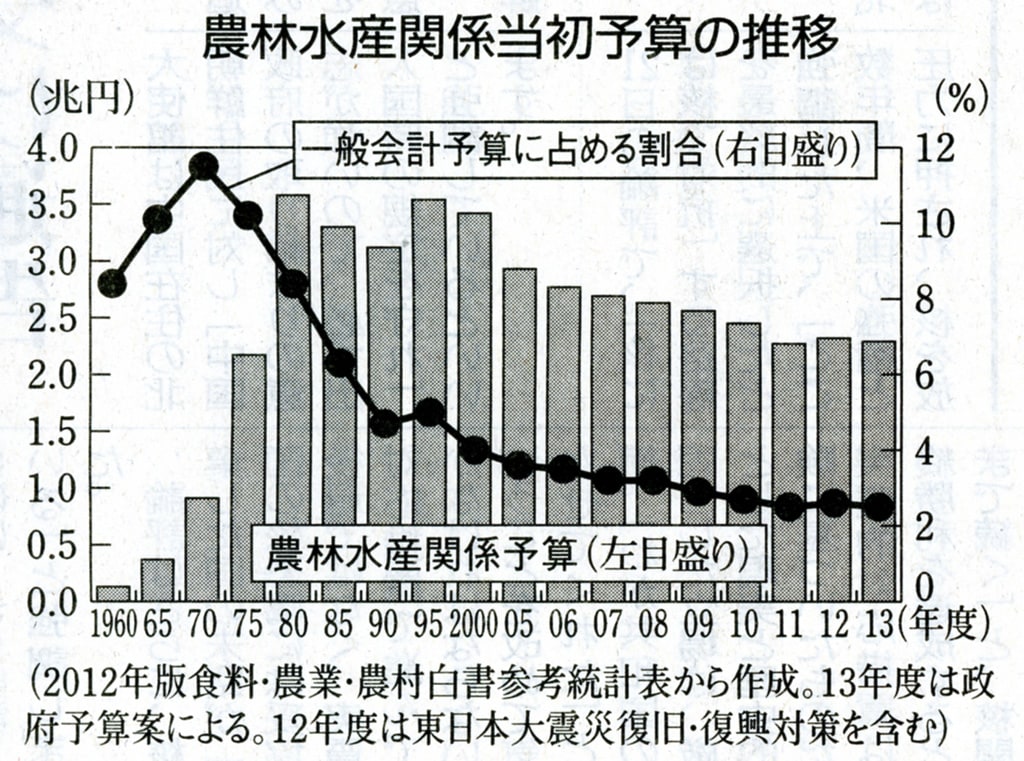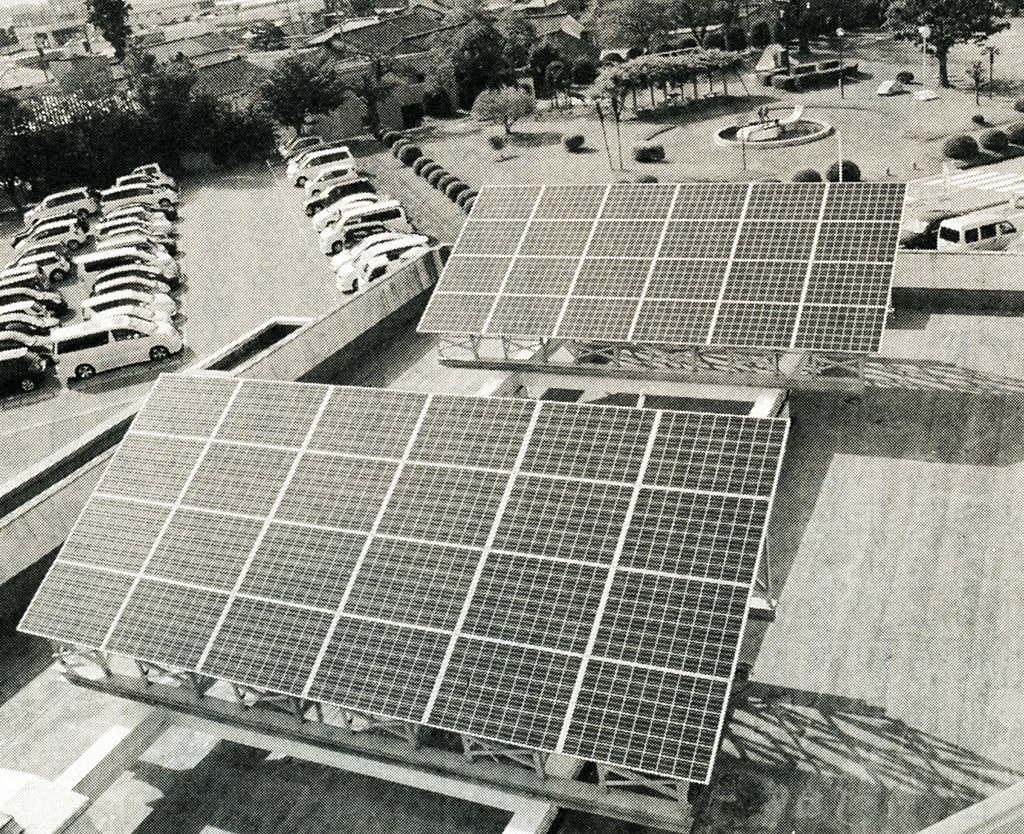2013年度予算案の焦点⑨ 軍事費 F35・水陸両用車も
2013年度の軍事費(防衛関係費、SACO・米軍再編経費含む)予算案は4兆7538億円で、12年度比400億円(0・8%)の増額になります。ただ、これは一般会計のみの数字で、復興特別会計の1252億円を含めると、総額は4兆8789億円。また、13年度予算と一体の「15カ月予算」として組まれた12年度補正予算案には過去最大の2124億円を計上し、政権交代を受け、軍事費は当初予算の見かけ以上に大きく伸びています。
特徴の一つは、13年度に契約し、支払う装備品等購入費の大幅増で、12年度比163億円(65・3%)増の411億円を計上。自衛官実員も8年ぶりに287人の増員を図ります。

国内企業製造の予算が初計上されたF35Aステルス戦闘機(米空軍HPから)
中国対抗根拠に
予算案は、軍事力の長期的な整備指針となる防衛大綱を年内に見直すことを受け、13年度限りの方針で編成。軍拡路線への転換の最大の根拠になっているのが、「南西地域における能力向上」「島嶼(とうしょ)防衛」を掲げての中国への対抗です。
日本最西端の与那国島への陸上自衛隊の国境監視部隊配置に向けて、駐屯地建設のための敷地造成工事費などに62億円を計上。先島諸島における航空自衛隊の展開基盤確保に関する調査研究費などに5000万円も盛り込み、下地島空港(宮古島市、沖縄県管理)の前線基地としての活用も念頭に入れます。
水陸両用車4両25億円を参考品として初購入。米軍垂直離着陸機オスプレイ導入を視野に、開発・運用に関する調査研究費800万円も計上しています。どちらも他国への侵攻能力の向上につながる動きです。また、南西諸島への陸自の展開を視野に、民間輸送船活用の調査研究(6000万円)も進めます。
米軍優先の姿勢
米軍関係では、普天間基地「移設」経費として辺野古新基地を前提にしたキャンプ・シュワブ内の陸上工事費約44億円を盛り込む一方、「思いやり予算」で普天間基地の補修費1億円も初計上。普天間基地固定化も、辺野古新基地建設も沖縄県民が総意で反対しているもので、日本政府の米軍優先姿勢を示しています。
米国主導で開発を進める次期戦闘機F35取得にあたっては、国内企業参画によるエンジン部品・最終組み立てなど製造ライン立ち上げの経費830億円を初計上。F35はイスラエルも導入予定で、国内企業の参画は「武器輸出三原則」の破壊につながります。また、F35は大幅な開発の遅れや値上がりが指摘されており、13年度購入額も2機299億円と、12年度比で1機当たり約50億円も上昇しています。
そのほか、サイバー関連経費には141億円を計上し、「サイバー空間防衛隊」を新設。宇宙・サイバー空間の覇権を重視する米戦略と同調したものです。(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年2月26日付掲載
軍事費こそ、それこそ不要不急の経費だと思うのですが…。まだ未完成の戦闘機・F35なども購入する。強襲上陸部隊が使う水陸両用車も購入するとの事。民主党時代にはまがりなりにも抑えられていた軍事費が、安倍政権になって、一気に増額しています。
本来なら外交努力で解決すべきである尖閣問題。それを軍事で抑え込もうって考えが間違っています。
2013年度の軍事費(防衛関係費、SACO・米軍再編経費含む)予算案は4兆7538億円で、12年度比400億円(0・8%)の増額になります。ただ、これは一般会計のみの数字で、復興特別会計の1252億円を含めると、総額は4兆8789億円。また、13年度予算と一体の「15カ月予算」として組まれた12年度補正予算案には過去最大の2124億円を計上し、政権交代を受け、軍事費は当初予算の見かけ以上に大きく伸びています。
特徴の一つは、13年度に契約し、支払う装備品等購入費の大幅増で、12年度比163億円(65・3%)増の411億円を計上。自衛官実員も8年ぶりに287人の増員を図ります。

国内企業製造の予算が初計上されたF35Aステルス戦闘機(米空軍HPから)
中国対抗根拠に
予算案は、軍事力の長期的な整備指針となる防衛大綱を年内に見直すことを受け、13年度限りの方針で編成。軍拡路線への転換の最大の根拠になっているのが、「南西地域における能力向上」「島嶼(とうしょ)防衛」を掲げての中国への対抗です。
日本最西端の与那国島への陸上自衛隊の国境監視部隊配置に向けて、駐屯地建設のための敷地造成工事費などに62億円を計上。先島諸島における航空自衛隊の展開基盤確保に関する調査研究費などに5000万円も盛り込み、下地島空港(宮古島市、沖縄県管理)の前線基地としての活用も念頭に入れます。
水陸両用車4両25億円を参考品として初購入。米軍垂直離着陸機オスプレイ導入を視野に、開発・運用に関する調査研究費800万円も計上しています。どちらも他国への侵攻能力の向上につながる動きです。また、南西諸島への陸自の展開を視野に、民間輸送船活用の調査研究(6000万円)も進めます。
| 【2013年度軍事費案の主な内容】 | |
| 護衛艦1隻の建造 | 701億円 |
| 潜水艦1隻の建造 | 531億円 |
| P1固定翼哨戒機2機の取得 | 409億円 |
| E767早期警戒管制機の能力向上 | 101億円 |
| 戦闘機(F15、F2)の能力向上 | 122億円 |
| 水陸両用車4両の購入 | 25億円 |
| F35A戦闘機2機の取得 | 299億円 |
| F35A国内企業製造ライン立ち上げ | 830億円 |
| 与那国島へ駐屯地建設のため敷地造成工事等 | 62億円 |
| 米軍関係経費(歳出べ一ス) (内訳:米軍再編経費692億円、SACO経費88億円、「思いやり予算」1860億円) | 2640億円 |
米軍優先の姿勢
米軍関係では、普天間基地「移設」経費として辺野古新基地を前提にしたキャンプ・シュワブ内の陸上工事費約44億円を盛り込む一方、「思いやり予算」で普天間基地の補修費1億円も初計上。普天間基地固定化も、辺野古新基地建設も沖縄県民が総意で反対しているもので、日本政府の米軍優先姿勢を示しています。
米国主導で開発を進める次期戦闘機F35取得にあたっては、国内企業参画によるエンジン部品・最終組み立てなど製造ライン立ち上げの経費830億円を初計上。F35はイスラエルも導入予定で、国内企業の参画は「武器輸出三原則」の破壊につながります。また、F35は大幅な開発の遅れや値上がりが指摘されており、13年度購入額も2機299億円と、12年度比で1機当たり約50億円も上昇しています。
そのほか、サイバー関連経費には141億円を計上し、「サイバー空間防衛隊」を新設。宇宙・サイバー空間の覇権を重視する米戦略と同調したものです。(おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年2月26日付掲載
軍事費こそ、それこそ不要不急の経費だと思うのですが…。まだ未完成の戦闘機・F35なども購入する。強襲上陸部隊が使う水陸両用車も購入するとの事。民主党時代にはまがりなりにも抑えられていた軍事費が、安倍政権になって、一気に増額しています。
本来なら外交努力で解決すべきである尖閣問題。それを軍事で抑え込もうって考えが間違っています。