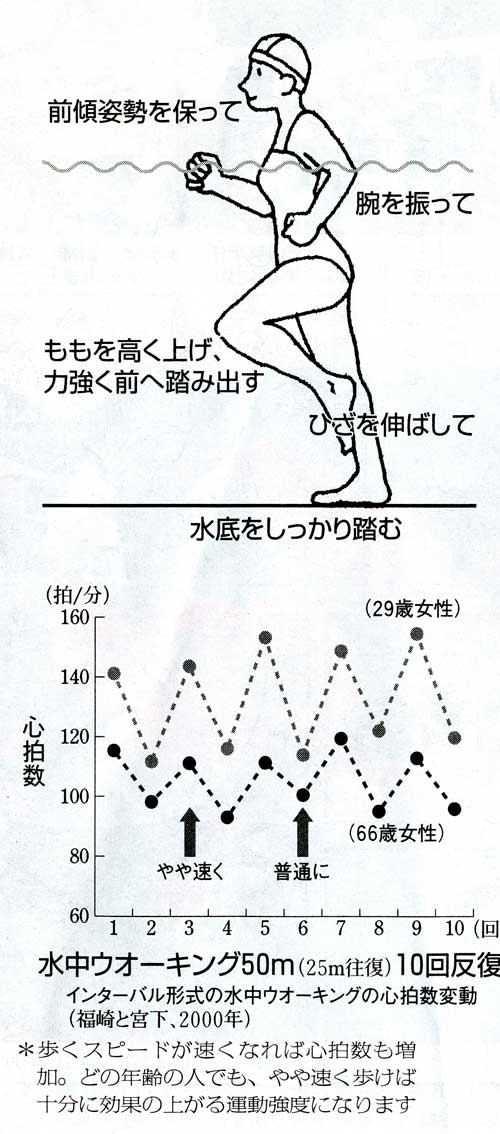ワーキングプア、生きにくい世の中。
「自己責任」が追及され、自ら命を絶つ若者・・・
そういう時、作家でフリーター支援の運動に取り組んでいる雨宮処凛と東京大学大学院教授で「9条の会」事務局長の小森陽一が対談した。
対談集『生きさせる思想』だ!!

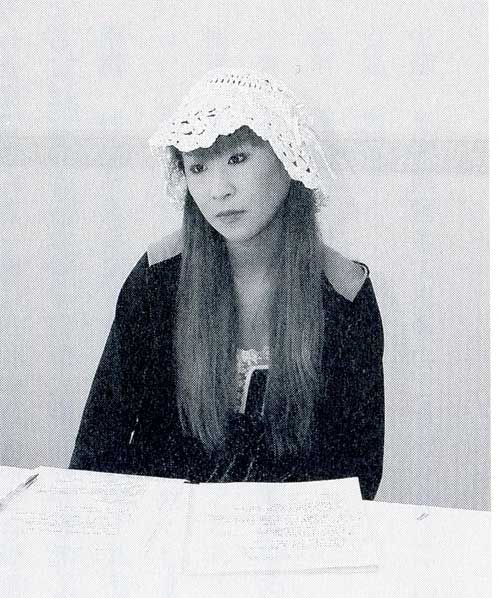
はじめに
雨宮処凛
今まで、いろいろな人と対談させてもらったが、ここまで「必死で考えた」ことはなかった。言い換えれば、ここまで「脳をフル稼動」させたことはなかったのだ。
小森さんは、「それはどうして?」「どういうこと?」と、次々と鋭いところを突っ込んでくる。しかも、今まで私が考えたこともなかったようなことについて。
対談を終えた後は、脳が痺れるような、そんな経験したこともない疲労に襲われた。それほどに、充実した時間だったのだ。
一九七五年生まれの私が初めて社会に対して「目を開かれた」きっかけは、オウム真理教による地下鉄サリン事件(一九九五年)だった。その年に阪神・淡路大震災があり、戦後五〇年があり、世の中は不況と言われて私はフリーターで、これは真剣に社会のことを考えなければ自分自身が生きることもできないぞ、と切実に感じた。
最近、二〇代の人たちと話すと、彼らの「ファーストインパクト」が911テロであり、イラク戦争であることに気づかされる。
この対談を通して、私は、私が「社会に目を開かれる」以前の様々な事件や出来事、政治の流れを具体的に、知った。そしてそれらがいろいろな形で密接に繋がっていることをあらためて確認した。それだけじゃない。自分自身が今まで生き、感じてきた様々な「生きづらさ」までもが、この社会のあり方と複雑に絡まりあって、繋がっていたのだ。
「いい学校、いい大学、いい会社」という唯一絶対の神話のもとに極限まで競争を煽られ、誰もが疑心暗鬼になり、教室に渦巻く「暴力」が私自身に向けられた理由。『自分は必要とされない」とリストカットを繰り返したフリーター時代の苦しみ。右翼団体に入会しながらも、世の中の「右傾化」に疑問を持って脱会した九〇年代後半の私の気持ち。「テロリスト」や北朝鮮という「敵」を見つけて安心したがるように見えた世の中への違和感。イラク戦争と、反戦運動。ネット心中と、「市場原理に勝ち抜けない奴はいらない」という身も蓋もない思想。
そしてやっと始まった、私たちを「生きさせる」ための「労働/生存」運動。
いろんなことが、繋がっていた。それを小森さんは、わかりやすく言葉にして、分析してくれた。
あなたにもぜひ、知ってほしい。知っている。それだけで、この複雑な世の中を生きていくのが、だいぶ楽になるはずだから。

おわりに
小森陽一
この対談の出発点となったのは、二〇〇八年六月九日夕刻の、中央大学での処凛さんとのトーク・ショウだった。その前日、偶然ではあるが、いわゆる「アキバ事件」が発生した。「アキバ事件」をどう考えるかをめぐるやりとりから、現在にいたる貧困社会と格差固定社会が、若者をどこに追い込んでいくのかが明らかになっていった。そして、この日本社会では、私自身がもう死語になっていると思っていた「同志」という二字熟語に、この日処凛さんは新しい生命を吹き込んでくれた。
「同志」とは、こころざしを同じくする者のこと。こころざしとは、自らの心の向うところであり、その心にめざすところであると同時に、相手が自分に寄せてくれる厚意のことでもある。だから、同じ言葉で、自分が相手に対する気持ちを表現するために物を贈ることや、その贈り物のことをも指すこともできる。この対談の後半でテーマとなる「贈与」という行為とも深くかかわる言葉が、こころざしである。
そして、もう一つの意味は、死んだ者への追善供養。まったく予期しなかったことではあるが、二〇〇八年の夏、猛暑の日々に行われていったこの対談では、あまりにも多くの累々としたこの国と世界の死者たちについて語り合うことにもなった。
そのことは、なぜ現在の日本社会は、これほどまでに死の欲動に取り愚かれてしまっているのか、なぜ暴力は常に弱い者に向ってしまうのか、なぜ富と権力と軍事力を専有している者たちへの抵抗の方向ではなく、自分への虐待へと向ってしまうのか、という、いくつもの重要な論点を、この対談にもたらしてくれたと、あらためて思う。
九〇年代から二〇〇〇年代にかけての死者たちについて言葉を交わす中で、次第に処凛さんと私は、生き延びている者としての死者への応答貢任を、共に感じはじめていったのだと思える。その応答責任を果たすためにこそ、題名は「生きさせる思想」で合意したのだ。
処凛さんに「どうして?」「どういうこと?」と問いを発することをとおして、私自身が四半世紀近く、不問に付してきた、いくつもの重要な問題に、正面から向き合い、自らを、思考する現場に引き戻そうとあがいていることがあからさまになっている対談だ。それは処凛さんが「同志」だから可能になった実践だと、今にして確信する。
この対談を同志的に編集してくださった、新日本出版社の角田真己さんに感謝しながら、本書を仲立ちとして、読者であるあなたと、同志となれることを心から願う。
ぜひ、お勧めしたい一冊だ!!
「自己責任」が追及され、自ら命を絶つ若者・・・
そういう時、作家でフリーター支援の運動に取り組んでいる雨宮処凛と東京大学大学院教授で「9条の会」事務局長の小森陽一が対談した。
対談集『生きさせる思想』だ!!

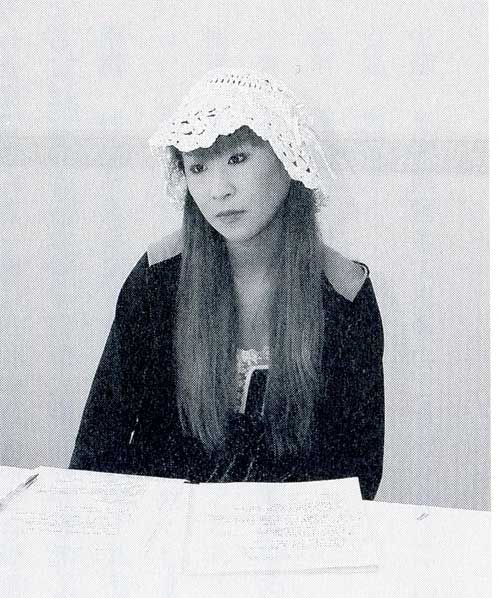
はじめに
雨宮処凛
今まで、いろいろな人と対談させてもらったが、ここまで「必死で考えた」ことはなかった。言い換えれば、ここまで「脳をフル稼動」させたことはなかったのだ。
小森さんは、「それはどうして?」「どういうこと?」と、次々と鋭いところを突っ込んでくる。しかも、今まで私が考えたこともなかったようなことについて。
対談を終えた後は、脳が痺れるような、そんな経験したこともない疲労に襲われた。それほどに、充実した時間だったのだ。
一九七五年生まれの私が初めて社会に対して「目を開かれた」きっかけは、オウム真理教による地下鉄サリン事件(一九九五年)だった。その年に阪神・淡路大震災があり、戦後五〇年があり、世の中は不況と言われて私はフリーターで、これは真剣に社会のことを考えなければ自分自身が生きることもできないぞ、と切実に感じた。
最近、二〇代の人たちと話すと、彼らの「ファーストインパクト」が911テロであり、イラク戦争であることに気づかされる。
この対談を通して、私は、私が「社会に目を開かれる」以前の様々な事件や出来事、政治の流れを具体的に、知った。そしてそれらがいろいろな形で密接に繋がっていることをあらためて確認した。それだけじゃない。自分自身が今まで生き、感じてきた様々な「生きづらさ」までもが、この社会のあり方と複雑に絡まりあって、繋がっていたのだ。
「いい学校、いい大学、いい会社」という唯一絶対の神話のもとに極限まで競争を煽られ、誰もが疑心暗鬼になり、教室に渦巻く「暴力」が私自身に向けられた理由。『自分は必要とされない」とリストカットを繰り返したフリーター時代の苦しみ。右翼団体に入会しながらも、世の中の「右傾化」に疑問を持って脱会した九〇年代後半の私の気持ち。「テロリスト」や北朝鮮という「敵」を見つけて安心したがるように見えた世の中への違和感。イラク戦争と、反戦運動。ネット心中と、「市場原理に勝ち抜けない奴はいらない」という身も蓋もない思想。
そしてやっと始まった、私たちを「生きさせる」ための「労働/生存」運動。
いろんなことが、繋がっていた。それを小森さんは、わかりやすく言葉にして、分析してくれた。
あなたにもぜひ、知ってほしい。知っている。それだけで、この複雑な世の中を生きていくのが、だいぶ楽になるはずだから。

おわりに
小森陽一
この対談の出発点となったのは、二〇〇八年六月九日夕刻の、中央大学での処凛さんとのトーク・ショウだった。その前日、偶然ではあるが、いわゆる「アキバ事件」が発生した。「アキバ事件」をどう考えるかをめぐるやりとりから、現在にいたる貧困社会と格差固定社会が、若者をどこに追い込んでいくのかが明らかになっていった。そして、この日本社会では、私自身がもう死語になっていると思っていた「同志」という二字熟語に、この日処凛さんは新しい生命を吹き込んでくれた。
「同志」とは、こころざしを同じくする者のこと。こころざしとは、自らの心の向うところであり、その心にめざすところであると同時に、相手が自分に寄せてくれる厚意のことでもある。だから、同じ言葉で、自分が相手に対する気持ちを表現するために物を贈ることや、その贈り物のことをも指すこともできる。この対談の後半でテーマとなる「贈与」という行為とも深くかかわる言葉が、こころざしである。
そして、もう一つの意味は、死んだ者への追善供養。まったく予期しなかったことではあるが、二〇〇八年の夏、猛暑の日々に行われていったこの対談では、あまりにも多くの累々としたこの国と世界の死者たちについて語り合うことにもなった。
そのことは、なぜ現在の日本社会は、これほどまでに死の欲動に取り愚かれてしまっているのか、なぜ暴力は常に弱い者に向ってしまうのか、なぜ富と権力と軍事力を専有している者たちへの抵抗の方向ではなく、自分への虐待へと向ってしまうのか、という、いくつもの重要な論点を、この対談にもたらしてくれたと、あらためて思う。
九〇年代から二〇〇〇年代にかけての死者たちについて言葉を交わす中で、次第に処凛さんと私は、生き延びている者としての死者への応答貢任を、共に感じはじめていったのだと思える。その応答責任を果たすためにこそ、題名は「生きさせる思想」で合意したのだ。
処凛さんに「どうして?」「どういうこと?」と問いを発することをとおして、私自身が四半世紀近く、不問に付してきた、いくつもの重要な問題に、正面から向き合い、自らを、思考する現場に引き戻そうとあがいていることがあからさまになっている対談だ。それは処凛さんが「同志」だから可能になった実践だと、今にして確信する。
この対談を同志的に編集してくださった、新日本出版社の角田真己さんに感謝しながら、本書を仲立ちとして、読者であるあなたと、同志となれることを心から願う。
ぜひ、お勧めしたい一冊だ!!