SDGsを力に 持続可能な世界へ③ 実現か失敗か、分かれる道筋
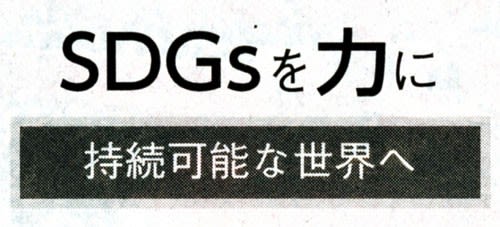
駒沢大学名誉教授 小栗崇資氏
SDGs(持続可能な開発目標)の行く末を案じる声の中には、国連総会に合わせて9月に開かれたSDGsサミットが提起する行動が、既存の処方箋を越えるものではなくSDGsを達成するためのビジョンに欠けるという批判的な意見もあります。今後のSDGsの道筋がどのようなものとなるかは大きな問題です。
「迫る危機、変革の時」と題するサミット報告書では、SDGsの推進を妨害するさまざまな問題が検討されています。例えば、ロシアのウクライナ侵略を筆頭に、国家レベルでの武力紛争が第2次世界大戦後もっとも増加している状況を指摘しています。
また、この二十数年間の年平均の富の増加率を所得階層別に分析し、上位1%の富裕層が世界の富の40%近くを占取していることを明らかにしています。
ウオッシュ分析
SDGs推進の側についても検討しています。特に積極的な取り組みを行っている企業について、誇大な宣伝やSDGsウオッシュ(もどき)の傾向を分析し、そこにもSDGsを阻む障害があると指摘しています。SDGsは山積する問題に直面しています。
SDGsサミットで採択された政治宣言も報告書も、2030年までのSDGs実現の可能性を示し加速化を訴えています。一方でポストSDGsへの道筋についても触れています。
分析によれば、最大限の取り組みをしたとして、17の目標のうち30年までに80%以上達成できるのはわずか三つ、後退が二つです。中程度の取り組みでは、達成可能なものは一つしかなく、後退する目標は七つに上ります。それに対して50年まで期間を延ばした場合、最大限の努力があれば達成可能は10となり、後退はないというのが検討結果です。
ポストSDGsの議論は時期尚早という意見もありますが、私たちは30年をめざしつつ、50年に向けた脱炭素化と一体的なSDGsの取り組みに備えなければなりません。
国連は24年に「未来のためのサミット」を開催予定ですが、そこではポストSDGsについて議論されることでしょう。

傍観者でいいか
報告書では、SDGsの加速的取り組みだけでなく、失敗に終わる道筋の可能性も示しています。図は「持続可能なシステム」が形成された後、加速され安定に至る段階を描くものです。首尾よく進む場合は右肩上がりに上昇する実現のカーブですが、他のカーブは挫折・失敗を示すものとなります。一つ目は古いシステムを守るだけの保守のカーブ、二つ目は途中まで上昇するが反対や抵抗が生まれる反動のカーブ、三つ目は取り組みがされないままシステムが崩壊する破局のカーブです。
SDGsの遅れは運動の側にも原因があります。革新的な運動の中にはSDGsにたいして傍観的・静観的(時には否定的)な姿勢も見られます。SDGsは「世界の変革」
をめざす取り組みですが、私たちは「日本の変革」をめざすものとしてSDGsを運動の柱に据え、積極的・先進的に取り組まねばなりません。
日本がどの道筋のカーブをたどるのかは、私たちの姿勢と力にかかっています。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年10月27日付掲載
SDGsサミット。分析によれば、最大限の取り組みをしたとして、17の目標のうち30年までに80%以上達成できるのはわずか三つ、後退が二つです。中程度の取り組みでは、達成可能なものは一つしかなく、後退する目標は七つに上ります。それに対して50年まで期間を延ばした場合、最大限の努力があれば達成可能は10となり、後退はないというのが検討結果。
ポストSDGsの議論は時期尚早という意見もありますが、私たちは30年をめざしつつ、50年に向けた脱炭素化と一体的なSDGsの取り組みに備えなければなりません。
SDGsの道筋予測カーブ。日本がどの道筋のカーブをたどるのかは、私たちの姿勢と力にかかっています。
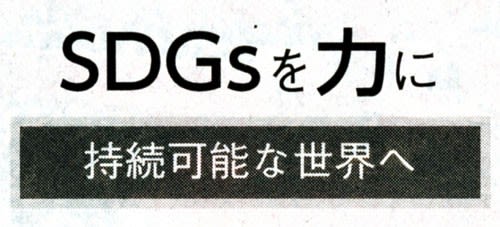
駒沢大学名誉教授 小栗崇資氏
SDGs(持続可能な開発目標)の行く末を案じる声の中には、国連総会に合わせて9月に開かれたSDGsサミットが提起する行動が、既存の処方箋を越えるものではなくSDGsを達成するためのビジョンに欠けるという批判的な意見もあります。今後のSDGsの道筋がどのようなものとなるかは大きな問題です。
「迫る危機、変革の時」と題するサミット報告書では、SDGsの推進を妨害するさまざまな問題が検討されています。例えば、ロシアのウクライナ侵略を筆頭に、国家レベルでの武力紛争が第2次世界大戦後もっとも増加している状況を指摘しています。
また、この二十数年間の年平均の富の増加率を所得階層別に分析し、上位1%の富裕層が世界の富の40%近くを占取していることを明らかにしています。
ウオッシュ分析
SDGs推進の側についても検討しています。特に積極的な取り組みを行っている企業について、誇大な宣伝やSDGsウオッシュ(もどき)の傾向を分析し、そこにもSDGsを阻む障害があると指摘しています。SDGsは山積する問題に直面しています。
SDGsサミットで採択された政治宣言も報告書も、2030年までのSDGs実現の可能性を示し加速化を訴えています。一方でポストSDGsへの道筋についても触れています。
分析によれば、最大限の取り組みをしたとして、17の目標のうち30年までに80%以上達成できるのはわずか三つ、後退が二つです。中程度の取り組みでは、達成可能なものは一つしかなく、後退する目標は七つに上ります。それに対して50年まで期間を延ばした場合、最大限の努力があれば達成可能は10となり、後退はないというのが検討結果です。
ポストSDGsの議論は時期尚早という意見もありますが、私たちは30年をめざしつつ、50年に向けた脱炭素化と一体的なSDGsの取り組みに備えなければなりません。
国連は24年に「未来のためのサミット」を開催予定ですが、そこではポストSDGsについて議論されることでしょう。

傍観者でいいか
報告書では、SDGsの加速的取り組みだけでなく、失敗に終わる道筋の可能性も示しています。図は「持続可能なシステム」が形成された後、加速され安定に至る段階を描くものです。首尾よく進む場合は右肩上がりに上昇する実現のカーブですが、他のカーブは挫折・失敗を示すものとなります。一つ目は古いシステムを守るだけの保守のカーブ、二つ目は途中まで上昇するが反対や抵抗が生まれる反動のカーブ、三つ目は取り組みがされないままシステムが崩壊する破局のカーブです。
SDGsの遅れは運動の側にも原因があります。革新的な運動の中にはSDGsにたいして傍観的・静観的(時には否定的)な姿勢も見られます。SDGsは「世界の変革」
をめざす取り組みですが、私たちは「日本の変革」をめざすものとしてSDGsを運動の柱に据え、積極的・先進的に取り組まねばなりません。
日本がどの道筋のカーブをたどるのかは、私たちの姿勢と力にかかっています。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2023年10月27日付掲載
SDGsサミット。分析によれば、最大限の取り組みをしたとして、17の目標のうち30年までに80%以上達成できるのはわずか三つ、後退が二つです。中程度の取り組みでは、達成可能なものは一つしかなく、後退する目標は七つに上ります。それに対して50年まで期間を延ばした場合、最大限の努力があれば達成可能は10となり、後退はないというのが検討結果。
ポストSDGsの議論は時期尚早という意見もありますが、私たちは30年をめざしつつ、50年に向けた脱炭素化と一体的なSDGsの取り組みに備えなければなりません。
SDGsの道筋予測カーブ。日本がどの道筋のカーブをたどるのかは、私たちの姿勢と力にかかっています。













