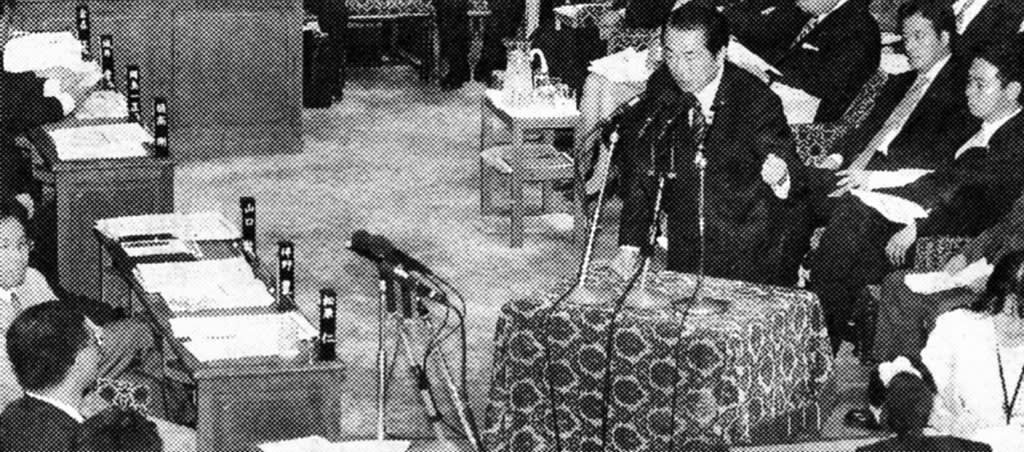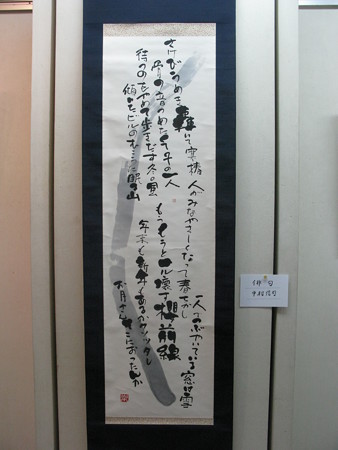「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
消費税増税と自民党型政治⑤ 財務省も認めた穴埋め 「これまでの税制改革で、直間比率自体を具体的にこういうふうに設定して、それに向かって税制改革をやったということはあまりないわけでありまして、所得税や法人税を中心に減税をして、その代わりに消費税を入れさせていただいたということであろうかと思います」 萬歳章JA全中会長との懇談に臨む米倉弘昌日本経団連会長(中央)=2011年11月9日、東京都千代田区 民主党の公約 経団連「困る」 民主党は、法人税減税の穴埋めとして、研究開発税制を削減してあてるってことはできなかったのですね。財界にとっては、税金を減らしてもらった分を別のところから取られるってことは許されないのでしょう。
消費税増税と自民党型政治④ 勢いづかせた10%発言 「自民党が提案している(税率)10%という数字を一つの参考とさせていただきたい」。2010年6月17日、菅直人首相(当時)は参院選挙の公約発表の記者会見で消費税増税に関し、このように明言しました。 谷垣禎一自民党総裁の質問に答える菅直人首相=2010年8月、衆院予算委員会 参院選で惨敗 要求4日後に 自民党との違いを出して政権交代した民主党は、財界からの働きかけで、いとも簡単に変わってしまいます。
消費税増税と自民党型政治③ 下手に出つつ政界工作 2009年10月27日、午後1時から第4回税制調査会が開かれました。霞が関の合同庁舎第4号館11階の共用第1特別会議室。関係団体からのヒアリングが行われ、そこには経団連評議員会副議長の大橋光夫昭和電工会長(当時)の姿がありました。 呼びかけに応じて署名する女性=10月24日、東京・巣鴨駅前 国民審判の力 巻き返し戦略 「コンクリートから人へ」のキャッチフレーズで政権についた民主党ですが、2010年には財界からの攻勢に早くも負けてしまっているのですね。
総選挙 日本共産党 近畿ブロックの兵庫県堀内事務所の事務所びらきがありました! 来月4日公示、16日投票の総選挙。日本共産党の比例近畿ブロック兵庫県堀内事務所の事務所びらきが11月27日午後6時から、神戸市兵庫区新開地商店街の日本共産党兵庫県委員会事務所前で行われました。 01_岡県委員長の訴え posted by
(C)きんちゃん
開会にあたって、岡県委員長から総選挙をめぐる情勢や日本共産党の躍進の役割について訴えがありました。 01_候補者たち_01 posted by
(C)きんちゃん
事務所びらきに集まった、小選挙区の候補者たちです。 01_候補者たち_02 posted by
(C)きんちゃん
左から6区の吉見秋彦さん、7区の浜本のぶよしさん、8区の庄本えつ子さんです。 01_候補者たち_03 posted by
(C)きんちゃん
左から、10区の井沢たかのりさん、11区の白髪みどりさん、12区の竹内のりあきさんです。 02_労働者後援会 posted by
(C)きんちゃん
最初に労働者後援会から訴えがありました。非正規労働者が増えて、労働者の賃金が減っている。ますますデフレ不況が進みます。大企業の260兆円もある内部留保を労働者の賃金や下請け企業に還元することで、日本の経済が活性化する。それを提案している日本共産党の躍進を! 02_新婦人内後援会_01 posted by
(C)きんちゃん
新婦人内後援会からの訴えです。 02_新婦人内後援会_02 posted by
(C)きんちゃん
02_業者後援会 posted by
(C)きんちゃん
業者後援会からの訴えです。今でも消費税を納付するのに身銭を切っている。10%にアップしたやっていけないのが現実。日本共産党の躍進で消費税増税ストップを。 02_青年後援会 posted by
(C)きんちゃん
青年後援会からの訴え。 青年は、「消費税をアップして欲しくないけど国の財政は大丈夫のだろうか?」、「あぶない原発はストップして欲しいけど電力は大丈夫のだろうか?」などと模索しています。それに応えるのは日本共産党ですと訴えました。 02_農業団体 posted by
(C)きんちゃん
農業団体からの訴え。TPP反対貫く日本共産党に期待します。 02_医療後援会 posted by
(C)きんちゃん
医療後援会からも訴え。国民皆保険を守るためにも日本共産党の躍進を。 05_事務所びらき参加者 posted by
(C)きんちゃん
事務所開きに参加された方々です。 04_堀内候補訴え_01 posted by
(C)きんちゃん
最後に、堀内照文・比例近畿ブロック予定候補から訴えがありました。 04_堀内候補訴え_03 posted by
(C)きんちゃん
特に圧巻だったのが、オスプレイ配備に関わり、兵庫県北部の米軍の低空飛行訓練ルート「ブラウンロート」について防衛省と交渉した事です。 04_堀内候補訴え_04 posted by
(C)きんちゃん
06_頑張るぞ_01 posted by
(C)きんちゃん
最後に、候補者全員で「頑張るぞ」と決意を表明しました。 06_頑張るぞ_02 posted by
(C)きんちゃん
花束もいただき、激励をうけました。短期決戦ですが、頑張ります。
日本共産党兵庫県文化後援会の作品展があった 11月21日(水)から11月26日(月)の会期で、高速神戸駅西改札口前のギャラリーメトロで、日本共産党兵庫県文化後援会の作品展が開催されていた。 文化後援会 高速神戸駅西口 ギャラリーメトロ posted by
(C)きんちゃん
文化後援会 出品作品_01 posted by
(C)きんちゃん
文化後援会 出品作品_02 posted by
(C)きんちゃん
文化後援会 出品作品_03 posted by
(C)きんちゃん
石原さんの新党「太陽の党」は、登ったと思ったらすぐに沈んでしまいました。 文化後援会 出品作品_04 posted by
(C)きんちゃん
文化後援会 出品作品_05 posted by
(C)きんちゃん
出帆する海王丸を見送る人たち・・・ 文化後援会 出品作品_06 posted by
(C)きんちゃん
阪神淡路大震災関連の写真もありました。 文化後援会 出品作品_07 posted by
(C)きんちゃん
文化後援会 出品作品_08 posted by
(C)きんちゃん
文化後援会 出品作品_09 posted by
(C)きんちゃん
文化後援会 出品作品_10 posted by
(C)きんちゃん
第4回作品展 日本共産党兵庫県文化後援会 部門 氏名 作品名 絵画 宇山英樹 鎖場を歩く 見守る岩場 黎明 池田 勇 静物 樫村道子 翔 楽 高橋富枝 離宮公園 畑中暁来雄 虚数美人 安武ひろ子 希望 山口克己 深まる秋 ディフェンパキア マンガ 段 重喜 石原さん「太陽の季節」は終わりました 先生走る「師走」 書 中村信司 宮本百合子 寒椿 蝉しぐれ 俳句 西澤 愼 喜 謹賀新年 秋の林 洛北閑吟 俳句 渡辺冬木 花のいのち 写真 金子賢治 うえ山の棚田 林の中を歩く 川井正弘 アンタイトルド 1 アンタイトルド 2 段野太一 海王丸出帆 1 海王丸出帆 2 堤 隆二 公園 家 紅葉 長井良弘 捕らえたよ 空からの眺めもいいよ
会場が場所的に人通りが少なくて、お客さんが少なかったです。残念ですね。