オックスファム報告書を読む③ 大企業がつくる不平等
政治経済研究所主任研究員 合田寛さん
オックスファムの報告書は、大企業の力の増大、独占力の強化が不平等拡大の最大の原因になっていると指摘します。
富裕者へ富移転
第1に、労働者から富裕者への富の移転です。この数十年は世界の多くの労働者にとって過酷な時代でした。巨大企業は強大な力と、グローバル・バリュー・チェーン(複数国に配置された生産工程や流通過程の連鎖)を通じて労働者に低賃金、権利の抑圧、ひどい労働条件を押しつけました。その一方、大企業と企業の重役には空前の利益と途方もない報酬を、株主には莫大(ばくだい)な富をもたらしました。
さらに強大な力を持った大企業は、潤沢な資金を使った献金やロビー活動で政府に働きかけ、企業に都合のよい労働政策のために影響力を行使してきました。その結果、政府は賃上げや労働条件の改善に取り組むのではなく、大企業やそのオーナーを豊かにする政策を選んだのです。
報告書によれば、2022年7月から23年6月までの1年間に大企業が生み出した100ドルの利益につき82ドルが、配当と自社株の買い戻しの形で株主の手に入ったというのです。株式保有は富裕層に偏っているので、この巨額の支払いは富裕層を不釣り合いにより豊かにしました。
第2に、税制に対する“戦争”に勝利したことです。大企業やそのオーナーは豊かな資金力を背景にして、自らに対する税を軽減するために、活発なロビー活動を行ってきました。80年代以降の税制改革によって、法人税の税率は半減し、配当や株式売却益に対する所得税も大幅に軽減されました。またタックスヘイブンの悪用によって、大企業は表面税率よりも相当低い実効税率(しばしばゼロ税率)の適用を受けています。
その結果生じた財源不足を賄うために、各国では付加価値税(消費税)を中心とする逆進性の強い税体系がつくられてきました。
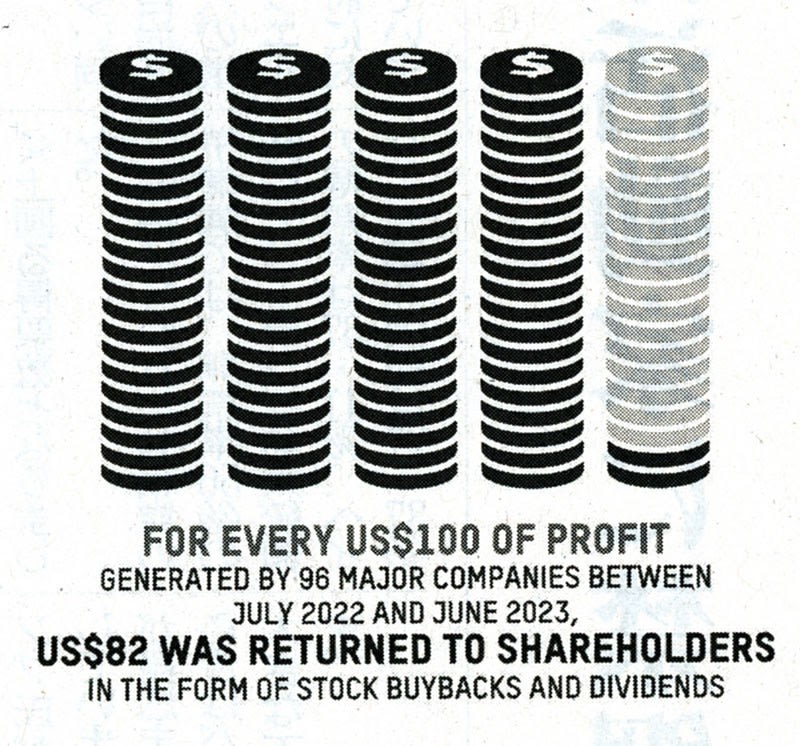
2022年7月から23年6月の間に大手企業96社が生みだす利益100ドルごとに82ドルが自社株買いと配当の形で株主に還元された(オックスファム報告書から)
公共財を民営化
第3に、民営化による公共サービスの収益事業化です。強大な企業の力は公的部門を「商品化」し、利益獲得の新たな分野にしてきました。富裕者は十分な資力を使って、高価な公共サービスを受けることができますが、一般の人々にとっては、生活に欠かせないサービスの享受を制限され、排除されることになります。
民営化には、従来型の国有企業売却のほか、近年、官民連携方式(PPPs=パブリック・プライベート・パートナーシップ)、あるいは外部委託方式が多く採用されています。
対象となる分野は、教育、医療、介護、水道、道路など、幅広い公共サービスに及んでいます。多くの民営化は財政コストの削減にはつながらず、企業に巨額の利益を保証する一方、財政上のリスクは納税者が負担するしくみとなっています。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年2月29日付掲載
第1に、労働者から富裕者への富の移転。報告書によれば、2022年7月から23年6月までの1年間に大企業が生み出した100ドルの利益につき82ドルが、配当と自社株の買い戻しの形で株主の手に入った。
第2に、税制に対する“戦争”に勝利したことです。大企業やそのオーナーは豊かな資金力を背景にして、自らに対する税を軽減するために、活発なロビー活動。
第3に、民営化による公共サービスの収益事業化。
対象となる分野は、教育、医療、介護、水道、道路など、幅広い公共サービスに及んでいます。
政治経済研究所主任研究員 合田寛さん
オックスファムの報告書は、大企業の力の増大、独占力の強化が不平等拡大の最大の原因になっていると指摘します。
富裕者へ富移転
第1に、労働者から富裕者への富の移転です。この数十年は世界の多くの労働者にとって過酷な時代でした。巨大企業は強大な力と、グローバル・バリュー・チェーン(複数国に配置された生産工程や流通過程の連鎖)を通じて労働者に低賃金、権利の抑圧、ひどい労働条件を押しつけました。その一方、大企業と企業の重役には空前の利益と途方もない報酬を、株主には莫大(ばくだい)な富をもたらしました。
さらに強大な力を持った大企業は、潤沢な資金を使った献金やロビー活動で政府に働きかけ、企業に都合のよい労働政策のために影響力を行使してきました。その結果、政府は賃上げや労働条件の改善に取り組むのではなく、大企業やそのオーナーを豊かにする政策を選んだのです。
報告書によれば、2022年7月から23年6月までの1年間に大企業が生み出した100ドルの利益につき82ドルが、配当と自社株の買い戻しの形で株主の手に入ったというのです。株式保有は富裕層に偏っているので、この巨額の支払いは富裕層を不釣り合いにより豊かにしました。
第2に、税制に対する“戦争”に勝利したことです。大企業やそのオーナーは豊かな資金力を背景にして、自らに対する税を軽減するために、活発なロビー活動を行ってきました。80年代以降の税制改革によって、法人税の税率は半減し、配当や株式売却益に対する所得税も大幅に軽減されました。またタックスヘイブンの悪用によって、大企業は表面税率よりも相当低い実効税率(しばしばゼロ税率)の適用を受けています。
その結果生じた財源不足を賄うために、各国では付加価値税(消費税)を中心とする逆進性の強い税体系がつくられてきました。
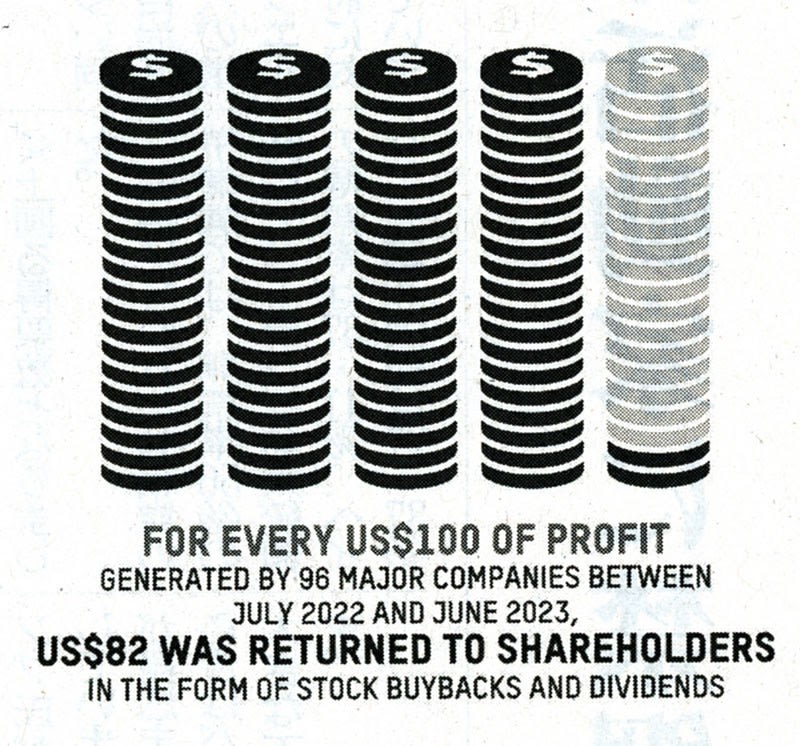
2022年7月から23年6月の間に大手企業96社が生みだす利益100ドルごとに82ドルが自社株買いと配当の形で株主に還元された(オックスファム報告書から)
公共財を民営化
第3に、民営化による公共サービスの収益事業化です。強大な企業の力は公的部門を「商品化」し、利益獲得の新たな分野にしてきました。富裕者は十分な資力を使って、高価な公共サービスを受けることができますが、一般の人々にとっては、生活に欠かせないサービスの享受を制限され、排除されることになります。
民営化には、従来型の国有企業売却のほか、近年、官民連携方式(PPPs=パブリック・プライベート・パートナーシップ)、あるいは外部委託方式が多く採用されています。
対象となる分野は、教育、医療、介護、水道、道路など、幅広い公共サービスに及んでいます。多くの民営化は財政コストの削減にはつながらず、企業に巨額の利益を保証する一方、財政上のリスクは納税者が負担するしくみとなっています。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年2月29日付掲載
第1に、労働者から富裕者への富の移転。報告書によれば、2022年7月から23年6月までの1年間に大企業が生み出した100ドルの利益につき82ドルが、配当と自社株の買い戻しの形で株主の手に入った。
第2に、税制に対する“戦争”に勝利したことです。大企業やそのオーナーは豊かな資金力を背景にして、自らに対する税を軽減するために、活発なロビー活動。
第3に、民営化による公共サービスの収益事業化。
対象となる分野は、教育、医療、介護、水道、道路など、幅広い公共サービスに及んでいます。











