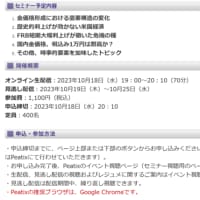注目のFOMC(連邦公開市場委員会)は、政策金利(FF金利の誘導目標)の引き上げ幅は0.75%と予想に沿ったものとなった。これで政策金利の水準は3.00~3.25%となった。
記者会見でのパウエル連邦準備理事会(FRB)議長の発言内容も、過去1カ月以内の複数の会合や講演での発言と大きな違いは見られなかった。ややサプライズともいえたのは、今回新たに発表されたFOMCメンバー19名全員による経済・金利の見通しだった。昨日ここに、ターミナルレート(今回の利上げサイクルでFRBが目指す終着金利水準)がどうなるかが注目としたが、内容が予想以上にタカ派だった。 発表された新たな金利見通しでは、高インフレの抑制に向けて政策金利を2022年末までに4.25~4.50%に引き上げ、23年には4.50~4.75%でピークに達するとの見方が示された。この見通しに沿うと、一般的には11月の会合で0.75%、12月は0.5%の利上げが想定され、事前の予想よりタカ派的と言えるもの。
さらに景気見通しについては、2022年の成長率見通しは0.2%と6月会合での1.7%から大幅に下方修正された。すでに米国経済は1~3月期、4~6月期とマイナス成長となっているが、それを踏まえると0.2%はマイナス成長の可能性もあるということになる。ここまでの急激な利上げと、さらにこの先も続ける見通しの引き締め策により、景気後退の可能性をFRB自体が予測値で示したことになる。ちなみに2023年の見通しも1.7%から1.2%に下方修正され潜在成長率を下回る見通しとなっている。
これもそもそも低成長をFRBは狙っている。失速せずに低く飛び続けるイメージだが、おそらく突風が吹いたり、どこかに不具合があったり、失速もあり得ることを今回記者会見でパウエル議長自身も認めている。ソフトランディングは難しくなったと。
パウエル議長は、FRBは40年ぶり高水準にあるインフレ率を引き下げるという「強い決意」を持っており、「仕事が完了するまでやり続ける」と述べた。この言葉は、少なくとも3回は繰り返されているもの。
過去1カ月間の議長はじめFRB関係者の発言内容から、金融引き締めの「加速、上振れ、長期化」見通しが市場に織り込まれつつあったが、今回のメンバー予測は、それらを可視化したもので、その内容は市場予想を上回るタカ派的なものとなった。 この可視化というのがポイントで、FRBが目指す終着金利が見えたことで、ここまで特に他国との金利差を手掛かりとしたドル買いは、早晩、振り切れるのではと思っていた。そこで昨日は、FOMC明けにNY金は動きやすくなるとした。
もちろん相場にはモメンタムが働いており、行き過ぎるところまでいかないと戻ってこない。流れの転換点が生まれたのではと注目している。
ドル円は今夕に日銀(判断は財務省)がドル売り介入に入ったが、カネ余りと参加者のすそ野が広がっているので、かつてのような効果があるか見ものだ。それでも、相場が熟れていれば効果はあるだろう。今回FOMCのタイミングを狙ったのは、FRBが当面の手の内を明かした後なので、意味はあると思う。
先日、S&P500種が3800割れがあるかに注目していると書いたが、記憶している人は少ないのだろう。割れが定着してくると、株式市場はきつくなると思う。日本株を含めて。