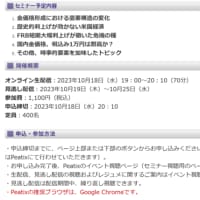最近、保有する米国債の評価が上がった(質への逃避で米国債に買いが集まり価格が上昇、米国債の利回りは低下)ことから外貨準備が初めて1兆ドルの大台に乗ったと報じられた我らの日本国。その外貨準備のドル建てで見たブレイク・イーブンのポイントが101円なんだそうな。オイオイオイ、国家が為替で評価損を抱えたというのが、この一両日のドル円相場ということになる。もともと借金で投じたドル投資ゆえ、反対側の支払利息も考えねばならぬし、これは由々しきこと。まぁ、調達金利は低いのだけれど。
一昨日の12日にファニーメイ債が値崩れを起こしていると書いたが、本日の日経朝刊一面特別解説記事(?)にもそれが触れられていた。一応米国政府の保証ではないことになっているが、機関の生い立ちから米国政府の保証付きとされ、だから「準保証」などというまだるっこい表現しかできない(国債に準じる)機関債(エージェンシー債)にあたるのが、この債券。一般には住宅債券などと呼ばれる。クリントン政権時代に、イケイケドンドンで米国は財政収支が改善し黒字化したことから最後は30年国債の発行を取り止めるということをやった。その際に、国債が品薄になり、各国政府が米国債の代替としてこのエージェンシー債を買うということがあったし、ある意味でそれが定着して今に続いている。何のことはない、日本を抜いて今や世界最大の外貨準備保有国である中国は、米国債以外にこの住宅債券を大量に抱えている当事者なのだった(当方の知る範囲では)。今回、だからと言って中国が何かモノを申しているわけではないが、中銀(FRB)が大慌てで担保として米国債との交換を認めることで価格を支えるという動きに出たのは、広い範囲では政治的な配慮もあったのかもしれない(金融的混乱の連鎖を断つのが第一義的な背景)。
いずれにしても、そんなことを外野が思ってしまうほど、ひっ迫しているのが現在の米国金融情勢ということ。今朝のニュースで注意を要するのは、格付けで知られるS&P(スタンダード&プァーズ)が、「大手金融機関はサブプライム関連の評価損の大半を計上済み」とのレポートを出したと伝えられていることだろう。事実であれば、完全解決には時間は掛かるものの大手では峠を越えつつあるといえ、注目に値するニュースとなる。それが株式市場では、センチメント(市場心理)の大幅な改善につながると読み換えられ、上昇材料となる(ハズなんだけど)。
一昨日の12日にファニーメイ債が値崩れを起こしていると書いたが、本日の日経朝刊一面特別解説記事(?)にもそれが触れられていた。一応米国政府の保証ではないことになっているが、機関の生い立ちから米国政府の保証付きとされ、だから「準保証」などというまだるっこい表現しかできない(国債に準じる)機関債(エージェンシー債)にあたるのが、この債券。一般には住宅債券などと呼ばれる。クリントン政権時代に、イケイケドンドンで米国は財政収支が改善し黒字化したことから最後は30年国債の発行を取り止めるということをやった。その際に、国債が品薄になり、各国政府が米国債の代替としてこのエージェンシー債を買うということがあったし、ある意味でそれが定着して今に続いている。何のことはない、日本を抜いて今や世界最大の外貨準備保有国である中国は、米国債以外にこの住宅債券を大量に抱えている当事者なのだった(当方の知る範囲では)。今回、だからと言って中国が何かモノを申しているわけではないが、中銀(FRB)が大慌てで担保として米国債との交換を認めることで価格を支えるという動きに出たのは、広い範囲では政治的な配慮もあったのかもしれない(金融的混乱の連鎖を断つのが第一義的な背景)。
いずれにしても、そんなことを外野が思ってしまうほど、ひっ迫しているのが現在の米国金融情勢ということ。今朝のニュースで注意を要するのは、格付けで知られるS&P(スタンダード&プァーズ)が、「大手金融機関はサブプライム関連の評価損の大半を計上済み」とのレポートを出したと伝えられていることだろう。事実であれば、完全解決には時間は掛かるものの大手では峠を越えつつあるといえ、注目に値するニュースとなる。それが株式市場では、センチメント(市場心理)の大幅な改善につながると読み換えられ、上昇材料となる(ハズなんだけど)。