


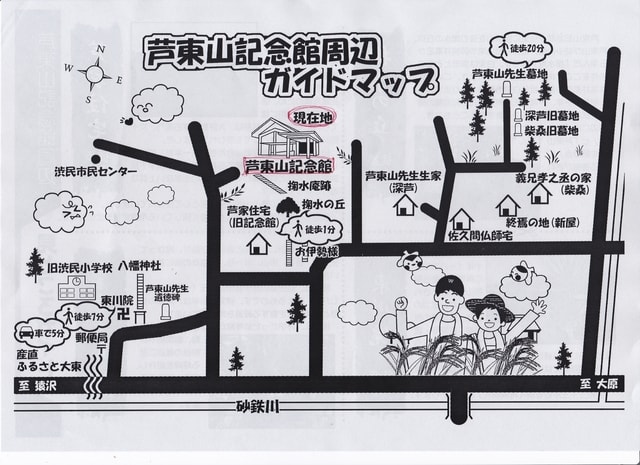
2018年2月14日(水)、芦東山記念館(一関市大東町渋民字伊勢堂71-17)主催の「平成29年度芦東山記念館
々長講座・第5回”高山彦九郎が見た天明の飢饉直後の東北地方(その2)」(13:00~15:00時)が実施され
たので、妻と共に聴きに行ってきました。



前回[2017年12月22日(金)]の続きで、「高山彦九郎が見た天明飢饉直後の東北地方(その2)」。
高山彦九郎は、寛政2年(1790)6月7日、44歳のときに蝦夷地踏査のため江戸より津軽へ向け旅をし
ます。9月3日、津軽半島宇鉄(うてつ)に着きましたが、…渡航を断念しています。帰路東北各地の
飢饉の様子を記録した「北行日記」を残しています。
講演は、天明3年(1783)の大飢饉から7年後の寛政2年(1790)戌6月7日の記述からでした。
配布されたA4判7ページのプリントのうち9月20日の条(現在の10月末)で、時間切れとなってしま
いました。
高山彦九郎が見た天明飢饉直後の東北地方(その2):『北行日記』
寛政二年(1790)戌六月七日、丙辰。快晴。夜七つ時に江戸橋木更津川岸発船す。永代橋佃島を左に見て
東海道大森沖に及んで夜明けたり。日の海上に湧き出で玉ふ赤ふしてほうづきの如し。(省略)
八日、午の下刻に木更津に船着す。(以下省略)
(九月)十一日条(省略)五ノ戸より八ノ戸迄東に来る。此所南部内蔵頭殿二万石の城下也。[(注)盛岡藩の南部利直公には三人の男子(重直、重信、直房)があり、重直が継いでいたが、世継ぎを決めないままに寛文4年(1664)9月に病死した。しかし、前以て幕府に世継ぎのことを願い出ていたため、藩は断絶されず、重信に8万石が与えられて盛岡藩が存続した。直房にも2万石が与えられて分藩「八戸藩」が成立した。]城は町の北に有り平城也。(省略)仁井田入口、三十余の圯橋(いきょう、土橋)を渡る。宿らん事を乞へども許さず。十日市ばに及んで暮に及び雨降り来る。又タ宿らん事を欲するとも宿らしめず。暫くにして晴れて月朗らか也。仰ぎてよめる。
宿るへき里もあらねは独り行く旅の空なる月のさやけき 正之[彦九郎の本名]とぞ。牛追おひに追ひ付ひて語りつ田代村に至る。(省略)庄屋作之丞所に宿す。(省略)
田代村元家百二十件、今は三十二軒、往還には三軒のみ、是れも元は七軒有しとぞ。飢年に餓死道路にたをれて八ノ戸馬の往来も止み、八ノ戸にて穴を四つ掘りて投込みけるに、余りてつつみの内へ水葬したる多ふし。野草より雉犬牛馬を喰ひ尽し人を食ふに至る。人食ひたるものは生るもの百か一もあらす、千万の内一人生るのみ。八ノ戸二万石の下計りにても六万人餓死す。餓孚のもの共の骨、今に道路に有りとぞ。空宅の内を見れば人の骨のみ也とぞ。侯(八戸藩主)も窮して一人に付き米壱升計りの手当有りける。家中(家来・武士)にも死する人ありけらし。侯の命にて月に六日、壱人に付き米壱升三百三十二文に売られしとぞ。今夜も畳(ムシロ)を着て寝ぬ。[盛岡藩や八戸藩の農民は土間住居を強いられワラやモミガラを敷いた上で寝たという。]
十四日条(省略)[大野村郊外の]兵右衛門所に宿す。八ノ戸湊神明神主村上主計(かずえ)、久慈の浜杉本藤馬と同宿す。あるじ酒を出たして饗応す。(省略)飢年には野草禽獣も食ひ尽し、親は子が死せば食はん事を思ひ、子も又た親の肉を食んとす。侯の制禁を出たされて人の肉を食ふものをは捕へて刎首す。され共、人の肉にて命をつなぎ今に在命のものもありと聞ゆ。(以下省略)
https://ayiva.sakura.ne.jp/misc/tiraura/html/x20-book-hokkounikki1790.shtml [book:高山彦九郎(1790)「北行日記」にみる天明飢饉」2014.10]
http://burari2161.fc2web.com/takayamahikokurou.htm[高山彦九郎]
http://www5.wind.ne.jp/hikokuro/ [太田市立高山彦九郎記念館(公式ページ)]









