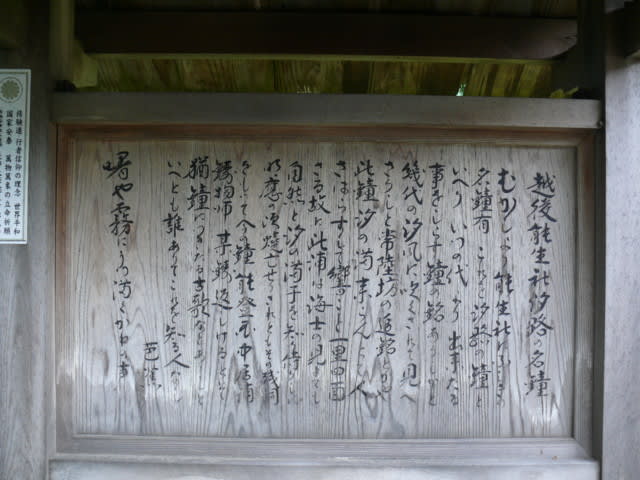2013年9月28日(土)、一関市博物館(一関市厳美町字沖野々215番地)が、9/21(土)~11/17(日)の日程で開催中の第20回企画展「地を量る~描かれた国、町、村」の関連行事の講演会「伊能忠敬(いのうただたか)測量隊について」が開催されたので聞きに行ってきました。

講師は 星埜由尚(ほしの・よしひさ)氏:(公社)日本測量協会副会長で、初めて実測による日本地図を作成したとされている伊能忠敬(いのう・ただたか)の生涯について話をされました。テレビドラマなどで幾らかは知っていましたが、知らなかったことも幾つか知ることができました。(13:30~15:30時の約2時間)

p>講 師 星埜由尚(ほしのよしひさ)氏
プロフィール ・(社)日本測量協会副会長
・伊能忠敬研究会 代表理事
・NPO法人 地域マップ研究所 理事長
・(社)日本山岳会茨城支部長
・元国土交通省国土地理院 院長

(上)伊能忠敬画像:伊能忠敬記念館(千葉県香取市佐原イ1722-1)蔵
http://www.city.katori.lg.jp/museum/ [伊能忠敬記念館]
伊能忠敬は、寛政12年(1800)から文化13年(1816)まで、足かけ17年をかけて全国を測量し「大日本沿海輿地(よち)全図を完成させ、歴史上はじめて国土の正確な姿を明らかにしたことでよく知られていますが、初めから「日本全国の地図を作ること」が目的だったわけではなく、地球の大きさを知りたいということが動機だったといわれているそうです。
50歳の時に、家督を譲り隠居すると、翌年江戸に出て、幕府の天文方・高橋至時(よしとき=高橋景保<かげやす>の父)に師事し、測量・天文観測などを修めました。暦学上の解析のために、江戸で天体観測を行い、緯度(子午線)一度の距離を求め地球の大きさを計算したところ、高橋至時に ”基準とする距離が短か過ぎ不正確である、江戸と蝦夷ほどの距離を元にすれば推測も可能であろう” と一笑に付され、この事が後年測量の旅に出るきっかけの一つになったと言われています。[一関市博物館発行「一関市博物館第20回企画展 地を量る~描かれた国、町、村」(平成25年9月21日発行)より] 因みに、後に28里2分と算出した数値は、ラランデ暦書の数値とほぼ一致したそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E6%9A%A6%E6%9B%B8 [ラランデ暦書(Wikipedia)]
ここに出てきた「高橋景保(かげやす)」は、伊能忠敬の日本全国測量を監督し、文政4年(1821)に「大日本沿海輿地(よち)地図」を完成させましたが、文政11年(1828)にシーボルト事件により牢獄に捕えられ、翌年獄中で病死しています。

寛政12年(1800)閏4月19日、56歳の時に第1次測量を開始し、大図と小図を幕府に提出したところ実績が認められ、文化12年(1815)に至る10次(第5次からは幕府直轄事業)の全国測量が行われたのです。
上の表や下右の辞令書(「測量試蝦夷地差遺に付」とある)を見ても明らかなように、第1次から第4次までは、忠敬の個人事業(幕府の補助)と比べると、第5次以降では測量作業担当等の人数が大部増えていますが、これは、初めの頃幕府はあまり期待していなかったことの現われなのではないかと述べていました。

伊能忠敬の日本地図測量方法は、2点間の距離と方角を測ることを積み重ねる「導線法」を基本とし、数か所から目標物の方位を測る「交会法」によって誤差を修正するという、当時すでに用いられていた手法によるものでした。測器と測量方法の工夫により精度を高めたのだそうです。
因みに富士山は遠くからでも良く見えたようで、富士山から引かれた直線は100本以上あるとのことでした。
緯度の測定のため北極星をはじめとする恒星の高度の観測を可能な限り毎日行い、経度の測定のために月食や日食などの観測を行っています。


シーボルト事件は、長崎出島のオランダ商館の医師であったシーボルトが、帰国する船に多数の禁制の品を積載していたことが発覚したことに端を発するもので、この中に高橋が渡した伊能忠敬の「日本沿海輿地全図」も含まれていました。シーボルトはこの図を持ち帰ることに成功し、帰国後ヨーロッパで出版し、精度の高い日本図が西洋に紹介されました。[一関市博物館発行「一関市博物館第20回企画展・地を量る~描かれた国、町、村」より]
(下)アドリアン・レランド作の日本地図 1715年(正徳5)31.5×45.8㎝(一関市博物館蔵)

伊能忠敬は、文政元年(1818)、地図の完成を見ることなく死去しますが、その死は公表されず、門弟らによって地図の作成が進められ、最終版伊能図「大日本沿海輿地全図」が、文政4年(1821)に幕府に提出されました。大図(縮尺36,000分の1)214枚、中図(216,000分の1)8枚、小図(432,000分の1)3枚の地図は膨大なものでした。
伊能小図を元にした「官板実測日本図」が、幕府開成所から慶応3年(1867)に刊行されますが、この時はまだ高価なもので一般には普及しませんでした。明治4年(1881)以降には、一般市民を対象とした伊能図を源流とする日本全図が次々と刊行されます。伊能図が、政府が実施した三角測量による帝国図と全て置き換えられ、姿を消したのは昭和4年(1929)のことでした。[一関市博物館発行「一関市博物館第20回企画展・地を量る~描かれた国、町、村」より]
伊能の実測図は、他に代わるもののない精度をもって、100年もの間用いられたのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%83%BD%E5%BF%A0%E6%95%AC [伊能忠敬(Wikipedia)]