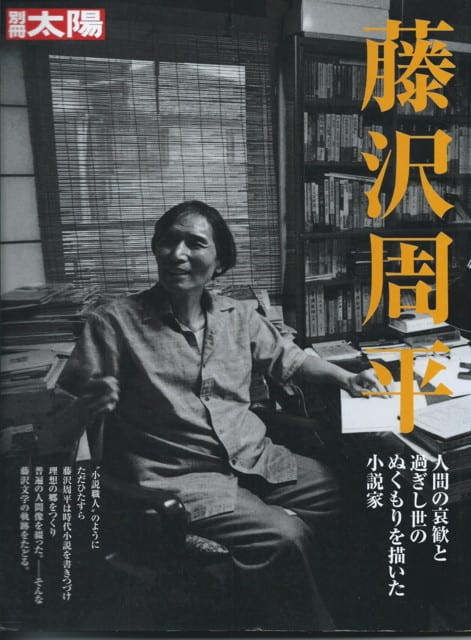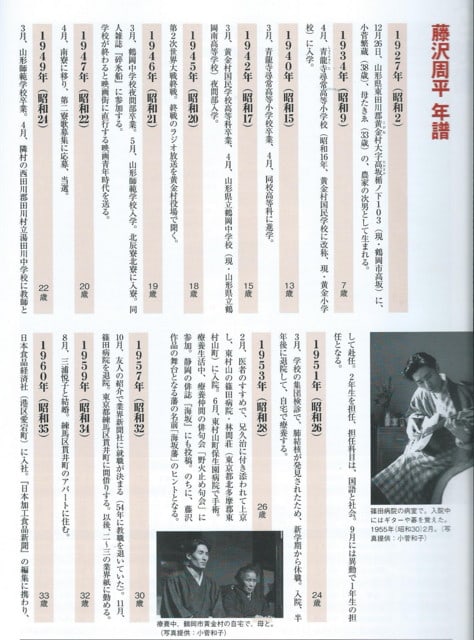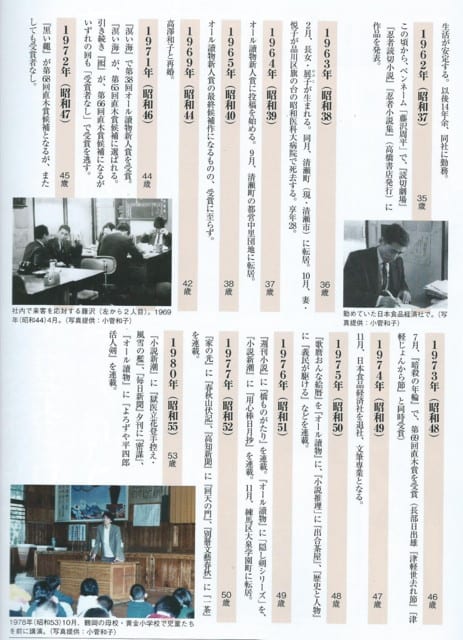2014年8月7日(木)、東山公民館(館長・鈴木勝市)、田河津公民館、松川公民館、石と賢治のミュージアム:主催の「昭和26年度 東山ふるさと歴史講座」の第4回(一関市の研修バスと徒歩による現地学習)”歩いてみよう今泉街道~長坂宿から摺沢宿へ”(9:00~15:00時)が行われました。講師は東山支所教育文化課 畠山篤雄氏。
現在の「今泉街道」である県道19号(一関大東)線沿いにある産直「季節館」からバスに乗って、県道105号線を猿沢(館合、赤柴)方面へ移動しました。旧・今泉街道は、下の地図の赤い線のように通っていたそうで、現在の「県道(今泉街道)」を離れて館合・赤柴の方へ大きくカーブして里前に続いています。

?桃の木洞入口の道標、?愛宕神社祭り場の古碑、?五輪坂上の古碑群、?千葉院の古碑、?館合道路傍の碑、?西館址、?東館址、?龍沢山善龍寺、?火産霊(ほむすび)神社。

(上と下)里前地区にある東山町の上水道施設(揚水ポンプ室、浄化槽)。右手に伸びている道が昭和40年代まで使われていた旧・県道19号(一関大東)線で、その時代はここが「今泉街道」であった。左側に急カーブして大船渡線の下を潜って現在の県道に合流している。


(上と下)このトンネル状のものが大船渡線と旧・県道が重なる所で、当時はバスもこの道を走っていました。

(上)このトンネル状の所から100mほど進んだ所で現在の県道19号線(現在「今泉街道」と呼ばれている道)に合流する。
東山町の上水道施設付近の山際に朱色の花を咲かせたフシグロセンノウ(節黒仙翁)が生えていました。



フシグロセンノウ(節黒仙翁) ナデシコ科 センノウ属 Lychnis miqueliana
山地の林の中などやや日蔭に生える日本固有の多年草。茎は直立し高さ40~90㎝になる。節は太くて、紫黒色を帯びる。葉は対生し、卵形または楕円状披針形で長さ4~15cm、幅2.5~4cmあり、先端は尖る。脈上と縁に毛がある。
和名は、やや肥大した茎の節の部分が紫赤色を帯びて黒っぽいので「節黒」の名がある。別名:フシグロ。山草の美花の1つとして、古くからセンノウ(仙翁)花とともに茶花、生け花に用いられた。センノウは中国原産の同属の植物で、観賞用に栽培されている。
7~10月、茎の先に直径5cmほどの大きな朱紅色の花を数輪平開する。稀に白花もある。花弁は5枚、下部は狭まって爪状になり、舷部(げんぶ)は倒心形で全縁。 各花弁ごとに2個の小りん片がある。
種小名は、シーボルトP.F.von Sieboldと同じ頃、日本からオランダのライデン大学に多くの植物を集め、植物目録をつくったミケールF.W.Miquelに因む。
分布:本州、四国、九州。[山と渓谷社発行「山渓ポケット図鑑2・夏の花」&同「山渓カラー名鑑・園芸植物」より]
https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=42962033&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:国指定史跡・達谷窟(たっこくのいわや)&フシグロセンノウ 2013年8月17日(土)]