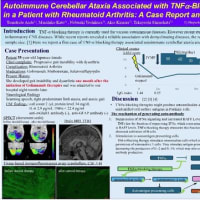テネシー州ナシュビルで開催された国際脳卒中学会2015(ISC2015)に参加した.今年のISC2015のプレナリーセッション(参加者が一同に集まって行われるシンポジウム)は大変盛り上がり,大きな拍手が沸き起こるものとなった.
2年前,ホノルルで開催されたISC 2013で,急性期脳梗塞に対する血管内治療の有効性に関する3つのランダム化試験の結果が報告され,3つの試験のすべてが否定的な結果となり,多くの医師は大変なショックを受けた(「ホノルルショック」と呼ばれた).その後,新しい血管内治療のデヴァイスを用い,背水の陣で行われた4つの試験(昨年発表されたMR CLEAN(※)を含む)の結果が報告され,今回はすべてで有効性を証明できたためである.つまり,Merciや Penumbraといった第一世代のデヴァイスを用いた血管内治療では有効性を示すことが難しかったものの,Solitaire(図上)やTrevoといった第二世代のデヴァイスを用いて有効性を示せたということである(※ミスター・クリーンと読むそうだ).
この4試験の結果について表にまとめた(図下).治療のtime windowは4.5~12時間で,画像検査による症例の選択はCT,CTアンギオ,ASPECTS,虚血中心や側副血行路の評価などが用いられた.発症から再灌流までにかかった時間は241分~290分,主要評価項目の90日後のmRS 0-2(予後良好群)の割合は33%~71%であった.再灌流に伴い生じうる症候性出血については,tPA群と比べると高いものの,その差は大きくはなかった.再灌流までの時間が短いほど効果は大きく,出血は少なかった.血管内手技に伴う合併症も低頻度であった.有効性についてはメタ解析でも確認され,time windowについては6時間までは可能という結果であった.絶対,失敗が許されない臨床試験を,デバイスとデザインを考えて万全の状態で行い,見事,成功したという印象である.学会はほとんどこの話題一色という感じであった.
脳梗塞治療の2大戦略は,再灌流と神経保護である.前者の代表がtPAで,後者は低体温療法やpreconditioning,エダラボンなどが挙げられるが,今回の結果を受けて,再灌流が大きくシフトすることになるものと思われる.患者の立場から考えると血管内治療を行える医師の治療を受けられるかが重要になってくる.シンポジウムの中で,今後,治療を受ける側にとって大事なことを示したスライドがあった.
1)血管内治療を行う医療機関の近所に住むこと
2)そしてあまり遠くに出かけないこと
3)あまりあちこち出かけない血管内治療医を主治医に持つこと
4)国際脳卒中学会でみな医師が出張している時期に,決して脳卒中を起こさないこと
みなの笑いを誘ったが,あながち冗談とは言い切れない時代に入ったという印象を持った.
ISC 2015

2年前,ホノルルで開催されたISC 2013で,急性期脳梗塞に対する血管内治療の有効性に関する3つのランダム化試験の結果が報告され,3つの試験のすべてが否定的な結果となり,多くの医師は大変なショックを受けた(「ホノルルショック」と呼ばれた).その後,新しい血管内治療のデヴァイスを用い,背水の陣で行われた4つの試験(昨年発表されたMR CLEAN(※)を含む)の結果が報告され,今回はすべてで有効性を証明できたためである.つまり,Merciや Penumbraといった第一世代のデヴァイスを用いた血管内治療では有効性を示すことが難しかったものの,Solitaire(図上)やTrevoといった第二世代のデヴァイスを用いて有効性を示せたということである(※ミスター・クリーンと読むそうだ).
この4試験の結果について表にまとめた(図下).治療のtime windowは4.5~12時間で,画像検査による症例の選択はCT,CTアンギオ,ASPECTS,虚血中心や側副血行路の評価などが用いられた.発症から再灌流までにかかった時間は241分~290分,主要評価項目の90日後のmRS 0-2(予後良好群)の割合は33%~71%であった.再灌流に伴い生じうる症候性出血については,tPA群と比べると高いものの,その差は大きくはなかった.再灌流までの時間が短いほど効果は大きく,出血は少なかった.血管内手技に伴う合併症も低頻度であった.有効性についてはメタ解析でも確認され,time windowについては6時間までは可能という結果であった.絶対,失敗が許されない臨床試験を,デバイスとデザインを考えて万全の状態で行い,見事,成功したという印象である.学会はほとんどこの話題一色という感じであった.
脳梗塞治療の2大戦略は,再灌流と神経保護である.前者の代表がtPAで,後者は低体温療法やpreconditioning,エダラボンなどが挙げられるが,今回の結果を受けて,再灌流が大きくシフトすることになるものと思われる.患者の立場から考えると血管内治療を行える医師の治療を受けられるかが重要になってくる.シンポジウムの中で,今後,治療を受ける側にとって大事なことを示したスライドがあった.
1)血管内治療を行う医療機関の近所に住むこと
2)そしてあまり遠くに出かけないこと
3)あまりあちこち出かけない血管内治療医を主治医に持つこと
4)国際脳卒中学会でみな医師が出張している時期に,決して脳卒中を起こさないこと
みなの笑いを誘ったが,あながち冗談とは言い切れない時代に入ったという印象を持った.
ISC 2015