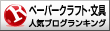朝一番に市役所に用事があるので、早めに行ったら時間が余って
しまった。
30分ほど時間つぶしのため歩いたことのない通りをぶらぶら。
ほー。
河原町二条と寺町二条の間に二本の通りがあるとは知らなかった。
まず、新椹木町通りを丸太町まで歩いてみた。

通りはこんな感じ。


古い醤油屋さんが二軒あった。

町名に木の字が使われていつせいか、材木屋さんも多い。

こんな建物や

通りに飾りつけとかが施してあり、意外と風情も感じさせてくれる。
・・・・・
新烏丸通りは下御霊神社や革堂の裏手にあたるため、裏通りといった
雰囲気がある。

下御霊神社の朽ち果てた蔵。上御霊神社の華やかさに比べると何か
寂しい。

仁丹看板は健在。

どこかで見たような狐?
金閣寺近くの不思議不動院にあったのとおなじような頭が狐、胴体が
タヌキの置物。

鍾馗さんも2階の明り取りのところにちょこんとおられた。

京の町屋らしい細い入口。

白衣を扱う問屋のようなものもあった。

このあたりも町屋を壊し、駐車場となっているところが多い。
こんなアンバランスな景色は見たくない。
・・・・・
敷地なのか公道なのか判らないのが不安だが、路地裏探検をまた
やりたくなってきた。
しまった。
30分ほど時間つぶしのため歩いたことのない通りをぶらぶら。
ほー。
河原町二条と寺町二条の間に二本の通りがあるとは知らなかった。
まず、新椹木町通りを丸太町まで歩いてみた。

通りはこんな感じ。


古い醤油屋さんが二軒あった。

町名に木の字が使われていつせいか、材木屋さんも多い。

こんな建物や

通りに飾りつけとかが施してあり、意外と風情も感じさせてくれる。
・・・・・
新烏丸通りは下御霊神社や革堂の裏手にあたるため、裏通りといった
雰囲気がある。

下御霊神社の朽ち果てた蔵。上御霊神社の華やかさに比べると何か
寂しい。

仁丹看板は健在。

どこかで見たような狐?
金閣寺近くの不思議不動院にあったのとおなじような頭が狐、胴体が
タヌキの置物。

鍾馗さんも2階の明り取りのところにちょこんとおられた。

京の町屋らしい細い入口。

白衣を扱う問屋のようなものもあった。

このあたりも町屋を壊し、駐車場となっているところが多い。
こんなアンバランスな景色は見たくない。
・・・・・
敷地なのか公道なのか判らないのが不安だが、路地裏探検をまた
やりたくなってきた。