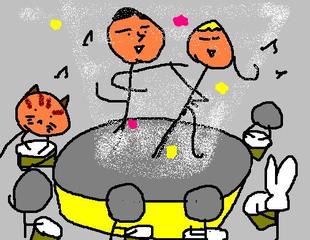例のノーベル賞の人が
奥さんパートナーとテレビにでていて、子どもの成長を横で見ながら研究出来てよかったです、研究が苦しい時には家族が支えになりました、とかなんとか言っていた。はいはい、そうですかい、と思っていたら、あまりにも垂涎の人生に悶絶。
奥さんパートナーは中学生の同級生らしく、大学「教員」であるわたくしなど、不純異姓交際かっ、とつい反応してしまったが、そんなことはなかったようで、順当に整形外科医の修業で「ジャマナカ」とか言われつつ、研究者に転身、二人でドクター取得後結婚(←これ立派)、二人の子どもを天から
取得授かり、ノーベル賞
取得受賞と、すばらしい軌跡が紹介されていた。わたくしの淫らな人生と比べて何という違いであろうか。
わたくし
↓
中学では不純異姓交際どころではない学校の荒れように悩み、音楽を目指すが「ジャマナカ」と人に言われるまでもなく勝手に挫折、順当に大学にも落ち、というわけで芸術家から研究者に転身(自意識では……)、ドクター取得までにかなりの女性に見放され、香川にたどり着き……ノーベル賞受賞(してない)
違いすぎる。
マスゴミの皆さんに言いたいのは……、学者の人生にはいろいろあるということである。離婚したらいきなり頭角を現した学者、ゼミ生と結婚してしまった学者、子どもが引きこもりないし不良になって研究どころではなくなった学者、自由を吹き込んだためか子どもがバイオリン職人なんかを好きになって自転車二人乗りなどして転落人生一直線、あるいは、研究に一生懸命だったので子どもがマザコンやファザコンに(あれ?この作品出でてくるお父さんは学者じゃなかったかな?忘れたわ)、しかもエヴァンゲリオンに乗ったり世界を滅ぼしたりする人達を量産するなど、まあいろいろいる訳である。
研究テーマだっていろいろあるからな、夢の再生医療に役立つから山×教授の研究はいいのかもしれないが、わたくしの業界は、破滅する人間模様になぜ人間は昂奮するのか、という研究で満ちあふれている。
あーちなみに、学者というものは一般的に「小市民や国家はおれを支えて当然」と思っているかもしれない。わたくしはヘタレ学者だから思っていないっ。マッドサイエンティストという言葉があるが、まちがっている。サイエンティストというのはもともとそもそも良くも悪くもマッドなのである。それでなければ精神の維持を優先する小市民のなかでやってられるか。(少なくとも以上のように思い上がっている)
例によって、遠回しな言い方になっているのであるが、はっきり言ってしまえば、ノーベル賞を取った人の人生や私生活などに注目しているマスコミの狙いは、山×教授をヘタレ庶民に引きずりおろすことであって、これが一番気にくわない。ルサンチマンの所産である。ノーベル賞とる人間だって普通の人間ですよ、だから何?家族の絆でノーベル賞が取れるのかよ。一応優れた業績を上げた人間に対して、これほど敬意を欠いた狂った時代があったであろうか?(たぶん、昔もあったけど……)
狂ってると言えば、黒澤映画の「生きものの記録」を思い出す。原爆水爆から自分の家族(妾とその子を含む)を守るために、ブラジルへ移住しようとし、家族から反対されたので、家族が執着する自分の家(工場)を焼き払ったため精神病院に入れられてしまった老人の話である。彼が狂気なのか、日本に平気に住んでいる彼以外が狂気なのか、この問題を突きつけるのがこの映画だが、まるで大江健三郎の小説の発想のもとになっているような作品である。主人公の「狂気」はどこからくるのか。映画をみていると、彼が案外原爆関係の情報に関し、メディアや人の言うことを疑いもなく信じてこんで突き進んでしまうことが重要かもしれないと思う。彼を向こう側の世界にまで追い込むのは、「ブラジルまで行っても地球を何回も吹き飛ばす量の水爆があるんだ」という近親者の言葉と、牢屋での同僚が面白半分に言った「地球から逃げリャいい」という言葉であった。これらをまともにうけとった結果、彼の精神は他の星に本当に飛んでいってしまった。原爆が落ちても原発が爆発してもなぜ我々は逃げないのか、この問題には我々があまり触れられたくない我々の精神的生そのものがあり、我々はこの映画を見終わったあと、原爆の恐ろしさより、その精神的生に悩まされ、そこから逃避してしまうであろう。ある意味で、この逃避は、主人公の逃避とも似ているはずであって、その証拠に、原爆関係の作品は、ある例外を除いてほとんどSFとして描かれているではないか。

すなわち、この黒澤映画は、おそらく前年上映の「ゴジラ」への根本的な批判である。ゴジラは水爆そのものである、しかも水爆ではないからである。その自明性を考察することは辛いから我々は常に逃避する。