本日は少し変わったところでシューマンとシューベルトのヴァイオリン協奏曲を取り上げたいと思います。2人とも言わずと知れた大作曲家ですが、ヴァイオリン協奏曲のイメージは正直言って薄いかと思います。シューマンのヴァイオリン協奏曲は生前一度も演奏されず、死後80年経ってようやく日の目を見たと言う曰くつきの作品です。現代ではシューマンのレパートリーの一つに加えられているとは言え、交響曲やピアノ協奏曲、チェロ協奏曲に比べるとまだまだマイナーな存在です。シューベルトに至ってはそもそもヴァイオリン協奏曲など存在したのかと思われるかもしれませんが、確かにヴァイオリン協奏曲そのものは作曲しておらず、いずれもヴァイオリンと管弦楽のためのに書かれた「コンツェルトシュテュック」「ロンド」「ポロネーズ」の3作品が存在するだけです。今回はそれらマイナー作品を取り上げたジャン=ジャック・カントロフ(ヴァイオリン)、エマニュエル・クリヴィヌ指揮オランダ・フィルハーモニー管弦楽団のCDを取り上げます。
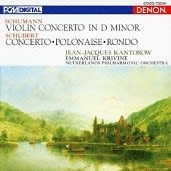
まずはシューマンのヴァイオリン協奏曲から。この曲は1853年に世界的ヴァイオリニストであったヨーゼフ・ヨアヒムのために作曲されましたが、一度も演奏されることなく封印されてしまいました。理由は曲の内容が気に入らなかったというよりも、ちょうどこの頃もともと精神を病みがちだったシューマンが自殺未遂を起こし、その後一度も心の病から回復することなく2年後に亡くなってしまったからというのが大きいようです。ヨアヒムが取り上げなかったのも妻のクララがこの曲の演奏を周囲に禁じたのも、曲の中に不吉なものを感じ取ったからかもしれません。実際に聴いてみると、そういう予備知識があるからかどうかわかりませんが、第1楽章の出だしが何とも暗く、重苦しく感じてしまいます。とは言え、「重苦しさ」とドイツ音楽の伝統である「重厚さ」というのは表裏一体でして、この重々しい冒頭部に続いて独奏ヴァイオリンが加わり、壮麗な響きの中間部へと展開していくあたりがこの曲のハイライトでもあります。続く第2楽章は穏やかな緩徐楽章、第3楽章は軽快なロンドで、重苦しさとは無縁なのですが、その代わりあまり個性がないというか、良くも悪くもあまり印象に残らない楽章です。この曲が現代にいたるまでイマイチ人気の出ない原因は第1楽章の「暗さ」より、第2楽章以降の特徴のなさが大きいかもしれません。
続いてシューベルトです。31年という短い生涯の中で、交響曲・歌曲・室内楽の分野に多くの傑作を残したシューベルトですが、協奏曲の分野には全く力を入れず、今日取り上げるヴァイオリンのための3つの協奏的作品があるだけです。それらも19~20歳の頃に書かれたいずれも1楽章のみの小品です。曲調はいずれもモーツァルトの流れを組む明るいもので、肩肘張らずに楽しめる内容ですが、深みと言う点ではやや物足りないのは否めません。その中では小協奏曲とも呼ばれる「コンツェルトシュテュック」が単一楽章ながら色々な旋律が盛り込まれていて楽しいです。わりと堂々とした序奏の後、3分過ぎからヴァイオリンがオペラのアリアのような歌心溢れる旋律を奏でます。続く「ポロネーズ」はさすがに軽すぎますが、最後の「ロンド」も悪くない。こちらも歌うような展開で、明るくポジティブに締めくくります。
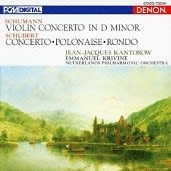
まずはシューマンのヴァイオリン協奏曲から。この曲は1853年に世界的ヴァイオリニストであったヨーゼフ・ヨアヒムのために作曲されましたが、一度も演奏されることなく封印されてしまいました。理由は曲の内容が気に入らなかったというよりも、ちょうどこの頃もともと精神を病みがちだったシューマンが自殺未遂を起こし、その後一度も心の病から回復することなく2年後に亡くなってしまったからというのが大きいようです。ヨアヒムが取り上げなかったのも妻のクララがこの曲の演奏を周囲に禁じたのも、曲の中に不吉なものを感じ取ったからかもしれません。実際に聴いてみると、そういう予備知識があるからかどうかわかりませんが、第1楽章の出だしが何とも暗く、重苦しく感じてしまいます。とは言え、「重苦しさ」とドイツ音楽の伝統である「重厚さ」というのは表裏一体でして、この重々しい冒頭部に続いて独奏ヴァイオリンが加わり、壮麗な響きの中間部へと展開していくあたりがこの曲のハイライトでもあります。続く第2楽章は穏やかな緩徐楽章、第3楽章は軽快なロンドで、重苦しさとは無縁なのですが、その代わりあまり個性がないというか、良くも悪くもあまり印象に残らない楽章です。この曲が現代にいたるまでイマイチ人気の出ない原因は第1楽章の「暗さ」より、第2楽章以降の特徴のなさが大きいかもしれません。
続いてシューベルトです。31年という短い生涯の中で、交響曲・歌曲・室内楽の分野に多くの傑作を残したシューベルトですが、協奏曲の分野には全く力を入れず、今日取り上げるヴァイオリンのための3つの協奏的作品があるだけです。それらも19~20歳の頃に書かれたいずれも1楽章のみの小品です。曲調はいずれもモーツァルトの流れを組む明るいもので、肩肘張らずに楽しめる内容ですが、深みと言う点ではやや物足りないのは否めません。その中では小協奏曲とも呼ばれる「コンツェルトシュテュック」が単一楽章ながら色々な旋律が盛り込まれていて楽しいです。わりと堂々とした序奏の後、3分過ぎからヴァイオリンがオペラのアリアのような歌心溢れる旋律を奏でます。続く「ポロネーズ」はさすがに軽すぎますが、最後の「ロンド」も悪くない。こちらも歌うような展開で、明るくポジティブに締めくくります。














