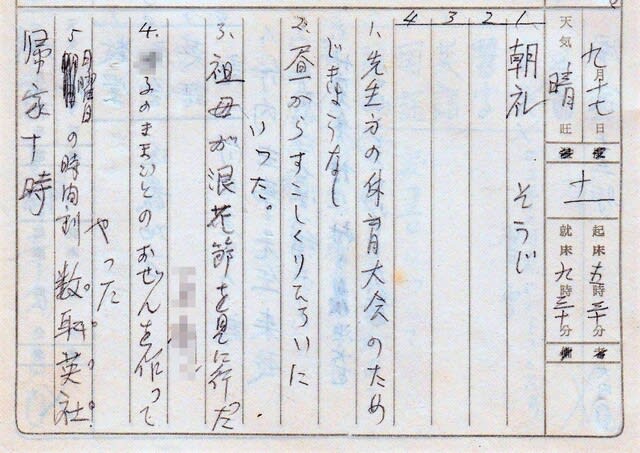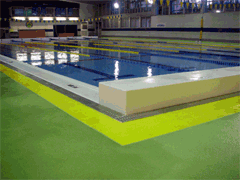足腰大丈夫な内に出来る限り、不要雑物処分・身辺片付け整理をしよう等と思い込んでからすでに久しいが、正直なかなか進んでいない。それでもここ2~3年には、押し入れや天袋、物置、書棚等に詰まっていた古い書籍類をかなり大胆に処分してきた。ただ、中には「これ、面白そう・・」等と目が止まり、残してしまった書籍もまだまだ結構有る。その中に 漫画家赤塚不二夫著、元東京学芸大学附属高等学校教諭石井秀夫指導の古典入門まんがゼミナール「枕草子」(学研)が有る。多分、長男か次男かが、受験勉強中に使っていた「枕草子」の解説本・参考書の一つのようだが、錆びついた老脳でもなんとか読めそうな、まんがで描いたくだけた内容、その内いつか目を通してみよう等と仕舞い込んでいたものだ。ながびく新型コロナ禍、不要不急の外出自粛中、ふっと思い出して、やおら引っ張りだしてみた。当然のこと、本格的な「枕草子」解説本、参考書とは異なり、限られたサワリの部分に絞ったものであるが、学生時代に多かれ少なかれ齧っていたはずの日本の代表的な古典、清少納言の「枕草子」も、ほとんど覚えていないし、「古典」に疎く、苦手な人間には、十分楽しめそうで、御の字の書である。(以上 過去記事コピペ文)
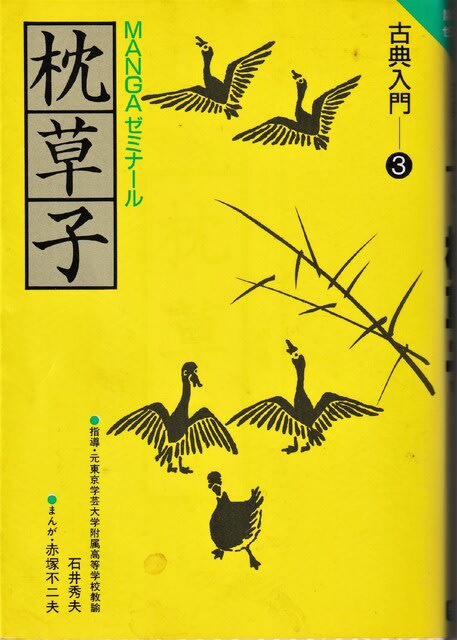
「中宮様は生涯の主人」・まんがゼミナール「枕草子」その11
第240段 「御乳母の大輔の命婦」
藤原道隆が生存中、中宮定子は実に幸せな境遇であったが、道隆の死後、叔父の道長の勢力が増大するにつれ、打って変わって、悲境のどん底に突き落とされることになる。定子の乳母大輔の命婦さえも、離れていくという事態となり、清少納言は、主君定子の寂しい心境を、同情の念をもって書き綴っている段。

おいとまのあいさつに参りました・・・。
おお、日向に参るか・・・。
中宮様の御乳母が 夫の転勤にしたごうて、
日向に下ることにならはりました。
まあ!、おっぱいのぎょうさん出そうなお方・・・。
ごらんおくれやす。こない立派な賜り物や・・・。
わあっ!、すごい!、中宮様の直筆サインやないの!
片面は 光うららな田舎の館。
もう片面は 雨ぬれそぼる京のさる所。
あかねさす日に、向かひても思ひ出でよ、
都は晴れぬながめすらむ と
みずからお書きになって、
中宮様はなんと心優しいお方どすやろ。
こないなお優しい主君から離れて、
とてもよそへ行けるものやあらへん。
日向はワテらには、地の果てみたいに遠く思われますんや。
原文だよーん
御乳母(おほんめのと)の大輔(たいふ)の命婦(みょうぶ)、日向(ひゅうが)へ下るに、賜(たま)はする扇(あふぎ)どものなかに、片(かた)つ方(かた)は、日いとうららかにさしたる田舎の館等多くして、いま片(かた)つ方(かた)は、京のさるべき所にて、雨いみじう降りたるに、
あかねさす 日に向かひても 思ひ出(い)でよ
都は晴れぬ ながめすらむと
御手(おほんて)にて書かせ給(たま)へる、いみじうあはれなり。さる君を見置き奉(たてまつ)りてこそ、え行くまじけれ。
(注釈)
中宮様の御乳母の大輔の命婦が、日向に下る際に、中宮様が下賜なさった扇の中に、片方には、日が実にうららかにさした田舎の建物等が多く描いて有り、もう一方には、雨が酷く降っている京のしかるべき所の絵が描かれていて、その扇には
日向に下っても、どうか思い出しておくれ
都では 私が長雨に閉じ込められて
心も晴れず物思いに沈んでいるだろう とね。
中宮様が御自筆でお書きあそばしたのは、実にしみじみと身にしみることだ。
私なら このようなご主君をお残しして、とても遠くへ等行けるものではないだろう。