イギリスってどうして階級間がスパッと分かれてんだろ?労働者階級と中上流者階級の隔たりの大き!っていったいどうやってできたんだ?暮らしぶりがまるで違うじゃないか。スポーツだって、サッカーは労働者、クリケットは中上流のもの、服装や食事や趣味だってくっきりと異なってる。今じゃ、かなり流動的になってるようだけど、どちらの層でも、自身の帰属感覚ははっきり残っているようだ。
それに引き換え、日本はどうよ?まったく判然としないじゃないか。食うや食わずの生存限界線上の人たちも、1回7万円の食事を楽しむ人たちも、階級としての対立感情はあまりない。最近、ようやく上流国民って言葉が現れて、少し意識化されるようになったが、なんとなく同質の感覚は変わらない。当然、労働者階級なんて言葉にプライドは付随していない。金持ちたちも取り立てて、差別を煽るような行動には出ていない。高度経済成長期に広く行きわたった中流意識が幻影のままに漂っている。
イギリスと日本、この違いはいったいどこから生まれてきているんだい?
そこが知りたいって思うようになったのさ。きっかけは、Netflix映画『ピーキー・ブラインダーズ』とか、『イングリッシュゲーム』を見たことだ。あと、アイルランドだが、『リベリオン』なんかも。
もう、歴然だよな、両者の違いは。特にプロサッカー創世時代を描いた『イングリッシュゲーム』は、二つの階層の暮らしから意識までその隔たりの大きさが物語の重要なバックグラウンドになってる。例えば、プロの存在、中上流階級にとってはスポーツで金を得るなんてことは、到底信じられない、認められない。その金持ち趣味チームに、地方の弱小チームがプロを雇って戦いを挑む、その中心エピソードをたどりながら、当時(19世紀後半)の興味深い様子を伺い知ることができる。
女性の選挙権を求めて果敢に戦ったサフラジエットの存在にも大いに惹きつけられた。同じ女権拡張運動でも、日本ではとても成し得なかった運動のあり方、例えば、違法行為を繰り返して入獄を繰り返す戦法とか、は何故可能になったのか?
こりゃイギリスについて、もっと知らなきゃならんよな。特に近代史を。
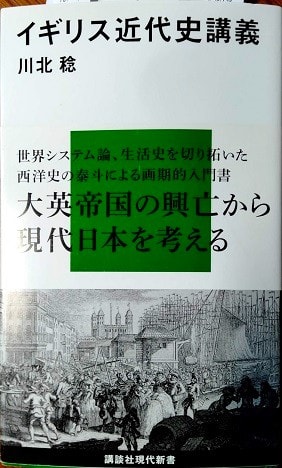
取りあえず、読んでみたのが、『イギリス近代史講義』川北稔著、講談社現代新書だ。歴史の本だし、新書だし、近世のイギリスの出来事が軽く編年的に記述されてるものか、と思ったら。これがまったく違った。何年に何がどうした、なんて記述はほとんどなし!書かれているのは、イギリスの都市とは何か、どのように成立したか、産業革命への新しい観方、そこから現在のイギリス衰退論への言及と、これはこれは、なんとも刺激的かつ挑戦的な本だった。
産業革命を生産手段の変革から見る従来の史観に対して需要消費から見るとか、ロンドンの貧民街は工場労働者のたまり場ではなく、港湾の荷受け関連に群がった地方出の貧民の住処だったとか、それを成り立たせた消費都市ロンドンのあり方とか、もうもう、目が覚める指摘ばかりだ。目的意識などなくても、知的な謎解きとしてもまったく飽きない。
イギリスは何が違う?という、こちらの問題意識についても、幾つか貴重なヒントをもらうことができた。一つは、中世以降、イギリスは極端な晩婚社会であったこと、核家族中心であったことだ。理由は、10年近い徒弟奉公が男女ともに広く行われていたことだ。徒弟期間を過ごした男女は、一人前と認定され、両親とは別に居を構え仕事を持つ。老親の面倒を面倒見るという仕切りたりはまったくなく、寡婦や孤児、老人の世話は、地域の金持ち層の役割とされていた。つまり、広義の福祉政策だ。
この金持ち層、ジェントリーの暮らしや意識、これがまったくの目から鱗だった。彼らはただ富裕だということではなく、働かずに財を得ることが資格の一番のもっとも重要なポイントであるということ。耕作とか製造には一切かかわらない。体を汚す仕事をすれば、それはジェントルマンではなくなる。彼らの任務は、地主や富裕者として、全体を差配することなのだ。この傾向は今でも続いていて、ケンブリッジやオックスフォードの卒業生は、製造業のトップに就くことはなく、金融や貿易などに就職すると言うのだ。
これは驚きだ。こんな階層が生きているのなら、対となる労働者階級だって強固に生き残っていて当然だ。この認識は、もっともっと考えてみなけりゃならない。ただ、問題解決の大きなヒントになることは間違いない。
ほんと、歴史てのは、しっかり見ておかないとダメだってことだ。ごくごく常識と思っていたことが、とんでもの事実に裏切られたりする。今について認識するにも過去をしっかりたどっておくことが重要なんだってことを思い知らせてくれた貴重な1冊だったぜ。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます