北小金駅の駅スタンプの絵柄になっている「本土寺のアジサイとしょうぶ」。

この時季はアジサイもしょうぶも咲いてないが、本土寺は千葉県屈指の紅葉の名所であるという。
スマホさんの紅葉情報によると、本土寺の紅葉は「見ごろ」を迎えていた。
ということで、「飛電」を留めていた北小金駅東口のイトーヨーカドーから出発。
スマホでGoogle Mapを確認し、北小金駅東口から本土寺までの最短経路を確認すると・・・駅構内を突っ切って西口に出ろってか!?
(最短経路をてっとり早く調べるため、徒歩経路の検索を使っている)
自転車かついでペデストリアンデッキに上がるのはきびしいので、Mapを確認しながら進むことにした。

ちょいと遠回りして進むこと7分、850m。

並木連なる参道を抜け、仲見世へ。

だいたい150mほど進み、木々を羽織った山門(仁王門)に到着。

仁王門をくぐると、色とりどりの楓が参拝客を出迎える。

全体的には、紅葉は色あせ始めていた。1週間くらい早く来ればよかったのかな。

振り返れば、紅葉は仁王門を暖かく包んでいる。

お、楓が3色そろっている。
赤赤赤、黄黄黄、緑緑緑・・・こいつは三色同刻だ!!
などと無粋な連想するのは私だけであろう(^_^;)
文永6年(1269年)に蔭山土佐守が建てた法華堂を、建治3年(1277年)に曽谷教信がこの地に移し、日蓮の弟子である日朗が開堂供養したのが本土寺のはじまりであるという。
池上の長栄山本門寺、鎌倉の長興山妙本寺とともに「朗流の三長三本」と称される。
(「朗流」は日朗の門流、「三長三本」は山号に「長」、寺号に「本」の字を含む3寺を表している)

仁王門から先の境内に入るには、受付で拝観料500円を支払う必要がある。

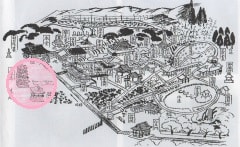
まずは五重塔と鐘楼。

鐘楼の中にある梵鐘【国指定重要文化財】は鎌倉時代に造られたという。
梵鐘は見えないが、傍らの紅葉がなかなか見事。

五重塔と、陽光に照らされる紅葉。
五重塔は平成3年建立と、比較的新しい。
続いて本堂へ。


本堂の紅葉はもう終わりかな。

本堂脇の仏塔の紅葉。
本堂の裏手には歴代住職の墓と、それとは少し離れた墓がある。

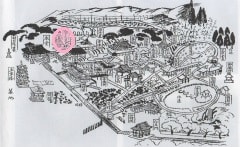
秋山夫人墓所【松戸市指定文化財】。
秋山夫人は武田家臣・秋山虎康の娘で、徳川家康の側室となり武田信吉を産んだが、1591年この地で逝去。
武田信吉はのち水戸藩主となったが、子がなかったため断絶となった。
秋山夫人の墓は、信吉の甥にあたる水戸藩主・徳川光圀によって建立された。

本堂の裏手は西日に照らされ、終焉を迎えつつある紅葉が最後の輝きを見せる。


6月には多くの人でにぎわうアジサイ園も、今はちと寂しい。
アジサイ園を抜けると竹林が見えてきた。

常緑の竹林と紅葉。


竹林を抜け、開けた場所にある菖蒲池。
季節外れの池はアタリメのように干からびていたが・・・

池向こうの銀杏がいいアクセントになってますなぁ~。
歩みを進め、菖蒲池の向かい側。


このあたりはまだ色あせていない紅の錦が残っていた!

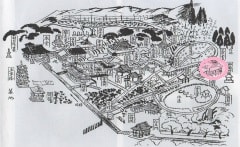
もみじに彩られた像師堂。


さきほどまでいた菖蒲池の対岸には、宝物殿が建つ。
日蓮上人直筆の書が保管されている。

正面からの像師堂。こちらはもみじが控えめ。
像師堂から順路に従って進むと、池沿いの道へ。

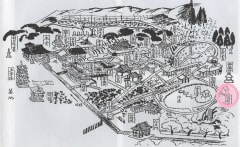
分かれ道の先にある稲荷堂。紅葉と鳥居の色がほとんど同じですな~。

本土寺の高僧・日像上人像。
日像は、本土寺開山の祖・日朗の異母弟にあたり、ともに日蓮の弟子であった。
日蓮は京都での布教と禁裏(朝廷)の帰依を、当時13歳の日像に託して入滅した。
日像はその遺命に従い、他宗や禁裏の迫害を受けながらも布教に努め、ついに後醍醐天皇からの帰依を得た。


こぢんまりした瑞鳳門は、紅の冠を装う。

池周りの紅葉はもうすっかり色あせていたが、水辺から離れている木々はまだまだ赤い。


寺内施設の入口である赤門は、赤に限らぬ錦をまとう。

おっ! 見事な赤だねぇ。


花のないアジサイと五重塔。
入口でもらったパンフレットとほぼ同じアングルなんだけど・・・。
心の眼で咲き乱れるアジサイを想像してくださいな・・・。
入口に戻ってきた。

最後に、紅葉に包まれる仁王門をもう一度。









