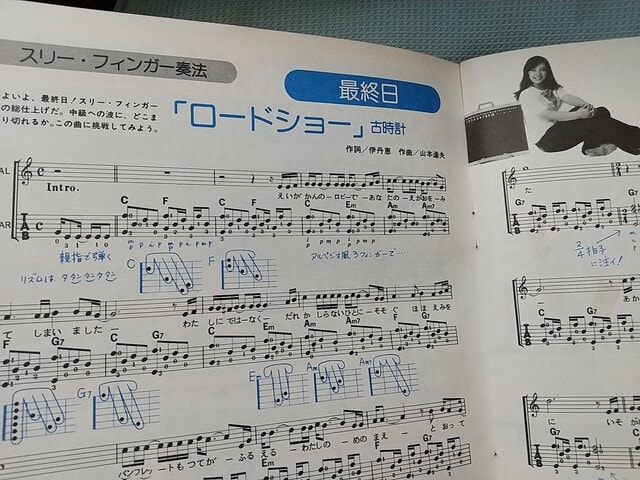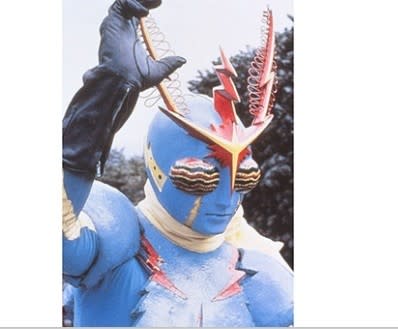NHKの「ラジオ深夜便」は、あとで曲目リストを見て「うわー」となることも多いので、タイマーセットしておいて聞いてみれば、良ければ残す、好みでなければ聞かないというのができるので便利です。
それにしても驚いたのは、今回の特集で曲紹介とか時代劇の解説でアナがちょっと間違った場合は、すぐリスナーから指摘が入って訂正するというのが何回かあったこと。深夜便をリアルタイムで聞いてる人は多いんですね。てっきりトラックドライバーのリスナーが多いと思ってたのですが、運転中だとすぐメールするのは難しいですしね。どうなのでしょう。
そして、「らじるらじる」の聴き逃しにないのでタイマー録音が重宝する「夜のプレイリスト」は、今週はサンプラザ中野くんが登場。あの人がどういうチョイスをするのか興味あったので録音したところ、初日は「かぐや姫LIVE」でした。1974年のライブ盤で、当時中学生だったそうなので、私よりは少し年代が上ですね。このアルバムを選んだのは、意外なような意外で無いような。
このアルバムは持ってなければ聞いたこともなかったのでラッキーでした。聞いてみたいアルバムを、思い入れのある解説付きで聞けるのはいいですね。ということで、ラジオサーバー活躍中です。今夜は何が出ますやら。