The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―74. ISOを取引条件にしても、顧客にとってのメリットは少ない?”
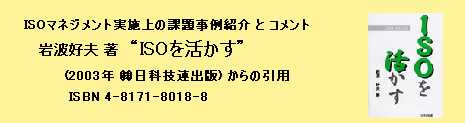
久しぶりの“ISOを活かす”です。今回は、経営の入札条件の看板としてのみのISO9001認証の品質マネジメントシステムがテーマです。
【組織の問題点】
建設業のA社は公共事業の土木工事を主な事業にしているため、入札条件に必要なISO9001の認証取得しています。
しかし、この3年是正処置や予防処置の事例が全くありません。
A社の社長は“ISO9001認証は取引には必要だが、それ以外には役立たなくても仕方がない”と考えています。
このような事例から、ISO9001認証取得を取引条件にすることは、顧客にとって有効なのでしょうか。
【磯野及泉のコメント】
私は A社の社長の考え方は 経営者としては一つの典型だろうと思います。つまり、“何だか面倒なISO9001の品質マネジメントシステム” ではあるが、入札条件という企業存続にかかわる問題であれば、少々コストがかかっても仕方ない。“ISO9001認証取得”は 看板として必要な、というか“必要経費”としてみなしているのでしょう。
ここで、著者・岩波氏はISO9001の本来の目的について指摘しています。つまり“ISO9001は、商取引すなわち二者監査(購買先監査)のために使用されていました。” それを 一々購買先に監査に行くのが面倒なので、第三者機関である審査会社に委ねて、監査結果を認証してもらい、その認証を保証として取引に入るというやり方になったというのです。したがって、ISO9001の認証取得を顧客が要求するのは当然考えられることなのです。従って、“ISO9001認証取得を取引条件にすることは、顧客にとって有効”な はずなのです。
しかし、もう一つのISO9001認証取得の付随効果として、“企業の経営改善に役立たせることができる”ということがあります。これが見落とされていることが多いと 著者は強調しています。
このように、一旦 ISO9001の認証を取得したのならば、これを経営に生かして行くべきだろう、と考えるのは私も含めてISO9001の業界の中に居る人々の発想です。ところが、どうやら経営者は“ISOは面倒だが入札のための必要経費”だとしか考えていないことが多いようです。ここに、経営者とISO9001業界人との認識の大きなギャップが認められます。どうしてこうなったのか。これが 日本のISOマネジメントの根本的問題だろうと思うのです。
認識ギャップの原因の一つは ISO9001の品質マネジメントシステムを構築する際に、経営者が“ISO9001を経営のツール”と認識するようにコンサルタントが十分に説明しなかったか、あるいは認証取得を焦った経営者が その説明を十分に理解し受け止めなかったことだと思われます。
このように経営者の理解が 得られないのは ISO9001の認証そのものへの信頼性が乏しいからではないかと思います。
事実、不祥事などの事件を引き起こした企業に ISO9001認証取得の会社が多いようです。あたかも、不良な企業がそれを覆い隠すための認証取得であるかのような印象さえ受ける現状です。それが、“ISO9001認証取得”への世間の目が “尊敬”というより“普通”というか “お飾り”程度にしか見なくなったという結果につながったのでしょう。
そして、審査機関もそのような経営者意識を覆す努力もせず、クライアントたる経営者におもねるような“甘い認証審査”を行い糊塗しているという面もあるのではないかと思うのです。
“甘い認証審査”は、今回の事例でも見てとれます。“3年間是正処置や予防処置の事例が全くありません。”で、毎年の審査機関による定期審査というか維持審査は どうなっていたのでしょうか。
是正処置・予防処置のきっかけは 色々あるはずですが、3年間全くないというのは異常としか言いようがありません。
是正処置の無い裏返しとして、不適合の発生が 本当に3年間無かったのでしょうか。不適合が無いのは 事前の予防処置が完璧だから、というのは論理的で十分に理解できます。ならば 予防処置は出ているはずです。
是正処置・予防処置が何も無いというのは ISO9001QMSが死んでいると 単純に判定できるのではないでしょうか。なのに“是正処置・予防処置が全く無い”ままな その状態を審査員は見過ごしているのです。審査の重要なポイントだと思うのですが。それに、第三者審査でも 不適合や観察事項が出されれば“是正処置”は せざるを得ないと思うのです。このことを見ても、このA社の審査員が“甘い認証審査”を やっているとしか思えません。
こういう“甘い認証審査”になるのには 様々な原因があると 私は考えていますが、これに言及するとこの事例の問題の核心からそれてしまいますので、それは後日にしたいと思います。
とにかく、もう少し企業経営者にISO9001の意義を理解していただき、本気で しかも主体的に取り組んでもらうことが、大いに望まれます。
つまり、是正処置が継続的改善への重要な契機になるものであるという認識に立てば、“3年間是正処置の事例が全く無い。”ということが、非常に“異常な状態”であると経営者自身は 当然気付くでしょう。そして、少なくともマネジメント・レビューでそれを指摘し、管理責任者をはじめ全社員に注意喚起するべきだと思うのです。(別に形式張ってマネジメント・レビューで言わなくても 日頃の発言で十分だとは思うのですが。)
それから、建設工事現場では、日々の作業開始前に いわゆるKY(危険予知)が必ず実施されているものと思います。これは その日に予定される作業要素に危険なものはないか、点検し、作業方法や危険箇所の確認によって 危険回避の方法を講じ、作業者の安全を確保しようという活動です。
このKYこそが、予防処置そのものであり、それらの記録を累積し、類似の危険対処には 次々と恒久対策を講じることがA社の継続的改善というより、結果的に驚くような体質改善につながって行くものだと考えます。
また、こういう“予測”という行為は 人にイマジネーションを喚起させることにつながりますので、社員への教育効果は 想像以上に大きいものであると思っています。仕事の結果を予測できるようになると、自分が業務の主人公になったような気分になるからです。そうなると“仕事のやらされ感”が霧消してしまいます。
このKYで危険要素を洗い出した時、最後に “私ならこうする” という 決意にも似た 予防策を記述することになっていますが、私は この一言も、ISOマネジメントにとって重要なキィ・ワードではないかと考えています。“私ならこうする” という主体的、積極的取り組みが あらゆる階層を通じてQMSが運営されれば、その企業は生き生きした企業に変身するでしょうし、経営者は そうなるように心掛けるべきでしょう。これは非常に大切なことではないかと思っています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 福田氏の投げ出し | アメリカ型市... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




