The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―23. 知的所有権の保護によって、顧客満足度を向上させる”
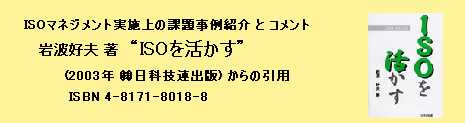
このシリーズも 早いもので そろそろ三分の一を経過しようとしています。
元々、私のISOマネジメントについてのイメージを表明するのに どうすれば良いか考えた時に、この本はテキストとして適当であると感じたものでした。例えば 私が ISOマネジメントの私的なセミナーを開催する時にこの本を テキストにして、そこでコメントするというような そういう状況があったとして、それを ブログで公開する、そういった企画のつもりでした。
そういう軽いつもりで、始めておりますので、このブログ記事のシリーズは著者の岩波氏には何の断わりも ご挨拶もいたしておりません。
しかしながら そのコメントには 受け取り方によっては、著者・岩波氏を 論難するような内容もあったかも知れませんが、私としては こういう形でしか 今のところ自分のイメージを語る方法を 持ち合わせておりません。
岩波氏には 本の企画によって 1件2ページの解説スペースしか有りませんが 私にはコメントするのに十分の自由な 広さがあり、その分 十分に言いたいことが言えるという有利な立場であるということも了解いたしております。
そういう訳で、私には 著者への気持ちは全くニュートラルですので、悪しからず ご了解いただきたいと思っています。
さて、今回は “知的所有権”というよりも、新製品に関する顧客情報管理の問題です。
【組織の問題点】
3年前にISO9001認証取得した アルミ加工メーカーのA社は、携帯電話ケース(外殻)などを製造しています。
このA社では、文書や記録は事務所の書棚にセンターファイルとして保管しており、これは原則 だれでも自由に見たりコピーをとることが可能になっています。顧客関連の図面や仕様書も同じように 管理しているとのこと。
ところが、このA社の客先 電話機器メーカーB社の近く発売予定の新製品とそっくりの形の携帯電話が、海外のメーカーから先に発売されてしまい、A社はB社からこの新製品の注文がもらえず、キャンセルされてしまったとのことです。
A社は、顧客の図面や仕様書をどのように保管すれば顧客満足を向上させられるか、という課題です。
【ISO活用による解決策】
著者・岩波氏は 顧客所有物についてのISO9001の規定要求事項7.5.4から説明しています。
“①顧客の所有物について、識別し、保護すること。/②顧客の所有物には知的所有権も含まれる。
顧客の所有物としては、一般的には顧客から支給された部品や材料などがあります。これらの顧客支給品について・・・取り扱いに注意して保護することが必要です。そして2000年版では②の知的所有権が追加されました。これには、顧客の特許、実用新案、意匠などがあります。A社の場合は、携帯電話ケースの図面などがこれに相当するでしょう。”
そして、次のようにも指摘しています。“顧客の知的所有権は、顧客から支給された仕様書や図面に限定されるとはかぎりません。顧客の要求や打合せにもとづいて、企業で作成した図面や金型などにも含まれていることもあります。”
そして情報漏洩には 注意するべきである、として“顧客の知的所有権の情報は、保管棚にカギをかけたり、それを取り扱う人を限定するなどの方法が必要でしょう。” と 言及しています。
【ポイント】
この事例での 著者の総括は 以下の通りです。

【磯野及泉のコメント】
このISO9001の7.5.4項は 1994年版では “顧客支給品”となっていました。それを 2000年版では 物品ばかりではなく、“知的財産(知的所有権)”も 含めようとして“顧客の所有物”にしたと いうことです。著者・岩波氏の意図は その紹介に有ったと思われます。
このISO9001の7.5.4項に相当する ISO9004を ご参考までに下に 紹介します。ここには、“顧客の所有物”の事例が記載されています。(枠線内が ISO9001の要求事項そのものです。ISO9004は このようにISO9001を補足するように 比較的具体例に近い事項を紹介している 推奨規格です。)

顧客所有物に含まれる“知的財産(知的所有権)” 即ち 情報について、それを保護するための 情報管理は 当然 重要な課題ですが これはISO9001の範囲を越えています。この問題はISMS(Information Security Management System)の範疇に入りますので 詳細な説明は省略させていただきます。ISMSも 他のISOマネジメントと基本は同じ要素(PDCA 等)で出来上がっています。
ところで、この事例では A社の情報管理不十分が 原因で海外のメーカーに漏れたとは 直ちには思えません。
蛇足かも知れませんが、B社からの発注がキャンセルされたのは、A社を原因と見たB社の報復ではなく、B社が戦略的に新製品の発売を見送ったためと見るのが 穏当な解釈だと思います。
情報漏洩対策には 単なる小手先の情報管理だけでは不十分だと思われます。それよりも人の管理が重要になると思います。意図的に情報を盗もうとする人には どんな情報管理も 困難だと思われるからです。
細々したルール化による情報管理より、自由で旺盛な士気の従業員が大勢いることの方が 情報漏洩の危機の可能性は はるかに低いと思われます。もちろん その従業員への情報管理に関する適切な教育が 前提です。
従業員の 高い士気の維持は組織運営の基本だと思います。組織内での 情報の共有は 全社一丸・全員参加の前提です。しかし、無原則な社外への情報の漏洩は問題です。この矛盾を 組織は 適切に 処理しなければなりません。そのためのISMSであると考えます。つまり 組織の内部統制と従業員規律の維持が より重要でしょう。
信頼される組織とは 規律が有り、なお且つ 活き活きした組織だと思うのです。
“言うは易く、行うは難し。” でしょう。ですが、経営者が 言い出さなければ 到底 実現は しません。“先ず 言葉ありき” それがリーダー・シップだと思うのです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 地震の予測 | 参議院の有効... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




