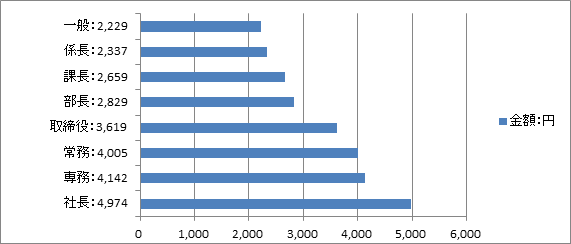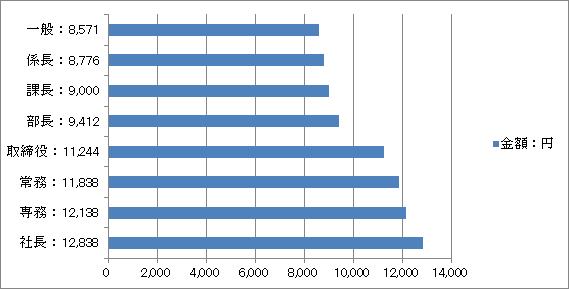皆さん、こんにちは。
安倍総理が10/15に消費税10%を表明しました。ただ軽減税率の問題が多々出てきています。
解決策がないまま、時間が過ぎています。2019年の夏の参議院選でもう一波乱あるかもしれませんね。
実は私も消費税増税前に購入検討したいものがあります。それは車です。
でも、車は車体本体価額だけではありません。たくさんの費用や税金が掛かります。購入時の悩みです。
また、この仕事で悩むのは、お客さんが車両を購入した場合の仕訳や消費税区分も悩みます。
カタカナやアルファベットが羅列されている、ごちゃごちゃした見積書・請求書ですし、パーツの名前にいたっては何の事かよく分かりません。
そんな時は下記の5分類に分けると良いと思います。実際に私も請求明細のコピーに①~⑤と番号を付けて電卓で集計します。
1.分類
①車両本体・付属品・納車費用・・・消費税課税
全て車両本体の取得価額となります。
納車費用は、販売店から購入者への納入にかかる費用であり、自動車の購入のために要した付随費用にあたり、取得価額に算入する必要があります。
②税金・・・消費税不課税
自動車税・自動車取得税・自動車重量税などの税金は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。
③保険料・法定費用・・・消費税非課税
自賠責保険料、及び法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。
④リサイクル関連費用・・・消費税不課税
シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金は、廃車時に自動車の廃棄というサービスを受けるための費用となりますので、購入時は預託金として処理します。
余談ですが、リサイクル関連費用消費税のポイントは、取得時は不課税、譲渡時は非課税売上(有価証券の譲渡と同じく5%対価に参入)、廃車時は費消するので課税仕入です。
⑤各種手続の代行費用・資金管理料・・・消費税課税
検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用は、上記の法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)に関する手続の手数料であり、損金として処理できます。
資金管理料金は、前述の④の預託金の管理に対する手数料であるため、自動車購入時に損金として処理できます。
車を買うのにいくつも税金を払うのだから、販売店の見積書を国の主導で統一フォーマットにしてくれれば良いのに・・・といつも思っています。
2.その他
①取得価額に含める物の注意
自宅まで移送してもらうなどの費用や関税は納車費用として取得価額に含まれます。
割賦手数料や保険料は期間に注意して前払費用などに振り分けてください。
②取得価額に含める物の任意処理
自動車取得税や法定費用は、取得のための直接必要であるため取得価額に含めなければならないような感じもしますが、購入による事後的費用であり、取得価額に含めるかどうかは任意とされています。
自動車税・自動車重量税・自賠責保険料は、「取得」というより「所有」することによって生ずるものであり、取得後に発生する費用と考えられるため取得価額に算入しません。
③任意処理による仕訳処理
任意処理による仕訳は、課税対象の車両運搬具と、不課税の車両運搬具、非課税の車両運搬具が出てきますので課税区分には注意してください。
車両運搬具(課) 100
仮払消費税等 8
車両運搬具(不) 5
車両運搬具(非) 5 → 固定資産台帳には車両運搬具 110(税込なら118)で登録。
ちなみに自動車取得税は、消費税が10%になった場合、廃止の予定になっています。確かに二重課税ですね。
新型ジムニーは、デザインとカラーが良いので検討していたのですが、燃費があまり向上しなかったので、家の総理兼財務大臣が首を縦に振りません。
HPはこちらから www.fukuda-j.com
監査部1課 吉野伸明