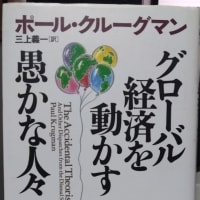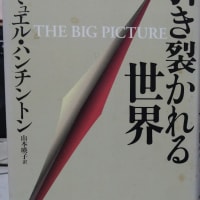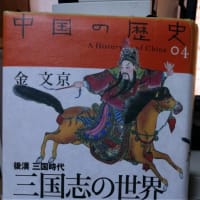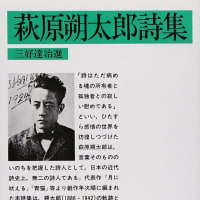お盆の季節である。お墓参りをする人たちを見かける。日本人の土俗的信仰心は、未だに健在である。無意識なものであっても、日本人においては、生者と死者とが一体なのである。
柳田国男の「死んでも死んでも同じ国土を離れず、しかも故郷の山の高みから永く子孫の生業を見守り、その繁栄と勤勉とを顧念して居るものと考へ出したことは、いつの世の文化の所産であるかは知らず、限りもなくなつかしいことである」(「魂の行方」)の言葉は今も息づいているのだ。
東北地方南部を中心にして、日本中どこでもハヤマがある。葉山、端山、羽山、麓山と書かれることが多く、子孫の集落を見下ろせる里近くの山をそう呼ぶのである。
柳田はそうした信仰を語るにあたって、それを「考へ出した」私たち日本人の先祖に対して、畏敬の念を抱いた。あの世に去ることもなく、身近にとどまっている死者の声を聞く、それこそが、日本の国柄を保守する者の立場でなくてはならないのである。
葬式は仏教で、お祓いは神道で、さらにはクリスマスまでも祝う日本人であっても、根底にある土俗的信仰は、失われずに引き継がれているのだ。「先祖の顔に泥を塗りたくない」という素朴な感情がある限り、日本はまだまだ捨てたものではないのである。
柳田国男の「死んでも死んでも同じ国土を離れず、しかも故郷の山の高みから永く子孫の生業を見守り、その繁栄と勤勉とを顧念して居るものと考へ出したことは、いつの世の文化の所産であるかは知らず、限りもなくなつかしいことである」(「魂の行方」)の言葉は今も息づいているのだ。
東北地方南部を中心にして、日本中どこでもハヤマがある。葉山、端山、羽山、麓山と書かれることが多く、子孫の集落を見下ろせる里近くの山をそう呼ぶのである。
柳田はそうした信仰を語るにあたって、それを「考へ出した」私たち日本人の先祖に対して、畏敬の念を抱いた。あの世に去ることもなく、身近にとどまっている死者の声を聞く、それこそが、日本の国柄を保守する者の立場でなくてはならないのである。
葬式は仏教で、お祓いは神道で、さらにはクリスマスまでも祝う日本人であっても、根底にある土俗的信仰は、失われずに引き継がれているのだ。「先祖の顔に泥を塗りたくない」という素朴な感情がある限り、日本はまだまだ捨てたものではないのである。