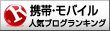尾崎健一氏は祝嶺正献先生に空手道、躰道の指導を受けた人。 躰道師範協議会副会長。
ロック歌手・尾崎豊氏の実父であります。
躰道壮年倶楽部講演会の資料より掲載しています。
**************************************
「祝嶺正献先生との出会いと躰道を学ぶ息子達」(その7) 尾崎健一
②先生の武道家へのデビュー
自衛隊を去られて間もなく、恐らく昭和三十一年春だったと思います。
先生は満を持した如く、武道家へのデビューを華々しく果たされたのです。
当日の思い出を再現します。
ところは、神田共立講堂。舞台正面には三十数枚の瓦が積まれている。
客席の私からはよく見えないが、たぶん数枚のコンクリートブロックがその下に敷かれている筈である。
舞台右ソデから、道着姿も凛々しい先生が静かに現われ、積まれた瓦を前にして客席に一礼された。
この頃は、まだ白黒のテレビが漸く町角などに出始めた頃で、場内には武道新聞の記者らしい人たちは多くきていたが、テレビ撮影は勿論ない。
今なら早速民放でライブ放映されるはずの名場面である。
それに、残念乍ら私もまだカメラなど持っていなかった。
最前列の席で、私はその瞬間を待った。
場内寂として、観客は息を殺し、一瞬静寂が凍りつく。
下から見上げると、三十数枚の瓦は先生の腰の辺りにまで及んでいる。
何しろ、五枚の瓦割りに苦労している私である。
祈る気持ちであった。
裂帛の気合が、凍りついた静寂を破った。
全身の力が、右肩から腕に流れ先生の手刀はグズッとにぶい音をたてて瓦の上にくいこんだ。
万雷の拍手が湧く。
だが、私はまだ心配だった。
高さの半分位までは左右に割れているが、更に下方の状態がよく判らない。
成否は。
と客席は固唾をのむ。
やがて介助者が現われて、積まれた瓦の片側を静かに引き離すと、積み重ねた瓦の中心線は見事に最下部の一枚まで左右に割れたのである。
成功。
再び場内には割れんばかりの拍手が鳴りひびいた。
先生は、再び静かに一礼して舞台を去られた。
安心と、喜びが余りに大きかったせいか、遠い日の事でもあり、このあとのことを私は良く思い出せない。
先生が、武道家として躰道をひっさげて、見事にデビューされた一瞬であった。(つづく)
ロック歌手・尾崎豊氏の実父であります。
躰道壮年倶楽部講演会の資料より掲載しています。
**************************************
「祝嶺正献先生との出会いと躰道を学ぶ息子達」(その7) 尾崎健一
②先生の武道家へのデビュー
自衛隊を去られて間もなく、恐らく昭和三十一年春だったと思います。
先生は満を持した如く、武道家へのデビューを華々しく果たされたのです。
当日の思い出を再現します。
ところは、神田共立講堂。舞台正面には三十数枚の瓦が積まれている。
客席の私からはよく見えないが、たぶん数枚のコンクリートブロックがその下に敷かれている筈である。
舞台右ソデから、道着姿も凛々しい先生が静かに現われ、積まれた瓦を前にして客席に一礼された。
この頃は、まだ白黒のテレビが漸く町角などに出始めた頃で、場内には武道新聞の記者らしい人たちは多くきていたが、テレビ撮影は勿論ない。
今なら早速民放でライブ放映されるはずの名場面である。
それに、残念乍ら私もまだカメラなど持っていなかった。
最前列の席で、私はその瞬間を待った。
場内寂として、観客は息を殺し、一瞬静寂が凍りつく。
下から見上げると、三十数枚の瓦は先生の腰の辺りにまで及んでいる。
何しろ、五枚の瓦割りに苦労している私である。
祈る気持ちであった。
裂帛の気合が、凍りついた静寂を破った。
全身の力が、右肩から腕に流れ先生の手刀はグズッとにぶい音をたてて瓦の上にくいこんだ。
万雷の拍手が湧く。
だが、私はまだ心配だった。
高さの半分位までは左右に割れているが、更に下方の状態がよく判らない。
成否は。
と客席は固唾をのむ。
やがて介助者が現われて、積まれた瓦の片側を静かに引き離すと、積み重ねた瓦の中心線は見事に最下部の一枚まで左右に割れたのである。
成功。
再び場内には割れんばかりの拍手が鳴りひびいた。
先生は、再び静かに一礼して舞台を去られた。
安心と、喜びが余りに大きかったせいか、遠い日の事でもあり、このあとのことを私は良く思い出せない。
先生が、武道家として躰道をひっさげて、見事にデビューされた一瞬であった。(つづく)